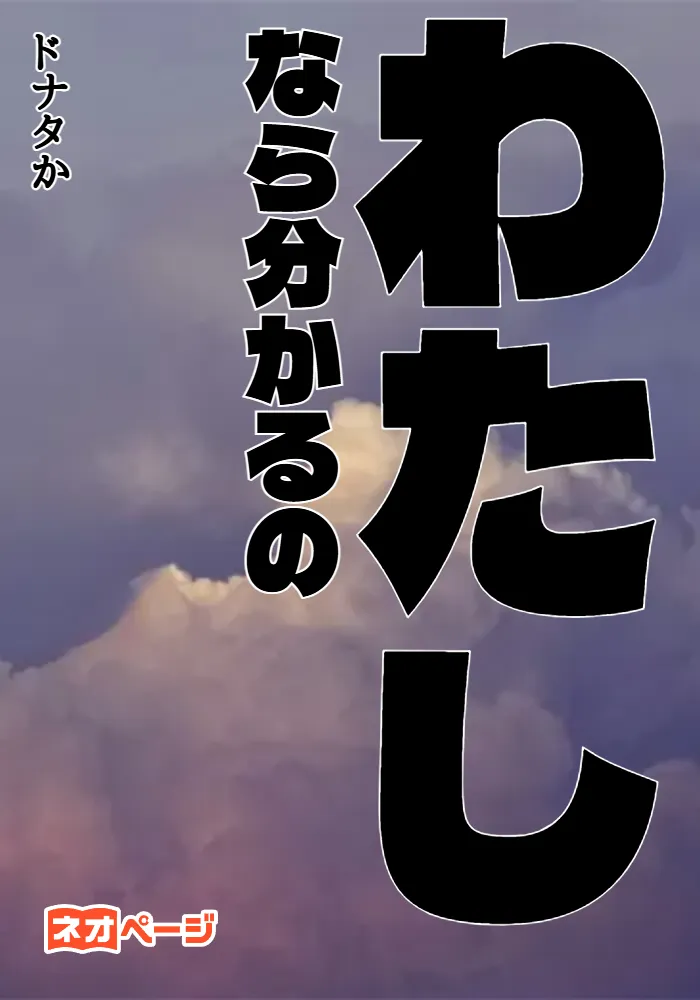
公開日
連載中
ん
ねえ、あなたはどうして、キザなのかしら。
わたしは思うの、あなたはどうしてそんなにカッコイイのかなって。どうしてそんなにイケメンで、どうしてそんなに気遣い上手なのって。わたしと付き合うのが初めての恋愛ともいうけども、それが嘘に思えるくらいに、女を知り尽くしているような甘い視線が色気溢れてて、もうたまらなかった。
百人、いや、千人くらいぺろりと食べてしまったのでしょ? 隠さなくて、いいの。わたしにだけはね。
わたしはあなたのことをとても好いているの。だってあなたは、わたしの一番。わたしのモノ。わたしの希望。わたしのマイノリティ。ねえ、それは、キザだって? あらいやだ、誰の、真似かしら。でもね、言わせて。あなたは、キザで、とたんにどこかに行ってしまいそうな儚さが似合っている。それをわたしは、とても、嫌いなの。あなたは、わたしの、モノだから。
甘くてとろけたいよね。でも、さ、それでも、しにたい?
ざんねん。
まだまだだよ。
あなたはわたしの一番ですもの、最後に食べるの。あなたのそのあどけない顔も、細い指も、すらりとした体も、汚い爪も、全部が、まるでわたしの為にあるみたい。女にとってあなたは禁断の果実。見るだけじゃダメ、触るだけでもダメ、でも、嗅いだらもうおしまい。その魅惑に憑りつかれて、はい、おしまい。あなたは、きっと、女を何人もダメにしてきた。そうでしょ? いいのよ、隠さなくても、わたしにだけはね。
ねえ、さいごに、教えて。
あなたは何を、考えているの?
知らない。知らない。知らない。
怖い。怖い。怖い。
僕は、怖い。彼女がぞっと恐ろしい。僕は別に女を食べている自覚は、ない。女をたぶらかすような企みも、持ち合わせていない。でも、不思議なことに、女はそれでも、酔ってくる。
怖い! 誰か、僕が嫌いな女を、紹介してほしいくらいだ。手を繋いでほしいと言われたから繋いだ。頭を撫でて欲しいと言われたから撫でた。でもそれだけだ。僕は、それだけしかしていない。気遣い? した記憶がない。きっとしたなら、それは身に染みたルーティンのようなものなんだ。ただそうしなきゃ気が進まないだけで、だから、あなたの為にやっているのではなく、これは、自分の為にやっている、自分勝手の産物なのだ。
なのでごめんなさい、あなたは、好きでも何でもないのです。嗚呼、分からない。アイとは、コイとは、なんだい。僕にはさっぱりわかりゃしない。何か包まれたいとは思う。アイを、遠ざけている訳ではない。でも、しかし、アイが分からない。誰かに好きになられたことはたんとあるが、でも、誰かにアイされている感覚は、いちどもない。
こりゃ、贅沢言ってるわけじゃない! これは、きっと、何かの病気だ。アイされたいが、コイは嫌い。コイはアイとは全く違う。ねえ、アイってなんだい。君はアイを知っているかい。僕はからっきし、しらないんだ。
コイは、怖い。何かを求めてくる。ねえ、アイは、そうじゃあないんでしょう。アイってのはきっと、一緒にいるだけでいいような静かなる行為であるはずなんだ。コイが語るアイは、アイではない。僕はきみを、知らない。きみがなにを求めていて、何を考えているのかが分からない。そりゃ、アイじゃあない。アイはたぶん、そういうものじゃないんだ。きみのそれはコイなんだ。一方的な、侘しい行為なんだ。僕は、それが、いちばんきらい。アイが、一番。
ねえ、アイは、なんだいな。アイとは、どこに落ちているんだい。僕は、どこに、アイを落としたんだい。
アイをください。お恵み下さい。
コイはいいの、沢山なの!
「ねえ、愛し合いましょ」
「――――」
僕は、彼女を、振り切れない。
彼女は恍惚と微笑んで、その魅惑的な小さい口からは、本物の幸せの感情をにわかに感じ取った。
僕は、絶句した。そして、名前のない激情が、とたんに身体を劈いて、僕は身をよじって、また彼女を拒絶して、川に飛び込んだ。
泥水に流されて、もうこのまま泥にまみれて醜くなってしまえばいいと切に願った。でも、アイを手にするには、自分を否定しなければならないと思うと、
それをアイとは、思えなくなった。
結局、僕は、マジョリティの産物だったのです。
ああ! もう! イヤになる


