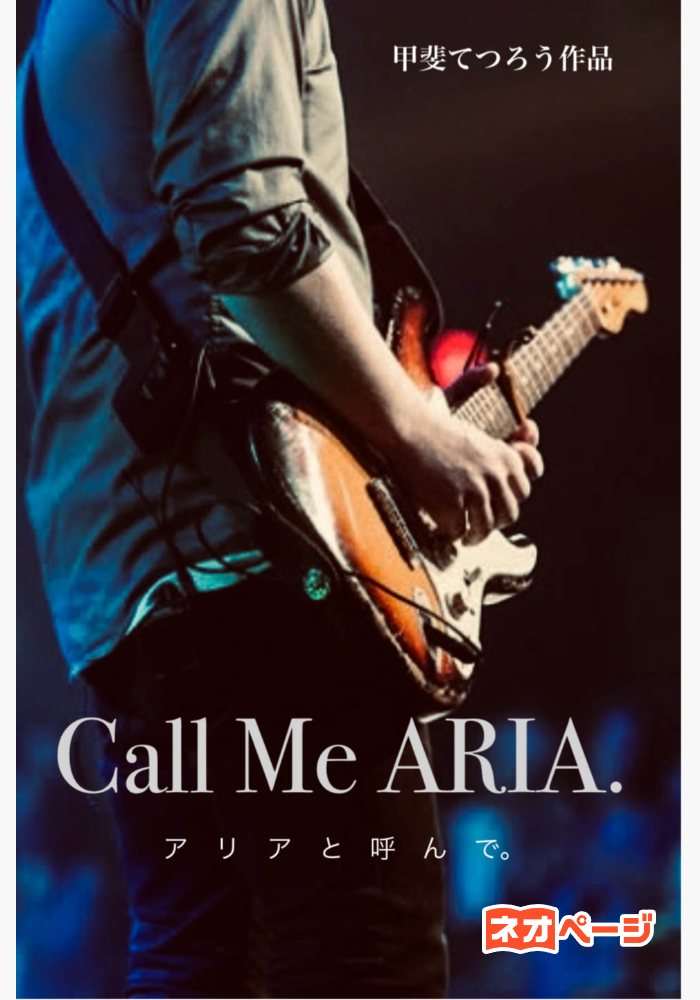
公開日
完結済
組織に管理され怪獣と戦わされる少女、親の言いなりでやりたい音楽が出来ない少年。
2人は出会い意気投合し、自由を求め全てを放棄する。
最も自由を謳うロックを追い求めて。
彼らが旅の果てに導き出す自由の意味とは。
#1
夏が過ぎ人々が残暑を感じている頃、北海道江別市にある大型商業施設の駐車場から入り口に向かうまでの道中に一人の男子高校生がやって来た。
背はそこまで高くなくどちらかと言えば細身で小柄な体型、そして何よりボサボサで毛量の多い頭髪と少しだけ生えた顎髭が特徴だった。
片手に小型のギターアンプを持ち、背中には当然の如くギターケースを背負っている。
そのケースのチャックには"神崎守(かんざきまもる)"と名前の書かれた札が付けてあった。
建物の電気を勝手に使いセッティングを完了させる。
そして軽く深呼吸をした後。
「ふぅ、よし……」
ピックを持った右手を思い切り振り下ろし歪んだエレキギターのサウンドを周囲に轟かせたのだった。
名札にある通り彼、神崎守は商業施設の入り口前で路上ライブという名目で演奏をしながら自身の宣伝をしている。
「今度学祭でライブやりますっ、興味持ってくれた方は是非来てください!」
そんな風に演奏をし、前方に置いたギターケースには投げ銭を出来るようにしているが誰も立ち止まらずお金も入れてくれない。
すると音を聞きつけたのか警備員がやって来た。
「ちょっと君、ここは路上演奏禁止だよっ!」
迫る警備員の影を見て焦った守は最後にもう一度宣伝だけしようと試みた。
「やべっ……では! どうか江別聖華高校の学祭来てくださいっ!」
警備員に止められながらも最後まで言い切った。
丁度そのタイミングだった。
「っ……⁈」
突如として街中に設置されたサイレンが大きな音で鳴り響き始めたのだ。
オマケに遠くの方から黒い煙が立ち上るのが見える。
「まさか怪獣……⁈ ここに出たのかっ⁈」
守とやり取りをしていた警備員が明らかな動揺を見せている、そしてそれは守も同様だった。
「急いでみんな逃げて下さいっ! ほら君も機材は置いて早く逃げなさいっ!」
守にそうとだけ告げ商業施設の中へ入って行く警備員。
逃げ遅れた者に避難誘導しに行ったのだろう。
そんな中で守は警備員の言う事は聞かずにせっせと機材を片付けていた。
「少ない小遣い貯めて買ったんだ、置いてけねぇって」
そんな事を呟きながら機材を片付け終わりその場を離れようと歩き出した。
するとそのタイミングで背後から凄まじい轟音が。
「〜〜っ⁈」
土煙が舞う中、恐る恐る振り返るとそこにあったものは。
「グゥルルルオォォ……」
大型商業施設のあった場所にはその代わりに20mほどの巨大怪獣の姿が。
よく見ると怪獣の下にはバラバラの瓦礫が確認できる。
「っ……」
予想以上の惨状に守は絶句してしまう、もし片付けるのにもう少し時間が掛かっていたらと考えると恐ろしい。
しかし怪獣は何故か倒れている、一体何があったと言うのだろうか。
「あっ、あれは……!」
視線を怪獣が現れたであろう方向に向ける。
するとそこには怪獣と同じほどの体躯をした影が聳え立っていた。
『オォォォ……』
15mほどで人型の宇宙人のような存在が立っている。
ソレが怪獣を突き飛ばしたのだろうか。
しかし守は、この世界の住民は皆ソレの存在を知っている、正体までは知らないが怪獣と同時期に突然現れては怪獣を倒してくれるのだ。
「すげぇ、本物だ……」
その場に立ち尽くしてしまった守はしばらく怪獣と宇宙人らしきソレの戦いを見続けてしまった。
☆
Call Me ARIA. episode1
☆
翌日、宣伝でも言っていた江別聖華高校にギターを担いで登校して来た守は自分のクラスである1-Bで机に座るとスマホを開き昨日の怪獣騒ぎのニュースを見ていた。
タイムリーな話題なので教室内でも同じ話をしている者が沢山いた。
「昨日やばくなかった? 遂にこの近くに出たよ、"3体目"……!」
「"北海道にしか"出ないと言ったってここに来るなんて……!」
この生徒たちが話すように何故か怪獣は北海道にしか出現しない。
それが何故なのかは分からない、更に何故怪獣が出るのに人々は北海道から出ないのかまだまだ子供の彼らには理解できなかった。
「でもまたあの宇宙人が倒してくれたんでしょ? アレは結局なんなの?」
「さぁ? でも敵じゃないっぽいし政府の秘密兵器とか?」
「でも街壊してるじゃん! 本当に敵じゃないのかな?」
「自衛隊も口ばっかでマトモな対処してるの見た事ないし、極秘の何かなのかね」
そんな事をクラスメイトたちが話しているとある人物たちが教室にやって来る。
それは同級生で少しチャラめのいわゆる陽キャというような"スグル"だった。
「みんな聞いてくれよぉー! 昨日の怪獣スマホで撮ってSNSに上げたらバズっちまって! バンドの宣伝に持ってこいだぜ!」
スグルのSNSアカウントにて投稿された映像は十万以上拡散され引用で宣伝された彼のバンド映像もそれなりに拡散されている。
「今度の学祭、めっちゃ人来たりしてな!」
そう言うスグルだがクラスメイト達の空気は重かった。
「学祭ね、近くに怪獣が出たのに出来るのかな?」
そのような不安があるらしい。
しかしスグルは元気に答える。
「そんな被害もデカくなかったしもう倒されたし、いつも次まで結構スパン開くだろ? 現に今も学校やってるから大丈夫だって!」
楽観的な意見を述べるがクラスメイト達も学祭は楽しみにしているためスグルの言葉を信じるしかなかった。
そんな会話を聞いていた守は少し羨ましそうにしながら彼らのバンドのSNSアカウントを見ていたのだ。
☆
休み時間になり守はクラスメイトであり学祭のためのバンドメンバーである陰キャ仲間を三人集めた。
今後の会議というような名目だ。
「お前らどうする? スグルのバンドがバズって完全に注目持ってかれちまう、やっぱクオリティ上げるしかないと思うんだよな」
その他のメンバー三人は少し俯きながら守の話を聞いている。
しかし当の守は三人の様子には気付かない。
「新曲は出来てる、だからこれまで以上に練習を増やして……ってどうした?」
ここでやっと三人の様子が浮かない事に気付いた守はその詳細を問う。
すると予想外の返事が来た。
「言いづらいんだけどさ、俺たちバンド辞めるよ……」
「……え?」
思わず守も聞き返してしまう。
まさか彼らは辞めると言ったのか。
「成績も一学期より落ちて来たし練習してても上手くなる気がしなくて……」
「俺も母さんに勉強の方もっと集中しろって言われた……」
少し理由としては弱い気がしてしまった。
そのため守は何とか引き止めようとする。
「何言ってんだよ、学祭は迫ってんだぞ? 勉強とも両立させれば良いし練習だってもっとやれば上手く……」
そこまで言ったところで遮るように否定されてしまう。
「無理だよ、神崎は両立させられてるの? "また成績下がって怒られた"ってこの間も言ってたじゃん……」
「それはっ、でもお前ら良いのかよ親の言いなりで? 俺たちは親の道具じゃねぇって勢いでロックやるってコンセプトだったじゃんか!」
守は反抗心を持って自由なロックを志していた、だからこそ彼らの不自由な選択に苛立ってしまったのだ。
「それだよ。やっぱ温度差があるよ、ごめんだけど正直神崎の独りよがりな熱意に着いていけない……」
「やっぱり学生のうちは親の言うこと聞いといた方が良いよ」
少し恐れるように震えながら言っていた。
そんな事を言われてしまっては守も気力が失せてしまう。
「……そうかよ、分かった」
思わず項垂れてしまう守。
学祭でのライブは楽しみにしていたためショックだ。
「それじゃ……」
そのまま各々のクラスに戻って行く元メンバーたち。
孤独になってしまった。
あまりの悔しさに自らの机を蹴飛ばしてしまう。
「クソッ……」
思った以上に力が籠ってしまい大きな音を立ててしまった、クラスの注目が一瞬だけ集まる。
「ふわぁ……」
誤魔化すように肘をついてあくびをしてみるがクラスメイト達からは怖がられてしまった。
「(アイツらも結局この世界の不自由さに負けてたんだ……!)」
必死に自分にそう言い聞かせる事でこの感情を誤魔化していた。
☆
放課後、いつもならバンド練習のために集まっている空き教室に一人でやって来る。
別の階からスグルのバンドが練習している音が聞こえて来た。
「何でこんな音楽が人気出るのかね〜」
独り言のように文句を呟きながらセッティングをしチューニングも済ます。
そして深呼吸をしてから思い切りギターをかき鳴らした。
「イェェェ〜〜〜アッ!」
周囲の音を掻き消すため、まるで現実逃避をしているかの如く激しいロックを奏で始める。
曲ではない、勢いのままアドリブで演奏しているのだ。
そのアドリブには学祭で演奏できない悔しさ、そしていつも人気なのにバンドとしても自分を差し置いて人気で在ろうとするスグルたちへの悔しさ、とにかく悔しさが込められていた。
「おらぁぁぁっ!」
どんどんボルテージは上がって行き椅子に足を乗せて凄まじいギターソロを奏でる。
まだ荒削りではあったが魂のこもったロックンロールであった。
そこで扉がガラッと開く。
「あっ……!」
ボリュームの問題で先生が怒りに来たのかと思った。
しかしそこにいたのは会った事のない、綺麗な顔立ちで黒髪ロングの美少女が立っていたのだ。
制服のネクタイの色から察するに3年生、上級生であろう。
「えっと、何でしょう……?」
1年生である守は少し恐縮してしまう。
もしや受験勉強の邪魔だと言いに来たのだろうか。
ズカズカと中まで入って来る彼女の表情は見れなかった、そして目の前に立たれて彼女の身長が自分より少し大きい事に気付く。
「ねぇ君、一人でやってるの……?」
「はい、そうですけど……っ」
その長身に合ったクールな声で尋ねて来る意図が読めずに守は声が裏返ってしまう。
すると彼女は少しだけ笑顔を見せ質問をぶつけて来た。
「もしかして学祭に出るの?」
「え……あ、えぇそうですね」
本当はメンバーに断られてしまった、当てなんかない。
それでもこのような綺麗な先輩が期待を寄せるような表情で問うのだからそれを裏切りたくなかったのだ。
「へぇ〜こういうのも出るんだウチの学祭」
そう言いながら先程まで守が足を乗せていた椅子に腰掛ける彼女。
「3年生ですよね……? 今まではこういうバンド居なかったんですか?」
「今年から転入したから知らない、でも練習聞いてる感じみんな軽い音ばっかで何かこう心にズシッと来るようなサウンドが無くてね」
恐らく彼女は守と同じようなロックが好きなのだろう、だからこそ同じ窮屈さを味わっている。
「その点君のサウンドは良いよ、今を生きてる感じがしたから思わず教室入っちゃった。練習の邪魔になってたらごめんね」
守は自分の音楽を褒めてもらうのが初めてだった、更に"今を生きてる感じ"だなんて。
初めて感じる幸福感に一気に彼女の虜になってしまう。
「マ、マジっすか! 俺そんな風に褒めてもらったの初めてで……っ」
顔を赤くしながら照れていると彼女は突然立ち上がり守の背中をバシバシと叩いた。
「ロックは良いよね、自由で! ちゃんと生きてる感じがする!」
そしてそのまま駆け足で教室を出て行く。
最後に振り返り守に軽く挨拶をした。
「忘れてた、私3-Aの"阿部マリア"!よろしくね神崎クン!」
名前を呼んでくれた事に驚くも口角が緩んでしまう。
彼女は制服の胸についた名札を見ていたため名前を知ってくれたのだと理解する。
そして彼女の名前も知る事が出来た守は感じた事のない充実感を味わっているのだった。
「…………」
しかし教室を出た瞬間のマリア。
彼女の表情は一変して暗いものとなってしまった。
先程の守とのやり取りが嘘であるかのようにそれからの彼女の表情からは心が失われていた。
つづく


