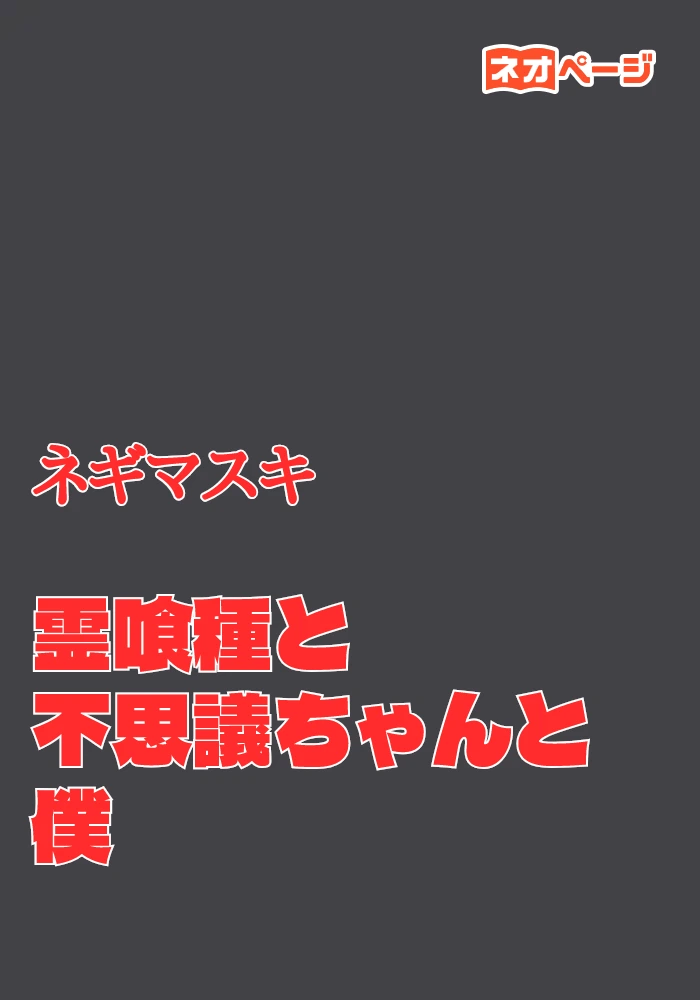
公開日
完結済
霊を引き付けやすい体質の少年は、霊を食べる霊、タベオに取りつかれていた。タベオは日々、少年に襲いかかる霊を食べていたが、あるときそのことに気づいた除霊師の少女がやってくる。
「おっ、メシだメシ。いっただっきまーす」
朝、中学校へ向かう途中。タベオは大口を開けて、僕に向かってきた霊を飲み込んだ。
タベオは僕に取りついている霊だ。霊というと普通、人間の生気を吸ったりするものだが、タベオは霊を食べる。キツネのような顔に、長いふさふさのしっぽが直接くっついたような体をして、ふわふわと浮いている。もともと名前はなかったのだが、霊を食べるからタベオだと、僕はそう呼ぶことにしていた。
「ふう、うまかった。久々の食事だからな。三日ぶりくらいか?」
三日で久々というのだから、普段はそれ以上に霊を食べているということだ。つまり、僕はそのくらい高い頻度で霊と遭遇している。
原因は僕のやっかいな体質だった。自分の意志とは関係なく霊を引き寄せてしまい、さらにそれらの霊は、僕の生気をいただこうと襲いかかってくる。おかげでタベオは、労せずして食事にありつけているというわけだ。
「霊を引き寄せやすい体質ってどういうことなんだろう?」
以前、そうタベオに訊いたことがある。
「うまそうな匂いでもするんだろ」
「匂い?」
「俺にとっちゃ、人間なんかどれもマズそうだけどな。だが、食欲をかき立てる匂いのする霊ってのはいるんだ。同じ
タベオはつまらなそうに答えたが、それは納得できるものだった。僕たち人間だって、おいしそうかまずそうかは、見た目や匂いで判断する。見た目が似たような存在ばかりであれば、いい匂いに惹かれるのは当然だろう。もっとも、自分が霊にとっておいしそうな匂いを発していると言われたところで、迷惑でしかないわけだが。
この日の午前中は平穏だった。授業中に霊がやってくることもなく、勉強の邪魔をされることはなかった。仮に霊が来たところでタベオが食べてくれるのだが、それでもGを見かけたような緊張が走り落ち着かなくなる。まれにすばしっこい霊だと、壁や天井をすり抜けつつ追いかけっこが始まるので、そうなるともう先生の話を聞くどころではなくなってしまう。
嵐が訪れたのは昼休みのことだった。嵐の前の静けさとはよく言ったものだが、穏やかすぎるときほど、不意打ちのようにやってくるものだ。
「あ、あそこ。あそこを今、霊が飛んでる!」
そう叫んだのは、クラスにひとりはいる、ザ・不思議ちゃん。いつも元気に、霊が見えるとのたまっている。今日は先生の机の上あたりを指差していたが、もちろんそんなところに霊はいない。いたとしてもタベオがすぐに飛びかかって、腹の中に収めているだろう。しかし、不思議ちゃんの友達なのか冷やかしなのか知らないが、いつも一緒にいる女子生徒たちが、小さな悲鳴や笑い声を上げながら、どんな霊なのかと聞いている。少し離れたところでは、別の数人のグループが楽しそうに話しながらも、苛立たしげにちらちらとそちらへ目を向ける。僕は外の校庭で遊ぶ生徒たちを見やりながら、不思議ちゃんたちの騒ぐ声が耳に入るにまかせていた。
「キツネよ、キツネの霊。今こっち見た!目を合わせたら危険よ」
よく思いつくものだ。それとも僕には視認できない何かを、彼女は本当に見ているのだろうか。
「キツネの霊ならここにいるのにね」
「!?」
突然、耳元でささやかれ、僕は思わず声と反対側に身を引いた。その拍子に、机の脚にももをぶつけたせいで、机が動いてギイと大きな音を立てる。キャッキャ言っていた不思議ちゃん御一行や、別のところで話していたグループがそろってこちらを見る。いくつもの視線に刺され息が止まったが、幸い彼女らはすぐにまた自分たちの世界へ戻っていった。
僕を脅かしたのは女の子だ。制服は着ていたが、見たことのない生徒。いや、中学生というよりは、もっと年上のように思える。クラスメイト達がこちらへの注目をやめたのは、僕の影の薄さによるものではなく、教室において異物感あふれるこの女の子から目を逸らしたかったからかもしれない。
そんなことを考え怪訝な表情をしていると、笑みを浮かべていた彼女は、制服のブレザーの内ポケットから手紙のようなものを取り出した。そして「読んでね」と僕の机の引き出しに入れ、颯爽と教室を出て行った。
「なんなんだ、ありゃ?」
「さぁ……」
普段、教室ではタベオと会話したりしないのだが、このときばかりは思わず反応してしまった。
『午後五時、鉄道橋の下にて待つ』
真っ白な洋封筒の中には、そうとだけ書かれた、厚手の紙のカードが入っていた。
「おい、行くのか?なんか怪しいぜ」
「仕方ないよ。あの子、君のことが見えてたんだ。無視する方が危険かもしれない」
「それもそうだが、時間がな」
「そうだね。起きたら、何があったか話すよ」
放課後、学校の図書室へ向かいながら、僕はタベオとそんな話をした。タベオは毎日、午後五時頃から一時間ほど、姿を消して睡眠をとる。理由を尋ねると、「食べた霊を消化するためじゃないか?」と本人は言っていたが、霊を食べても食べなくても寝ているので、本当のところはよく分からない。
図書室へ来たのは、時間を潰すためだ。中へ入ると、ちょうど不思議ちゃんたちがカウンターで本を借りていた。図書委員に貸し出し処理されていく本にちらりと目をやると、一目で霊関係のものだと分かるタイトルばかりが並んでいる。勉強熱心なことでと心の中で苦笑しながら、僕は奥のテーブル席へ向かった。
特にやることもないので、ひとまず宿題をして時間をつぶした。それが終わると、何か面白い本でもないかと棚を物色しに立った。『暇のつぶし方辞典』というタイトルが目に留まり、その本を取って、もといた席へ戻る。パラパラとページをめくってみたが、しかし今この図書室でできそうなことは書かれていなかった。
四時半を過ぎたころには、まだ少し早いけどと思いながら、本を返却台に置いて図書室を出て、鉄道橋へ向かうことにした。学校からは十分ほどの距離だ。
「他に誰もいないといいけどね」
「あの女がいるのが、一番の問題だろ」
「それはそうなんだけど」
鉄道橋の下は、ガラの悪い生徒が同級生を殴ったり、不良が子猫に餌をやるようなことはないのだが、それでも誰かしらいることは考えられる。少し前までは、家のない中年ひげもじゃの男が住んでおり、近づかないようにと言われていた。
昼休みのあの子の感じだと、誰かがいても、そのまま霊の話をし始めかねない。そんな心配をしながら堤防を歩いていると、僕と同じ中学の制服を着た男女が、河原を走ってくるのが見えた。カップルだろうかと目で追っていると、階段で堤防まで上がってきて、必死の形相で僕の横をすり抜けていく。鉄道橋の下に目を移すと、昼休みに僕をおどかした女の子が、腕組み仁王立ちでこちらを睨んでいた。制服は着ておらず距離もあるので、本当にその子かは分からないが、発している雰囲気がそうだと伝えていた。
「おい、なんかヤバくないか?無視して行こうぜ」
今まで幾多の恐ろしげな霊を食べまくってきたタベオが引いているのは少し面白い。
「大丈夫だよ。いきなり取って喰われたりしないって」
僕はそう返すと、さっき走っていった男女が使った階段を下りて河原を歩き、女の子のもとへ歩いた。近づいて見ると、やはりというか、女の子というより女の人、だった。
「よく来たわね。逃げ出すんじゃないかと心配したわ」
その人は、腕組み仁王立ちの姿勢を崩さなかった。
「何の用でしょう?」
僕は率直に訊いた。
「私は葛城アケミ。とある組織で除霊師をしているわ。今日は驚いたでしょう?私、二十歳なんだけど、すっかり中学生として溶け込んでて。でも可憐すぎて、みんなの視線を集めちゃってたから、それは失敗だったかもしれないけれど」
「……」
校内に不審なコスプレ女がいる、という注目のされ方だったのでは?そう思ったが、黙っていることにした。
この人も不思議ちゃんのようだ。僕はそう理解した。そして、不思議ちゃんに対しては、口ごたえしないに限る。僕は、クラスメイトの不思議ちゃんに霊がついていると言われた男子生徒が何か冷やかすようなことを言い、支離滅裂なののしりを受けたことを思い出していた。
「最近、この街にやたらと霊が集まってるでしょ。組織の人にその話をしたんだけど、なんの被害も出てないからって、誰も動こうとしなくて。それで私が、被害が出てからじゃ遅いからってひとりで調査してたら、あなたに行き着いたってわけ」
「はあ。ずっと前からそうですけど」
自分に対して霊がわらわら集まってくるのなんて、もちろん今に始まったことではない。いまさらの感があったので訂正したまでだが、葛城さんはさっきまでとは違い、ひどい剣幕でまくしたてだした。
「うるさいわね!私は短大出て組織に就職して、やっと最近、あなたはもう好きにしなさいって言われて、ひとりで動けるようになったの!他の子たちはすぐに研修が終わったのに、私だけヤな教官がついてグヂグヂグヂグヂ言われて!だから、これからはバンバン結果を出して、すぐに売れっ子アイドル除霊師になるんだから!あんたはその最初の踏み台になるんだから、感謝しなさいよ!」
やっぱり不思議ちゃんに口ごたえしない方がいいようだ。突っ込みどころが多すぎて閉口してしまう。
「ああ、すまん。そろそろだ」
「そうだね。寝ていいよ」
余計な話をしているあいだに、タベオの寝る時間が来たようだ。タベオは僕に体を巻き付け、肩にあごを置くような姿勢を取ると、すっと姿を消した。
「へぇ、
葛城さんは、急に小さなノートを出してメモをし始める。その様子に、今度は図書室で見かけた不思議ちゃんのことを思い出した。妙に勉強熱心なところも、不思議ちゃんの特徴なのだろうか。
「それでだけど。あなたがこの街に霊を呼び寄せてるの?」
やっと、そして唐突に本題だ。
「好きでそうしてるわけじゃないんです。僕は霊を引き寄せやすい体質で、勝手に霊が近づいてくるんですよ。それが都合がいいから、タベオは僕に取りついて、やってきた霊を食べてるんです」
僕の説明を聞くと、葛城さんは眉間にシワを寄せた。
「タベオ?それ、ひょっとして、あんたについてる霊の名前?ダサすぎて引くんだけど。一周回ったとしてもダサイわよ」
そう言い放つと、またノートにペンを走らせる。名前なんて、一周回ってようが回ってなかろうが、分かりやすいのが一番だ。それに今回はたまたま教えることになったが、タベオのことを人に話す機会なんてまずないのだし。
「でも、状況は分かったわ。あんたのその体質が治ればいいわけね」
「え?まあ、そうだけど……」
名前のダサさについてムっとしながら考えていたので、急に問いかけられて間の抜けた答えをしてしまった。葛城さんはそんな僕のことなど気にも留めず、「明日、同じ時間に高平神社に来なさい。分かったわね?はい、解散」と勝手に話を打ち切ると、こちらに背を向けて帰っていった。取り残された僕は、どうしていいか分からないまま、しばらくその背中を見続けていた。


