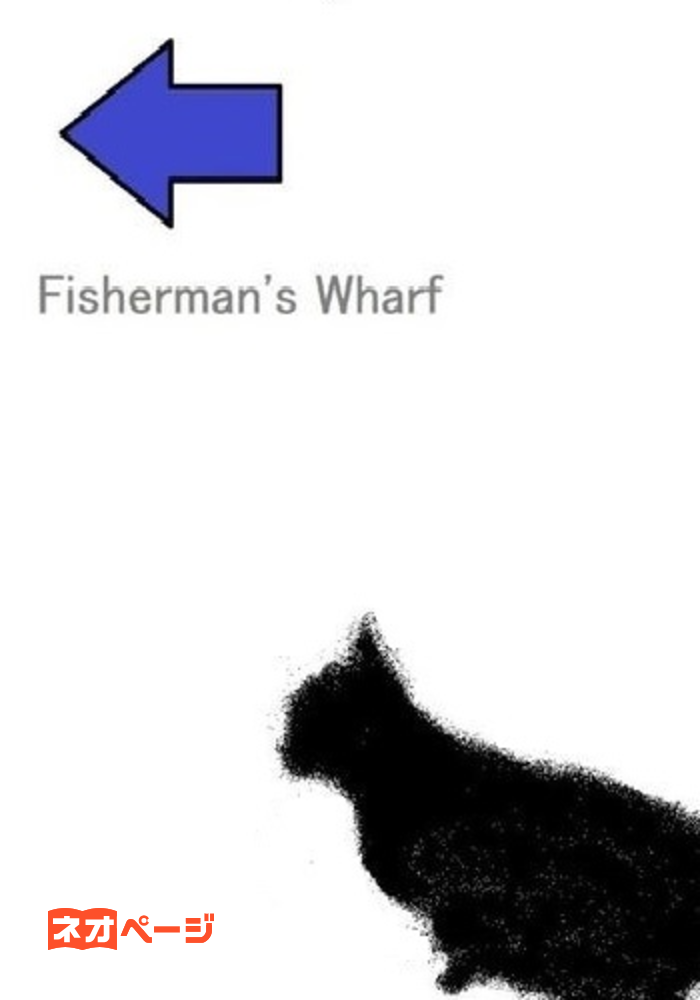
公開日
連載中
雪深い山奥の村に春が訪れた。
一人の青年が少年時代に体験した出来事を話し始める。彼は幼少の頃に聞いた祖父の口癖「森の向こうには湖がある!」を覚えていた。
10才の頃、幼馴染のジローと共にその森へ侵入、巨大なクモに化けた女を目撃した。女は森に巣食う鬼たちを次々と退治する。
そのおぞましい光景を忘れられないと語る青年。ある日、再会したジローから手紙を受け取る。それは施設にいるジローの弟、忠が書いたものだった。
施設を訪ねた旅人と話す忠。義父が母親を殴り殺したのだという。
一方、村の女子中学生、カナは山奥にそびえる塔を眺める。生まれる遥か前に建てたこと以外、何も知らないままだった。学校では美術部の友達、麟からレコードを借りている。麟は姉へのコンプレックスを抱え、森の中へ消えていった。
「森には湖がある!」
それが爺さんの口癖。最初に聞いたのは九歳、まだ小さな手のひらに鉛筆を閉じ込めて、ノートにたくさんの絵を描いた頃。周りの友人たちも、窓色が曇ることすら気付いていない。つまり子供だったわけだ。
遠くから眺めても広いとわかるし、一度迷い込んだら最後、骨になるまで見つかりっこない。きっと梟か、狼だけが知っている。村の大人が言ったけど、「夕暮れには近づくな」って禁止事項、果たして俺たちが守るわけがなかった。湖を探す。そうすれば世界中で自慢できると信じていた。
ちっぽけでしかない行動だったと思う。森の手前、そこに二人の女神様がそびえているんだよ。日々、眼下の少年に軽蔑の眼差しを注いでいる。あっちへ行け、ということらしい。わかっていたんだ。
でも勇気をもって足を踏み入れてみる。学校が終わってから、今日こそ森に行こうと決めたんだ。背の高い女の人が二人、確かに腕を挙げている。アーチを作って迎えている。裸だ。見上げると乳房が四つも見えた。全部、誰かが掘った大理石だったけど。裸の女性を潜らなきゃ、先に行けない。そばにいたジローが照れ笑いを浮かべて、「女神さま、ごめんなさい」と吐露したんだ。
村を覆ったあの雪が跡形もなく去っていた。三月のある日の午後。それは俺たちの、最初の冒険でもあった。どこかにいる彫刻家に聞きたかった。ふざけるなと。もし酸性雨が降り注いだら、おっぱいも溶けるに決まってる。石がどれくらい頑丈かは知らない。今より小さくなって、やせぎすの女になると思うと、晴れた日に潜り抜けてよかったと思う。春休みを引き延ばす権利なんかないけど、一度宿題から逃げ出すくらいは許せるはずだ。あとで無知やうぬぼれを後悔する。それでいい。
見上げた樹の葉から光が射す。なんだか笑いたくなった。ぬかるみに足をなくしても、天からの豪雨に足を止めても、別に心配はなかった。森に行く。それだけを胸に、放課後も遠くの丘を眺めて過ごしたのだから。
振り返ることはしなかった。夕ご飯までたっぷり時間があるし、何より潜り抜けたことが楽しかった。ガキ二人消えたところで、驚きはしない。あれだけ学校でも近づくなと聞いていたから、まさか俺たちが本当に入るなんて誰も思っていない。
恐怖と感じたなら、さっさと女神様の元へ引き返していた。どうせ何もないに決まっている。枯葉の道を駆けた。穏やかな風だった。あいつが早く走るもんだから、追い越せとばかり腕を振った。通り過ぎる樹々と、踏みつける葉っぱの音。もう学校に戻れやしないと思ったんだ。
同じスニーカーなのに、俺より先に行かないと気が済まない。同じ背なのに、俺より向こうへ行かないと気が済まない。ジローはいつもそんな性格だった。
そういやステンドグラスを作る宿題があった。ジローは俺の絵を見て何も言わなかった。あいつはふてくされて、自分の拙い電車を隠そうとした。
下手なんだよ、本当に。言わなきゃ電車だとわからないくらい。俺が描いた熱気球と大違いの代物だった。
図工の時間は終わってんだよ、と俺が言う。ジローは「知ってる」とだけ答えた。
それが十歳だったなんて、絶対信じない。
決して息切れなんかじゃなかった。
あいつ、明らかに戸惑っていたから。
砂浜に大きなクジラがいたら、同じように立ち止まる。あそこは海じゃなくて、獣が啼く場所だったみたいだ。
目の前に裸の女性がいるなんて誰が思う? 鬱蒼とした世界の真ん中で、確かにその女性は地面に横たわっていたんだ。二人とも言葉に詰まった。ジローが何かつぶやこうとしていたのはわかった。だけど裸の女性を見て、俺たちがその場を去るなんてことはできなかった。目を閉じている。金色の髪が長くて、腰辺りにまで伸びていた。体は真っ白だった。陽が射していたせいだ。おまけに唇はぼってり、ジローのつぶやきに何か反応している。


