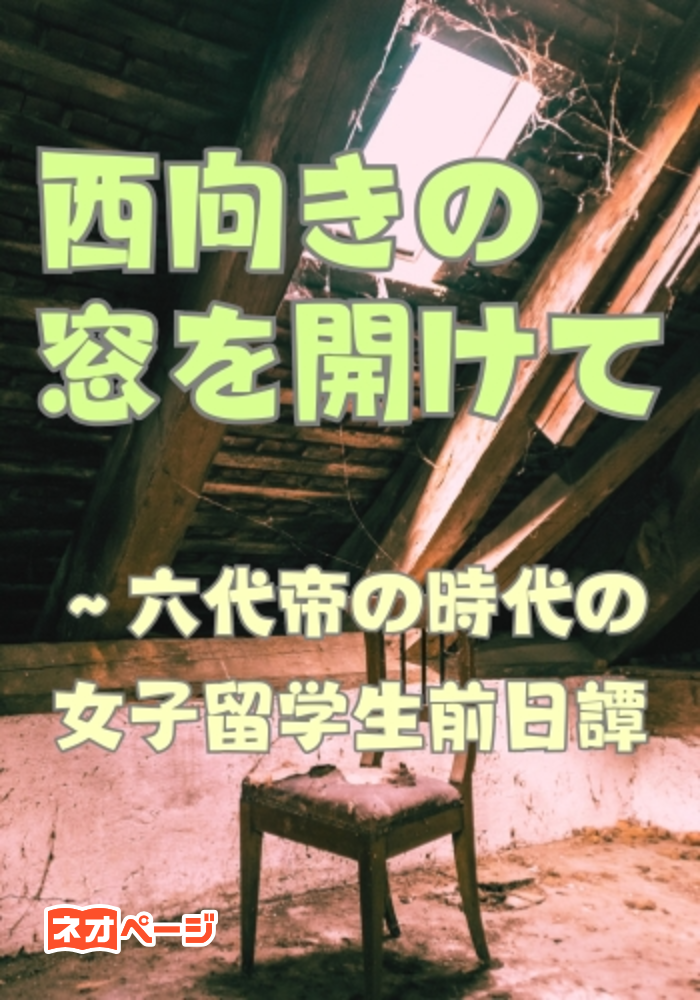
公開日
完結済
「帝国」六代皇帝の時代、はじめて女子の留学生が「連合」へ行くことになる。
境遇の違う三人の少女は直前の研修のために同居することとなるが、そこで事件は起こる。
少女達は全員無事「連合」へ行くことができるのか。
前日譚。
「ああもう寝付いてしまったわ」
毛足の長い絨毯は大きな犬みたいだ。そう言ってころころと転がり回っていた少年もおねむの時間だった。「犬の毛」にくるまっていつの間にか母親のそばで静かな寝息を立てている。
彼女は側に控えていた女官長に合図をする。下がる。
少しすればこの館つきの侍従がやってくるはずだ。さすがに九つにもなった少年を抱えて部屋に連れて行くのは、女官長にはもうしんどいことだろう。
その様子を見ながら彼女の夫は低く、ややけだるげな声をかけながら床に座り込む。
「昼間元気な奴は夜よく眠るな。健康でよろしい」
「あなたもそうでしたか? 皇帝陛下」
彼女は小首を傾げて、多少の皮肉と多分の愛情を込めて夫を眺める。
結い上げず、簡単に編まれただけの豊かな髪は、肩に掛けていた分が動く拍子にざらりと落ちる。
他愛のないそんな仕草は、彼女が嫁いでからこの十年、変わることがない。その中に込められている思いも。
「いやいや、俺はお前ほどではなかったと思うぞ、皇后どの」
くすくす、と二人は笑う。寝入ってしまった子供を起こさないように、静かに、優しく。
やがて侍従が一礼して入室する。彼は皇太子をそっと抱き上げると、女官長とともに部屋を退出していった。
何処にも夜が来るように、皇宮にも夜が来る。
「帝国」で唯一の地位を持つこの二人が現在居る所は、皇宮の中の後宮と呼ばれる区域の中に建つ一つの館だ。周囲からは「楓館」と呼ばれている。
現在の皇后は皇宮に入った際、まずこの館に住むことを命じられた。
彼女はやがて男子を身ごもり、皇后の位についた。そして現在でも、本宮よりもこの館に居ることが多い。
そしてこの皇后を、端の誰もが羨む程熱愛しているという皇帝もまた、ほとんどこの「楓館」を本宅にしているかのようだった。
尤も、皇帝は一日の殆どを本宮での政務に費やしている訳だから、文句をつけられる程のことはない。朝働きに出て、夜帰ってくる市井の労働者と、そのあたりは変わりがない様だった。
皇太子が存在する今、皇帝が義務のように後宮のあちこちの館へ出向く必要性もない。
一方、皇后は式典や訪問といった「公務」以外に本宮に行くことは滅多に無い。あまり好きではない、と言ったとも伝えられる。
「帝国」には「女性は政務には一切関わらない」という法が存在している。故に下手な動きをせず、館で大人しく暮らしているというらしいというのも、それはそれで周囲の不評を買うものではなかった。
時折彼女を訊ねてやってくる者は居る。皇后には多様な方面の友人が居るのだ。が、特にそれが問題になったこともない。学生上がりの皇后の、文化的なサロンの様なものだと考えられている。
尤もその経歴自体は、過去の代には無かったものである。学生という身分が女子に与えられたのが「帝国」の長い歴史の中ではごく近年のことである。
皇后は学問にも芸術にも多大な関心を示し、彼女の出来る範囲でそれらに才能のある者には支援をしている。
それに文句を付ける者は、表向き居ない。何せ直接に政治に口を出す訳ではないのだ。現在の地位を守ることに東奔西走するような閣僚には彼女の行動は大した問題ではなかった。
その件を除けば、現在の皇后は、それまでにこの後宮に暮らした女性の中では最も問題が無い人物だったのである。
彼女と同じ年頃で争いが起こるような女性も殆ど居ない。過去には後宮内に多数あった館、多数居た妃達も、大半はそれぞれの故郷へ戻って余生を送っている。残る者は彼女を支援している。少なくとも表向き。
それが何故なのか、閣僚の誰も判らない。知っているのは当の女性達本人と、おそらくは皇帝だけだった。
彼女が皇后になって十年、皇宮はそれまでにない程穏やかな日々が続いていた。
息子が侍従と女官長に連れられて行ったのちにも、この二人は床に直に座り込んでいた。豪奢な椅子が無い訳ではない。ただ基本的に二人ともその様な体勢を好むのだ。
式典関係は肩が凝って仕方ないと言う点で似た者夫婦とも言える。類は友を呼んだのかもしれない。
皇帝はワゴンに乗せられていた銀のトレイを手ずから床に置く。ふっと癖のある香りが漂った。皇后は何ですか、と瓶の中身を訊ねる。
「辺境庁長官からだ。華西のイダ・ハンのかなり強い馬乳酒だ。お前も呑むか?」
「そうですね。いただきましょう。今日いらしたのですか?」
「ああ。最近はやっと平穏になってきた、と言っている」
「一時はかなり忙しそうでしたわね」
白い液体が、二つの杯に注がれる。
「あなたは本当に向こうのものがお好きですこと」
「お前も人のことはいえないだろう? 黒茶より乳茶が好きなくせに。おかげで女官長が昔ながらの茶を入れる楽しみが減ってしまった、と嘆いていたぞ」
「あれは私の愛する学都の習慣です。言いましたでしょう? 向こうで昔、流行っていたんです。あなたのはただのご趣味。私のは美しい学生時代の名残りです」
彼女はぬけぬけと言いながらくすくすと笑う。
「ぬかせ」
そう言いながら皇帝は強い酒を一気にあおった。皇后もそれにならう。
強い酒だろうが何だろうがお互いに心配はしない。
何しろ彼らは皇帝と皇后なのだ。そんなものは大したものではない。
「ところで陛下」
「何だ?」
「前に私が申し上げました件、どう思われます?」
「女子留学生の件か」
彼女はうなずく。
「ええ。前々からの。どうやら形になってきました。無論反対する者も多いのでしょうが…… だけどそういう事ができる、ということを示さなくては気付くことすらできませんから」
「まあ、な。送ることには俺は反対はしない」
「陛下」
「……何しろ今のこの国じゃいくら頭が良かろうが意欲があろうが、高度な講義を受けることすらできないからな。だがそんな者一人一人に個人教授していたらたまったものではないし、だいたい受けている側も苦痛だろう」
ええ、と彼女はうなずいた。
同じ学舎で学び、競い合う友人居てこその学生生活だった。それをこの皇后は誰よりもよく知っている。
「それに、何はともあれ、究理学系は『連合』にはかないません。悔しいことですけど」
「悔しい、ね」
皇帝はにやり、と笑う。
「悔しいですわ。ほら、ここは向こうの書物とかかなり早く入ってきますでしょ?」
「文化大臣がぼやいていたぞ。皇后陛下は新しい本をすぐに横から借りていってしまうから皇宮の図書室になかなか新しい本が入らんと」
「横からって言ったって、せいぜい一日か二日ですわ。私読むの早いですもの」
「帝国本紀を読破するのに一ヶ月かかった奴は誰かな」
「誰のせいだと思ってるんですか。とにかく、向こうの本を見ると、ああどうしてこんなに詳しく系統だっているの、って、せき立てられる思いですもの。留学だって、行けるものなら今から私が行きたいくらいですもの」
「おい」
皇帝はやや彼女の方へ身を乗り出す。
「冗談ですわ。今は行きません。あなたとあの子が大切ですもの」
「驚かすな。で、何人程度送るつもりだ?」
皇后はにっこりと笑うと、空になった杯をすっと夫の前に差しだした。
彼は半ばあきれるが、請われるままに馬乳酒を注ぐ。そしてお返し、とばかりに今度は彼女が皇帝のコップに注ぐ。
「二人です」
「ずいぶん少ないな」
「最初から大人数送るのは、反対派の標的をいたずらに大きくするだけでしょう。二人くらいならまだ私の手の者で、目の届きようもあるでしょう」
「ほお」
「ですが、当初は三人です」
「三人?」
皇帝は黒い太めの眉を寄せ、露骨に嫌そうな顔になる。それには全く構わずに皇后は繰り返す。
「そう、三人です」
三人ね、と皇帝は呆れたように繰り返す。そしてやれやれ、とつぶやきながら、眉と同じ色の、やや長めの髪を引っかき回した。


