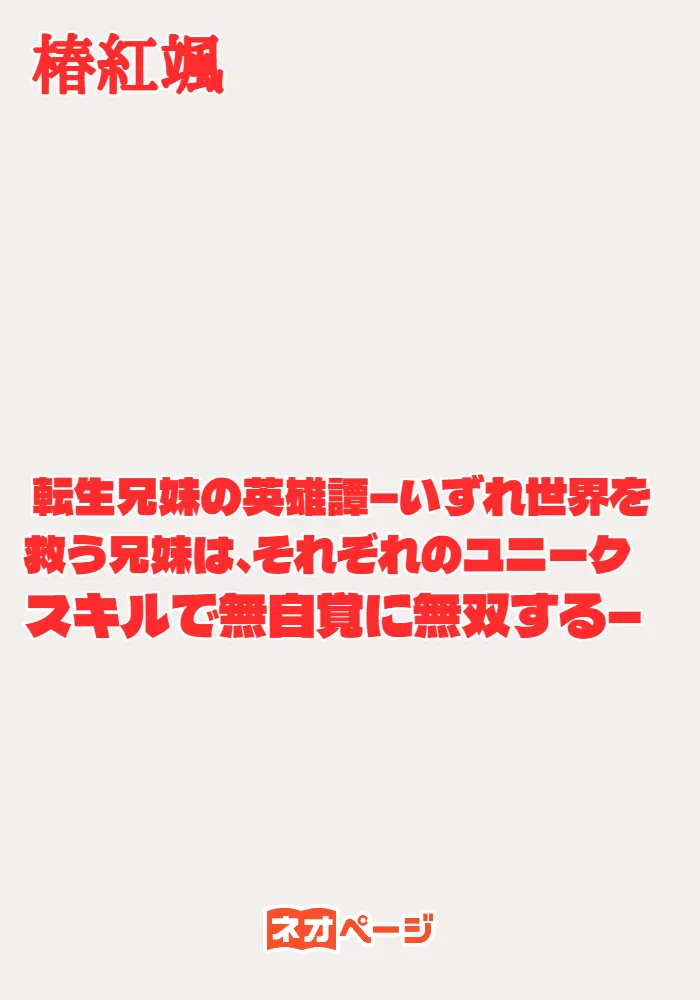
公開日
連載中
彼らは本当に極普通で特技も特にない極普通の青少年少女。
ただ、守は少しだけ人より正義感が強く、恵海は少しだけ人より笑顔が似合うだけ。
そんな佐近兄妹はある日、不慮の事故により命を落としてしまう。
時は過ぎ、それぞれに同じ異世界で再び生を受ける兄妹。
だが、再び兄妹として生まれるほどロマンチックなことは起きず、現実世界と同じ年齢になっても尚巡り合うことすらなかった。
そんなある日、アルクスは一人の少女をパイス村にて助けることに。
生まれ変わっても尚、己の正義感を捨て去ることはできず行動するのだが、それをきっかけに止まっていたかのような時間が動き出す。
再会を果たす兄妹。
それは運命の巡り会わせなのか、それとも偶然なのか。
動き出した小さな歯車は次第に大きくなり、村を、街を、国を、世界をも巻き込んでいく。
五月二十五日。
職員会議により全校生徒は早めの放課後が訪れ、部活動のない自由時間となっていた。
『放課後、せっかく時間が空いたから一緒に帰ろうよ!』
高校生にしては随分と可愛げのある文面であるが、それは連絡だけではない。
タイミングがちょうど良く、その連絡を確認したのが校門だった。
「お兄ちゃーん、お待たせー!」
「大丈夫。僕も今来たところ」
「本当ー? ならよかったっ」
「じゃあ、帰ろうか」
時折こうやって一緒に帰ることはあるが、守も『いつまでもこんな感じで大丈夫なのだろうか』とも思っていた。
いざ歩き出そうとすると、鞄を持たない右手に柔らかいものが触れる。
「右腕もらいー!」
「おいこら、それはさすがに」
「えー? さすがに何? 私は誰かに見られたって何にも問題ないよ?」
守は「え、そういうものなの?」と、内心ツッコミを入れるもこれが初めてではない。
幼稚園の時や小学生の時は、よくこういったやりとりをしていたから慣れていると言えばそうなのだが、でもこの年になっても続けるの? という葛藤が渦巻いている。
つい最近でも二人だけで買い物へ行く時に同じ状況になったし、それ以外の時も同じ流れになった。
だが、こういった大衆の目に触れる状況では久しぶりだったため、守は『血の繋がった兄妹なんだから別に変な事でもない』という思いと『この年になっても兄離れできない妹が心配』という思いがせめぎ合ってしまう。
「それに、私たちが兄妹だってわかる人の方が少ないんだし」
「いや、それの方がまず――」
「え? なにか不都合なことでもあるの? ま・さ・か……お兄ちゃん、彼女ができたとか?」
「そんなわけないだろ」
「だっよね~。お兄ちゃんに彼女なんてできなくたって、私がいるから全然問題なーしっ」
満面も笑みを浮かべる
満足そうに守の右腕に頬ずりをしているが、それはまるで動物がやるマーキングとしか言いようがない。
「まあ、こんな僕でも恵海に変な虫が付かない程度の役割は果たせてるってことか」
「全然ちっがーう! それに、もしもの時はお兄ちゃんが守ってくれる、でしょ?」
「まあな」
「小さい頃から、お兄ちゃんは私のヒーローなんだから。ちゃんと信じてるよ」
――そうだな。恵海は俺が守る。昔も、今も。
まるでカップルのそれと違わない二人がしばらく歩いていると、横断歩道を渡る老婆が視界に入る。
「ごめん、あの人を手伝ってくるから離れてくれるか」
「うん、わかった。荷物は持ってあげるよ」
「ありがとう恵海」
正義感。
現代の社会において、これほど綺麗事なものはあまりない。
偽善者。
いくら正しい行動を起こそうとも、必ず誰かから非難される。
故に、ほとんどの人間は行動を移さない。
その行動が正しいと分かっていても、その発言が誰かを救うと分かっていても。
だが、守はそんな時代でも馬鹿正直に自分が正しいと思うことを貫き通すような男だ。
物語の主人公のように、物語の英雄みたいに。
「すみません。もしよろしければ、お手伝いをさせていただけませんか」
「ありゃあ? ああ、そうかいそうかい。ありがたいねえ、じゃあお願いしちゃってもいいかな」
「はい、もちろんですとも」
買い物袋を両手に受け持ち、歩く速度を合わせて歩道を進み始める。
もちろん、辺りの行き交う人間は手伝おうとするどころか、見て見ぬ振れをして通り過ぎていく。
当然ながら歩く速度は遅い。
だが、もう残り半分が過ぎた。
……が、残酷にも歩行者用の信号機の点滅が始まってしまう。
守の気持ちは少しだけ焦る。と、同時に、車用の信号が変わってしまったとしても、車が止まってくれると信じている。
――歩道までもう少し。後もう少し。
「あれ……もしかして、あのおばあちゃんの落とし物なんじゃ」
恵海は、兄の勇姿を背後から見届けていたが、老婆が手に持っていたハンカチを落としていることに気づいた。
――もしもお兄ちゃんだったら、絶対に見過ごさない。私も、少しはお兄ちゃんみたいに……!
意を決した恵海は、足早に横断歩道に飛び出し、ハンカチを拾い上げた。
「よし、ここまでくれば、車が来ても大丈夫ですね」
「あら、本当ねぇ。本当にありがとう。このお礼は何をしたらよいかしらね?」
「いいえ、気にしないでください」
腰を曲げた老婆は、体は返せなくともしっかりと礼を述べる。
だが、守は聞き滲みのある声が耳に届き、反射的に視線をその方向へと向けた。
「おばーちゃーん! これ、落とし物ですよー!」
「なっ、恵海!? っ!?」
恵海の姿を視界に捉えるも、それと同時に暴走するトラックも視界に入ってしまう。
駆ける恵海は老婆と守に集中していて、トラックが真っ直ぐこちら側へ突っ込んできていることに全く気が付いていない。
守は手に持つ荷物を手放し、恵海の方へ駆け出した。
――間に合わない。クソッ!
「えっ?」
守は、咄嗟に恵海を抱き締めて反転し、自分の体をトラック側に回す。
「俺が守って――」
老婆は物凄い急ブレーキ音と衝撃音に目線を上げて振り向いた。
眼前――そこには、顔面スレスレまで接近し、横転しているトラックが。
だが、そこには先程助けてくれた少年の姿はなかった。


