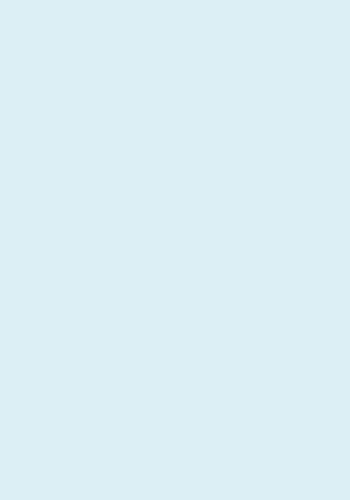
公開日
連載中
塚井との出会いは、高校の入学式だった。
高木と塚井で、並びが前後だったので、おれから塚井に話しかけたのだ。
出身中学を聞くというアイドリングトークを終えると、おれは少し踏み込んだ質問をした。
「塚井は、クラブとかもう決めてるの?」
「クラブには入らない。やることがあるんだ」
塚井は首を振って、きっぱりとした口調で答えた。
「え、もしかして塚井って、勉強に青春をかけるタイプ?」
おれが少しからかうようにいうと、塚井は目を輝かせて、
「おれは、パシリになるんだ」
といった。
「……え?」
おれはたしかめるように聞き返した。
「パシリって、あのパシリか? 使いっパシリのパシリ?」
学校内において、立場が一番下で、いじめのまろやかな言い換えともいえるパシリに、こいつはなろうとしているのか?
だいたい、パシリってめざしてなるものか?
だけど、おれを見つめる塚井の目は、冗談をいってるようには見えなかった。
「ああ。おれは高校の三年間で、立派なパシリストになるつもりだ」
「パシリスト?」
なんか、ピアニストみたいな、ちょっとしたプロフェッショナルみたいな単語が出てきた。
「パシリを極めた人のことを、パシリストっていうんだ」
塚井の言葉に、
「ごめん。全然意味が分からない」
おれは正直にいった。
「そうか」
塚井は悲しそうな顔をした。
「やっぱりまだまだ、パシリストの知名度は低いんだな」
「いや、低いのは知名度じゃなくて、立場だと思うぞ」
つっこみながらも、おれは塚井の語る「パシリへの熱意」に、すっかり興味をひかれていた。
それからの塚井の行動は、まさに有言実行だった。
一週間もしないうちに、すでに何人もの先輩のパシリとして、昼休みになると焼きそばパンを抱えて走っていたのだ。
パシリというのは、使い走り――つまり、おつかいをさせられているだけで、お金を奪われるわけではない。
塚井が提供するのは金銭ではなく、昼休みになった焼きそばパンが届けられるという労力であり、快適さなのだ。
うわさでは、四時間目のチャイムが鳴り終わるころには、すでに売店に到着して、大量の焼きそばパンを買い込んでいるらしい。
またたくまに評判は広まって、五月の連休明けには、昼休みになると数十個の焼きそばパンを、給食の時にパンを運ぶような大きなケースに入れて 廊下を急ぐ塚井の姿がみられるようになった。
パシリとして好スタートを切った塚井だったが、二年生の時に大きなピンチがおとずれた。
新しく入学してきた金井という一年生が、パシリの座に挑戦してきたのだ。
金井は家が金持ちで、先輩に「ぼくがおごります」といって、塚井の顧客を奪っていった。
いつもよりも少ない焼きそばパンを運ぶ塚井に、おれは「お前もちょっとおごるとか、割引するとか、なにか特典をつけた方がいいんじゃないか?」といった。
しかし、塚井は涼しい顔で、
「それはおれの目指すパシリストじゃない」
と首を振った。
いつもは温和で、なにを頼んでもやってくれる塚井だが、パシリに関してはだけは、絶対に自分の考えを譲らない。
結局、一時は何人かの先輩が金井についたものの、半月も経たないうちに、全員塚井のもとに戻ってきた。
塚井にいわせると、パシリが金を出してしまうと、それはカツアゲになってしまうのだそうだ。
そんな塚井の二年生の時の卒業式は圧巻だった。
式が終わって、体育館裏に呼び出された塚井に、心配になってついていくと、卒業生のほとんどが集まっていて、この二年間の塚井のパシリに対して、感謝の気持ちを伝えたのだ。
「それじゃあ、これが最後のパシリだ」
そういって、卒業式で答辞を呼んだ先輩が、塚井に財布を渡した。
「これで、おれたちに焼きそばパンを買ってきてくれ」
その日の帰り道。
夕陽に染まる河原を歩きながら、おれは塚井に、前から気になっていたことを聞いてみた。
「塚井は、どうしてパシリを目指してるんだ?」
いままでにも、何度か聞いたことはあったのだが、「かっこいいから」とか「男のロマン」とか「パ行が好きだから」と、ごまかされたいたのだ。
塚井は足元の小さな石を蹴飛ばすと、
「おれの親父も、パシリストを目指してたんだ」
つぶやくようにいった。
「それで、なれたのか?」
おれの問いに、塚井は無言で首を振った。
「だめだった。いまは、ただの一部上場企業の社長だよ」
「すげえじゃん」
「でも、飲むといつも『おれは負け犬だ。パシリになれなかった、敗残者だ』って泣くんだよ」
パシリの権威って、いったいどうなってるんだ?
おれが首をひねっていると、
「勘違いするなよ」
塚井はおれをにらむように見ながらいった。
「おれは別に、親父の代わりに親父の夢をかなえてやろうとおもってるんじゃないからな」
いや、おれが首をひねったのは、そこじゃないんだけどな、と思ったけど、照れたように顔をそむける塚井に、それ以上は何もいわなかった。
そんな塚井も、高三になると同級生と下級生だけになるので、やっぱりやりずらそうだったのだ。
それだけに、大学に入学した直後は、すごく生き生きしていた。
同じ大学に進学したおれは、学部は違ったけど、評判は聞いていた。
そのころには、おれもパシリストがどれだけ尊いものなのかをわかっていたので、心から喜んだ。
だから、卒業を前にして、とつぜん大学を辞めると言い出したときはおどろいた。
「辞めてどうするんだよ」
キャンパスのベンチでおれが聞くと、
「アメリカにいく」
塚井は決意に満ちた顔でいった。
「アメリカ?」
「ああ。おれはこのままじゃだめだ」
ここ数年で、パシリはAIにはまねできない仕事として、注目されていた。
たとえば、焼きそばパンが売切れていたらどうするのか。
別のパンを買うのか、ほかの店にいくのか、自分で調理してつくるのか――機転や発想力、行動力が必要な、総合芸術として認められていたのだ。
さらに、塚井がプロヂュースした焼きそばパンがバカ売れして、いまでは焼きそばパン専門店をフランチャイズ展開するほどになっていた。
「どうしてアメリカなんだ?」
おれが聞くと、塚井は話し始めた。
「この前、留学生のパシリをしたんだ」
「留学生?」
「ほら、法学部にペガサスっているだろ?」
ペガサスは、塚井にケバブを買ってきてくれといったらしい。
しかし、塚井はケバブがなにか分らずに、ペガサスを失望させてしまった。
「やっぱり、国内だけに目を向けていたらだめなんだ」
おれは思った。
ケバブはトルコだし、ペガサスは漢字で翔馬と書いて、生粋の日本人だ。
だけど、なにかを決めた塚井をとめられるものはいなかった。
「もう決めたんだな」
「ああ」
「じゃあ、アメリカで一番うまいハンバーガー、買ってきてくれよ」
「まかせろ」
おれたちは、拳を握りしめて、グータッチをした。
それからの塚井の活躍は、めざましいものだった。
〈スキヤキ〉や〈オリガミ〉のように〈パシリ〉が英語として認定されたのは、塚井のおかげだし、三年後に正式種目となったオリンピックでは、パシリのスペシャリストとして、フリー、テクニカル、ビッグエアの三種目で金メダルを獲得した。
そんな塚井から、ひさしぶりに電話がかかってきたのは、残業が終わって、駅から家までの道を歩いているときのことだった。
「今度、宇宙に行くんだ」
おれが電話に出るなり、塚井はいった。
「宇宙?」
塚井の話によると、正体不明の宇宙船が地球の上空にあらわれたので、国連からのメッセージを届けにいくらしい。
たしかに、相手の気持ちを読み取ることにかけては、世界中探しても、塚井以上の者はいないだろう。
「大丈夫なのか?」
「ああ。みとけよ。おれは宇宙一のパシリストになってやる」
なにかを決めた塚井をとめられるものはいない。
「そうか。だったら、宇宙で一番うまい……なんだかわからないけど、なにか買ってきてくれよ」
「まかせろ」
おれは拳を握りしめると、夜空に向かってグータッチをした。


