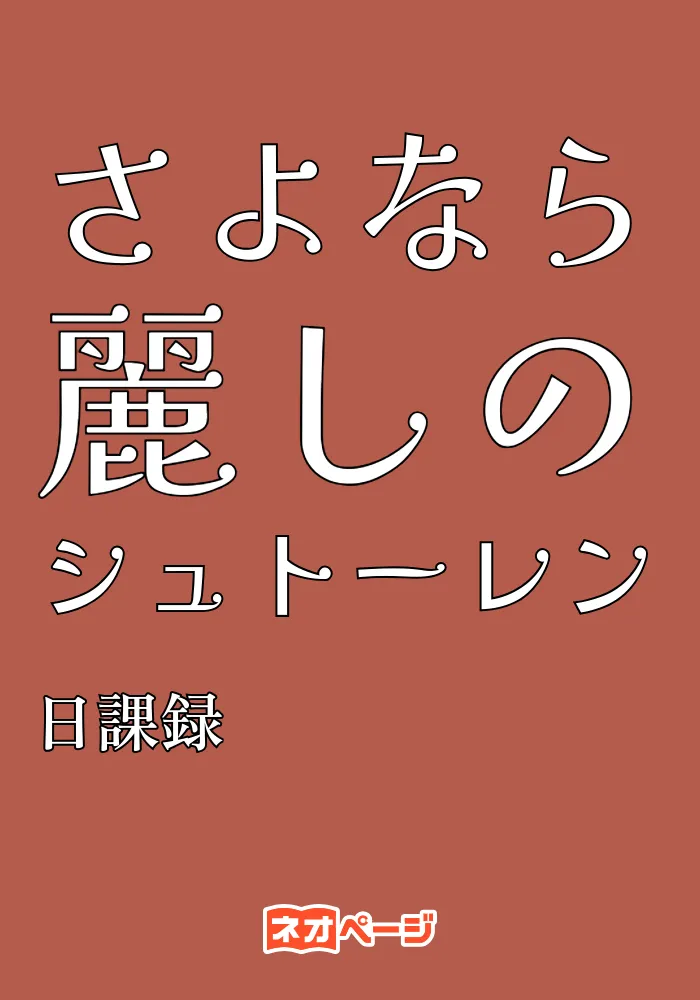
公開日
完結済
砂糖とバターをゾッとするほどブチ込むのさ』
ところで「シュトーレン」と「シュトレン」どっち️️派っすか?
第1話
「シュトーレンのカロリーを知っているか?」
目の前の人物が季節菓子の脱け殻に指を這わせる。その整えられた爪先は裏面の白いラベルの上で止まり、解答たる印字はその下へと秘匿されてしまった。
シュトーレンのカロリーを知っているか。
私は薄々勘づいている。いや、本当は知っている。指摘されずとも、そんなものはとっくに悟っているのだ。
「これは一気に食べるものじゃない」
やめてくれ。そう叫び出したかった。喉の奥に押し込めた反駁は、胸の苦しいところに詰まって私を嘖む。
「真ん中から薄く切って、都度切断面を閉じ合わせる。空気に触れないように」
そうだ。これは本来、そうして熟成させながら楽しむものだ。洋酒の効いたぎっしりのフルーツは、確かにまだ若い味がしていた。控えめに添えられた愛らしいクリスマスカードにもその旨記載されていた。
『ぜひ珈琲や紅茶のお伴に、少しずつ切り分けてお楽しみください』
ああ、不特定多数に向けられた心尽くしの端正さたるや。こうして人はその場限りの恋に落ちてしまうものなのだ。私は名も知らぬその人の親切に報いなければならなかった。
それなのに。
……いや、今更何の取説が必要か。私は密かに拳を固めた。それを叩きつける勇気まではないのだが、自らの精神を鼓舞する為には必要な動作だった。
既に鷹は放たれたのだ! 最早それは細切れになり――――
「今日の日付を言ってみろ」
――――全て私の胃袋に収まっている。
なのに、再び鋭く問い直され、掻き集めたなけなしの闘志は儚くも霧散してしまう。霜月も末だというのに、不快な汗がこめかみを流れていく気がした。
言えないのか、と指先で机を小突く音がやけに響いて耳が痛い。
「いつまでもこんなことを繰り返していたら、」
わかっている。分かっているからその先を言わないで。
「あっという間に――――」
「うるせー!!!! カロリーが怖くてデブ活が出来るか!! 太く短く生きて何が悪いッ!! 好きなもん食わせろッッ!! うわああああ」
ウワーッ!!!!!!
私は机に伏せて泣き崩れた! 叫んだ拍子に馥郁たるスパイスの香りが鼻から抜けた! サイコロ切りにしてヒョイヒョイ食べてたシュトーレンの欠片がちょこっとまだ皿の上に残っていたので泣きながら口に入れた!!
美味しい……美味しかった……もうなくなっちゃった……。いつの間にか涙の意味は変わっていた。
ああ、さよなら麗しのシュトーレン。
さっきから対面で私を詰めていた相手からは、この世の終わりぐらいドン引きされた。


