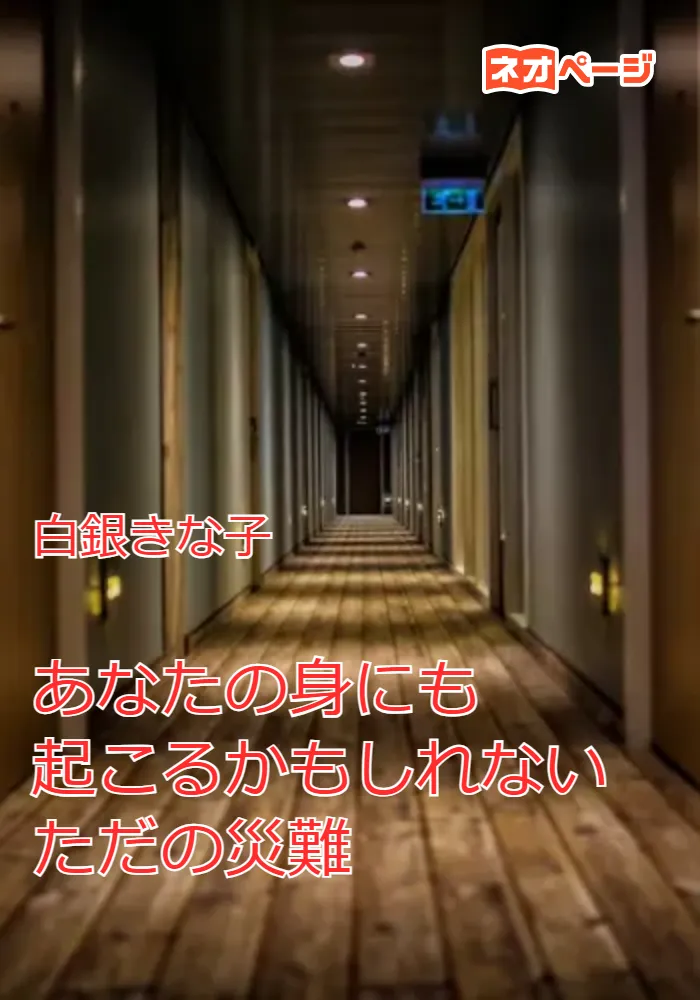
公開日
完結済
誰にでも起こりうる、ただの日常の一幕。
気付いて、気付いた、気付かれた。
冷蔵庫を開き、缶ビールを手に取る。
帰宅後すぐに入浴を済ませて夕食、というルーティンに逆らったのは、あまりの疲労に体がアルコールを求めたせいだ。
空きっ腹のビールは良くないというのは入社してすぐの歓迎会で先輩に教わったこと。冷蔵庫の奥に眠っていたサラミを一口だけ齧り、プルタブに指をかけビールを一気に喉に流し込む。一日中、外を駆け回ってくたくたの体にアルコールが沁み渡る。
──あー、最高。
テレビを点けてみると知らない芸人がネタを披露してダダ滑り、ベテラン芸人のツッコミが冴え渡る。お決まりの偽物の笑い声に、思わずつられてしまった。
……はぁ、つまんね。何か良いこと起きねぇかな。
スマホアプリを立ち上げて、レースゲームにでも興じるとしようか。風呂はその後でもいいか。気ままな一人暮らしは、こういうとき楽だよな。
テレビを消して間もなく、沈黙が訪れる。……かと思えば、そうでもない。
外からかすかに聞こえてきた、野太い叫び声。ベランダの方からだろうか?
引っ越してきて2年目になるこの4階建て賃貸マンションは、荒川の脇に立っている。川を挟んで向かい側には巨大なゲーセン兼パチンコ屋があり、ここら一帯の治安の悪化に一役買っているらしい。常連同士の喧嘩で夜にパトカーが出動することもちらほら。今日もその類だろうか。
缶ビール片手にふらふらとベランダに近づいてカーテンを開くと、煌々と光るライトがパチンコ屋の駐車場を明るく照らしている。
ベランダの戸を開き、サンダルに履き替える。駐車場を見てみればその真ん中で、小太りの男がひとりでなにやら叫んでいる。
なーんだ喧嘩じゃないのか、つまんねぇな。
おもむろにタバコを取り出し火をつけた。紫煙を燻らせている間も、男が全身を使って何かを叫んでいる。
なんだよあいつ、頭おかしいんじゃねえのか。
煙を吐きながら鼻で笑っていると、他の部屋のベランダの戸の開く音が複数聞こえてきたので、俺は急いでタバコを消した。
「……なにあれぇ……」
「警察呼ぶか?」
小声の応酬。ひとつ下の階だろうか、たしか若めの夫婦が最近引っ越してきていた気がする。
やめとけやめとけ。通報なんかしたって警察から事情を聞かれて、面倒なことに巻き込まれるだけだ。
心の中でのアドバイスを彼らが聞き入れたかは知れない。どうするー? なんて言いながら彼らは居室に戻ったらしいので。
缶の中のビールも残り少ない。そろそろ引き上げるか、そう思って一口含んだ、その時。
「むとうーーーー!! むとう!! む・と・うーー!!」
むせ返るかと思った。「むとう」。「武藤」。
俺の名前だ。
男は顔を真っ赤にして、俺の名前を叫び続けている。
誰だ、あいつ。まさか俺の知り合いか?
「むとうーーーー!!」
缶ビールを置いて、思わず身を乗り出す。
俺と同年代くらい、より僅かに上か? だがあんな小太りのおっさん、しかも苗字を呼び捨てしてくるような奴が知り合いにいただろうか?
「むーーとーーうーー!!」
目を細め、さらに身を乗り出す。
──その時、気づいた。
俺だけだ。
このマンションで、身を乗り出してまであの男の顔を確認しようとしているのは、俺だけだ。
当然だ。だって、俺だけが名前を呼ばれているんだから。
武藤なんて名前のやつは、このマンションに俺しかいないんだから。
男の顔を見て確信する。やっぱり、いない。あんな男は知り合いにいない。なぜあいつは、あの男は、知り合いでもない俺の名前を呼んでいるんだ……?
駐車場のライトが明るく、男を照らしている。
いつの間にか叫ぶのを止めていたそいつの、いやに円らな瞳と目が合った。
口角を上げたままで、男の唇が動く。ずっと叫んでいたから声が出せないのかもしれない、唇だけが大げさに動いている。
──『むとう、みーつけた』。
男が笑顔のまま走り出す。見た目とは裏腹に俊足で。駐車場を出て橋を渡り、かと思えば律儀に手前の歩行者信号の赤で止まっている。
終始、円らな瞳が俺に向けられている。
あ、これ、ヤバい。
信号が青に切り替わり、男が再び駆け始めた。腕白な子供が自転車を乗りこなしたときのような、無邪気なスピードを維持したまま。このマンションの裏口に吸い込まれるように──消えた。
俺は震える心臓を抑え、サンダルを脱ぐのに手間取りながら玄関へ向かって走る。
階下の夫婦が、どうか警察に通報してくれていますように。そう願いながら。
終


