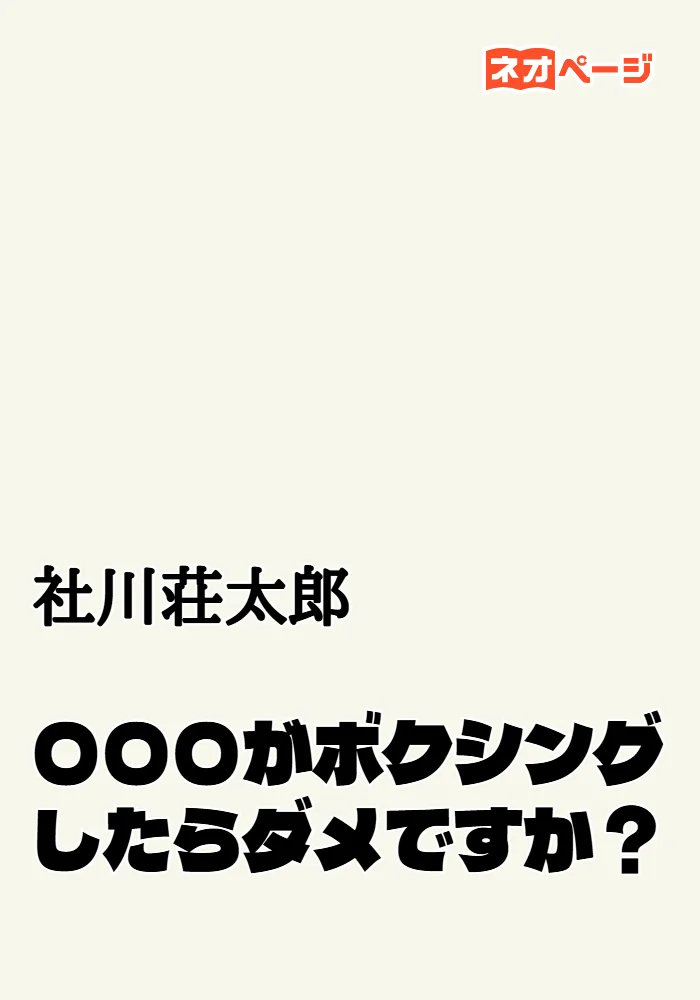
公開日
完結済
監督が僕のために審判団と揉めているのを見て、僕は申し訳ない気持ちでいっぱいになった。
全国高等学校総合体育大会ボクシング競技大会予選。
リングに立った僕の、周りの人間とは違う姿を見て、会場中から大量の野次が飛んだのは数分前のことだった。
――人とは違う僕がリングに立つことで日本中で巻き起こることになる一大騒動とは…⁉
第1話
「高体連の規約にはそんなこと書いてないでしょう!」
監督が僕のために審判団と揉めているのを見て、僕は申し訳ない気持ちでいっぱいになった。
全国高等学校総合体育大会ボクシング競技大会予選。
リングに立った僕の、周りの人間とは違う姿を見て、会場中から大量の野次が飛んだのは数分前のことだ。
すぐに審判団がやってきて、僕に「失格」の二文字を告げてリングから降りるよう命じた。
僕がボクシングの大会に出ようだなんて、最初から無茶だったんだ……。僕は涙をこらえ、おとなしくリングから降りようとした。
だが佐藤監督は――僕を異国の地からここ日本に連れてきてくれた自慢の監督だ――僕のために審判団に詰め寄ってくれたのだった。
「規約には書いていないかもしれませんが、これを認めてしまうと公平性が保てなくなりますので」
「なにが公平性だ! その公平性とやらで、これまで必死に努力してきたあの子の挑戦を否定する権利があんたらにあるのか?」
「そう言われましても、決まりは決まりですので」
「だから決まりって言ったって、どこにも書いてないじゃないか」
「書かなくても分かるから書いてないだけですよ」
「分からないからこうして揉めてるんだろうが」
「だってカンガルーをボクシングの試合に出そうだなんて、誰も考えつかないですよ。そんなわけないですもん」
オーストラリアの大地で監督にスカウトされ、飛行機に乗って日本にやってきたときから薄々感じてはいた。
日本語を理解するために一生懸命勉強をしている間も、ボクシングのルールを覚える間も、常にそれは頭の片隅にあった。それでも、僕らは万に一つの可能性に賭けてこの大会に臨んだ。だが、結局僕のようなカンガルーがボクシングの大会に出場することは認められなかったのだった。僕がカンガルーだったばっかりに――。
監督はまだ諦めずに審判団を相手に大きな声を出していた。
「あの子の肌の色が違うからダメなのか」
「肌の色はこの際関係ないです」
「じゃあなんだ、ちゃんと高校にも入学してるんだぞ。学生手帳だって袋に入ってる」
「ボクシング大会にカンガルーが出ることより高校に入学できたことが驚きですよ」
「人間に換算すると高校生くらいだって、現地のガイドも言ってたんだ」
「その『人間に換算すると』っていうのでおかしいと気づいてください」
「袋に赤ちゃんが入ってることを心配しているなら大丈夫、彼はオスだから。オスは子育てしないから袋もないんだ」
「だからメスが袋で子育てをするような生物は、この大会には出られないんです」
これ以上抗議しても無駄だと、ようやく監督も悟ったらしい。
「すまない、力になれずに」、そうやって頭を下げると、佐藤監督は僕にリングから降りるよう促した。次の瞬間だった。
「俺は別にいいっすけど」短い髪の毛を赤く染めた対戦相手は言った。「別にカンガルーでもなんでもいいっすよ。どうせ勝つんで」
対戦相手が納得しているというのは、審判団たちが正式な議論を始めるのには十分な動機になった。
ある審判は「確かに規約には書いてないですよ」と言い、またある審判は「じゃあカバやサイが大会に出てきたら認めることになりますよ」と主張。これに対し「カバやサイはグローブを付けられないでしょう」と反論を受けていた(僕はグローブもヘッドギアも付けていた)。
協議は一時間以上に及び、結果、世界で初めて、カンガルーと人間の試合が開催されることになった。
ゴングと同時に、僕は右ストレート一発で対戦相手の顎を砕き彼をリングに沈めた。
会場中からブーイングが飛んだが、僕は監督が喜んでいる姿を見れたらそれで良かった。
だが、オーストラリアからはるばるやってきた僕の物語は、これで終わらなかった。
※
結局、僕はその年のボクシング競技大会のチャンピオンになった。
初めて人間の競技に人間以外の動物が出て、いきなり優勝をおさめたのだ。それはもう国民の反応は物凄かった。
「動物が人間の競技を穢すな!」
「人類の権利を守れ!」
「動物は出しゃばってくるな!」
ただ、中にはこう言う人もいた。「それって人間だけを特別扱いした差別じゃないですか?」
僕らにとって運が良かったのは、その時期、人類はことさら『差別』という言葉に弱かった。
最終的には僕のトロフィーは没収されることもなく、2024年度チャンピオンの名前には『ワラビ』という監督が付けてくれた僕の名が刻まれた。
そこからの流れは凄かった。
次の週、福岡県で開催された水泳大会に本マグロが出場登録された。
大会当日、水を張った軽トラの荷台に乗ってやってきたマグロを出場させて良いかどうか、主催者は緊急会議を開催することになった。
大会の開催時間を二時間遅らせて主催者側が出した結論は、水泳大会へのマグロの出場を認めるというものだった。
やはりカンガルーがボクシング大会で優勝をおさめたという前例があったのは大きかった。また、ここでマグロの出場を拒否したとなると、哺乳類の権利が認められたにも関わらず魚類の権利を認めないという差別主義者の烙印を押される可能性があった。
六人(五人と一匹)が自由形で同時に泳ぐ予定であったが、うち三人がマグロとは一緒に泳げないと参加を拒否。二人と一匹での勝負となった。
同様の事例は各地で発生した。
とあるソフトボール大会には動物園からオラウータンを借りてきて四番打者として立たせ、代走にはチーターを起用。また守備では大鷲が全てのフライをアウトにしてしまった。
サッカーではアジアゾウにゴールを守らせ攻撃では俊敏なサル軍団が相手チームを翻弄した。
また砲丸投げでは一時期エントリーがゴリラのみとなった。彼らはスポーツ動物と呼ばれ、瞬く間にスポーツ界を席巻した。
中高の部活に留まっていたこの流れは次第にプロの世界までも幅を利かすようになり、これに怒ったのは努力を積み重ねてきた競技者たちだった。
「我々の努力をなんだと思ってるんだ!」
「スポーツマンシップを理解できない獣にスポーツをさせるな!」
「動物が勝っても誰も感動しない!」
彼らの主張も理解できたが、当の球団のオーナーや部活動の監督たちが勝利のみを求めて人間よりも動物を出場させたがるのでどうしようもなかった。
そのような状況になってくると、僕と佐藤監督は恐怖を感じるようになっていた。後に告白してくれたが監督も半分おふざけで僕をオーストラリアからスカウトしたらしく、このような状況は全く想定の範囲外だった。
ついには高校球児(だった高校生たち)とその保護者たちによるスポーツ動物ヘイト団体が動物園を襲撃するに至り、僕と佐藤監督はボクシング部の部室で震えて抱き合いながら騒ぎが収まるのを待った。
僕らの心配もつかの間、騒ぎが収束するのは一瞬だった。
それまで動物たちが持つ能力へのずるさにばかり注目され重要視されてこなかったが、ルールを理解しない動物たちの勝率はすこぶる悪かった。
例えば水泳大会を泳いだ本マグロはゴールにタッチできないどころか塩素水に入った瞬間に弱ってまともに泳げなかったし、オラウータンはバットで球審を殴って退場になった。また、チーターは二塁に走塁するどころか一塁に留まることができずアウトになったし、アジアゾウは股の間へのシュートにめっぽう弱かった。
結果的に、スポーツ動物の中でまともに試合ができたのはカンガルーのボクシングだけだった。
伊達に古くからボクシングのイメージキャラクターとされていない訳だと僕は思った。
※
「よし、いいパンチ入ってるから、次で決めよう! 足止まらないようにだけ注意して」
佐藤監督の声がリングに響く。
相手は右ストレートが武器の剛腕選手だった。
これまでの戦績は6戦6勝6KO。ただ、僕もカウンターには自信がある。相手のパンチを潜り抜け、長い鼻先を打ち抜く。
敵カンガルーはリングに崩れ落ち、僕は勝利を確信し右手を高く上げた。
スポーツ動物はすっかり衰退したが、ボクシングだけはカンガルーの独壇場となった。
あまりに人間とかけ離れた強さであったため、ボクシングは人間部門とカンガルー部門に分けられ、カンガルー部門は主に競馬と同じように公営ギャンブルとして愛好されるようになった。
人間と闘うことが許されない悔しさはあったけど、僕は今の待遇におおむね満足していた。
あの日、監督のおかげで僕はリングを降りずに済んだ。そのことはいくら感謝してもしきれないと思う。だって僕は誰よりボクシングが強くて、なによりボクシングを愛していた。
君はカンガルーがボクシングをしてはダメだと思うかい? ただ、カンガルーがボクシングをせずに、いったい何をするっていうんだい?


