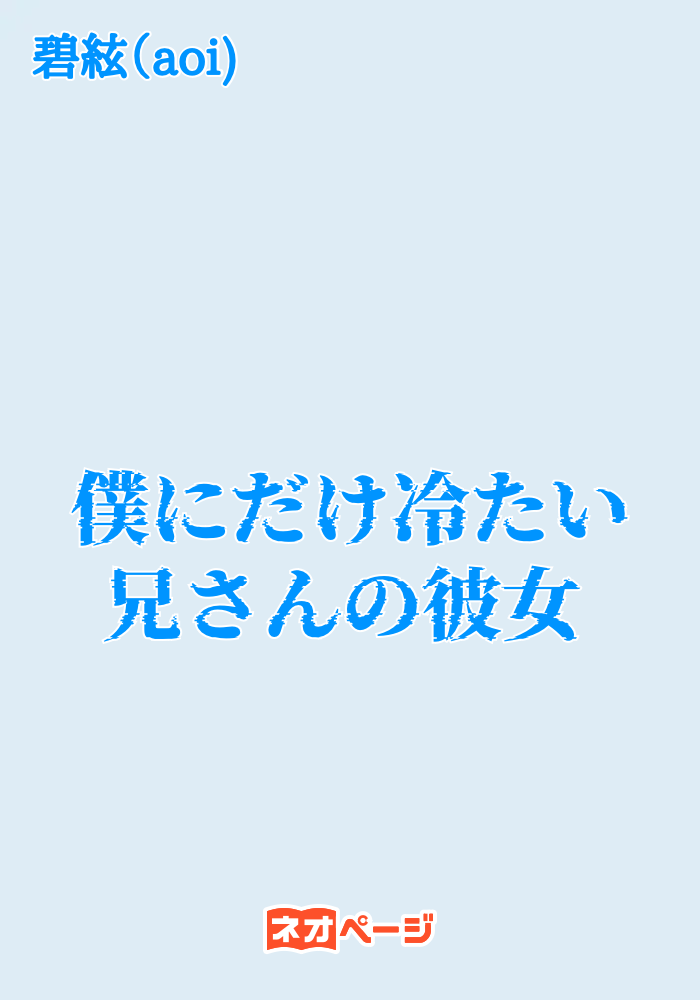
公開日
完結済
僕は嫌われることなんて、何もしていないのに。
兄さんの彼女、ユキさん
「どうしてあの場所にいたの? 私の後をつけてきたの?」
ベンチに座っている僕を、兄さんの彼女、ユキさんが仁王立ちで見下ろしている。
「違うよ! 本屋に行って、帰る途中だったんだ。偶然だよ」
ユキさんの目が冷たい。全く信じていない目だ。路地から出てきた雪さんに、ばったり出会しただけなのに、どうして怒っているのだろうか。
肌を突き刺すような冷たい風が吹いて、身体が震えた。
「本当のことを言いなさい」
「本当だってば! なんで僕がユキさんの後をつけるんだよ!」
「だってあなた、いつも私のことを気にするじゃない。気付いてるんでしょ?」
「気付いてるって、何に? 僕はただ、なんで僕にだけいつも冷たいのかなって——」
「冷たい……?」
ユキさんの目が険しくなった。何に怒っているのか分からない。
「ユキさ——」
「雪……?」
——えぇー‼︎ なんか暗殺者みたいな目をしてる! なんで!?
「やっぱり、気付いていたのね……」
また冷たい風が吹いて、ぎゅっと目を瞑った。一気に身体が冷えてガタガタと震えている。
「さ、寒……! 何?」
そっと目を開けると、白い雪がぶつかってくるのが見えた。なぜか、僕の周りだけが吹雪いている。
「何これ!」
「とぼけないでよ、気付いてたんでしょう? 私が普通の人間じゃないって」
たしかにこんな吹雪を起こすなんて、人間にはできない。そんなことができるとしたら——。
「もしかして、雪女……?」
「ほら、やっぱり気付いてたんじゃない」
「今、気付いたんだよ! どう見ても、僕の周りだけ吹雪いてるから!」
ユキさんは顎に手をあてて、僕を睨んでいる。
——めちゃくちゃ疑うじゃん。
「まぁいいわ。でも、もしバラしたら……氷のオブジェにしてやるから!」
ゴゥッ、と音がして、また僕の周りだけ吹雪が起こった。大粒の雪が全身にバチバチと当たってくる。呼吸ができない。
「じゃあ私は、
ユキさんが公園から出て行くと、吹雪は消えた。
「はぁ……。妖怪って本当にいるんだな……」
しかも兄さんの彼女だなんて。
トボトボと歩いていると「うぅ」と呻き声のようなものが聞こえてきた。男の声だ。
——ここは、ユキさんが出てきた路地だよな。
暗い路地を、恐る恐る進む。
「うぅ、う……」声がする場所を覗き込むと、ビルの室外機の奥に男性が倒れていた。その下半身が——凍っている。
「助け、て……バケモノ……」
「うわあぁぁあ!」
男性が手を伸ばしてきたので、驚いて逃げてしまった。
——絶対にユキさんの仕業だ!
ユキさんが出てきた路地に、下半身が凍った男性が倒れていた。もう間違いないだろう。
「こわっ! 怒らせないように気を付けよう……」
「おかえり〜」
家に入ると、兄さんが出迎えてくれた。そして兄さんの斜め後ろには、ユキさんの姿が。家に来るのなら、言ってくれたら良かったのに。聞いていたら、僕は帰って来なかった。
「今からおやつを食べるんだ。涼介も一緒に食べよう」
「えっ! えーと……」
ちらりとユキさんの方へ目をやると、ユキさんの後ろが吹雪いている。
「あ、僕はちょっと用事が……」
「いいから、一緒に食べよう!」
逃げようとしたが、兄さんに捕まり、キッチンへ連れて行かれた。
「涼介はどれがいい?」兄さんが冷凍庫を開ける。
「ユキがアイスを買ってきてくれたんだよ」
「あぁ、溶かさずに持って来られるから……」
——はっ! ヤバイ!
ヒュウっと音がして、首筋に冷たい風が纏わりついた。
恐る恐るユキさんを見ると——思った通り、激しく吹雪いている。ホワイトアウトでユキさんの顔が見えないのは、好都合なのかも知れない。
ただ、表情は見えないが、光るものが2つある気がする。ちょうど、ユキさんの目と同じくらいの位置に。
「ユキは何にする?」
兄さんが振り向くと、吹雪は一瞬で消えた。
——兄さん、ナイス!
「私はバニラにするわ」
「分かった。俺はどうしようかな〜。涼太は何にするんだ?」
兄さんは冷蔵庫を覗き込む。
「僕は、チョコで」
「じゃあ俺もチョコにしよう」
今日は兄さんがそばにいると、ホッとする。この状況では、ユキさんも何もできないだろう。
「あ、バニラも食べようかな。涼太は?」
「僕は、チョコだけでいいよ。ちょっと寒いし」
「寒い? 体調が悪いのか?」
「ううん、大丈夫だよ。部屋の中に冷気が漂ってるから……」
——あ。
見なくても分かる。肌を突き刺すような、冷たい風を感じた。おそらくまた、吹雪いている。
コン、コン、コン
——何の音……。はっ! 雪じゃなくて
雹が床に落ちる音だった。落ちた雹は勢い良く転がっているので、相当硬いのだろう。
落ちる雹が、どんどん大きくなって行く。すでにゴルフボールと同じくらいの大きさだ。氷の粒というよりは、氷の塊。当たると致命傷になるだろう。
ゴン、ゴン、ゴン
重そうな音が響く。
——鈍い兄さんでも、これはさすがに気付くだろ。
期待を込めた目で兄さんを見ると——。
「抹茶も捨てがたいな。涼太はどれがいいと思う?」
——ウソだろ。全っ然、気付いてない!
リビングの床は、氷の塊で埋め尽くされ、部屋の中は真冬のような寒さになっている。
——凍死する……。
「に、兄さん? ユキさんが呼んでるよ」
気付かないなら、気付かせてやればいい。彼女が雪女だということを!
「ん? どうかした?」
兄さんは前屈みになっていた身体を起こして、リビングにいるユキさんの方を向く。
すると、一瞬で吹雪は止み、床を埋め尽くしていた雹も消えた。なんて便利な力なんだろう。
「私は何も言ってないわ。涼太くんの勘違いよ」
ユキさんは、にこっと微笑む。でも、冷たい空気が首に纏わりついてきた。彼女は怒っている。これはおそらく、殺気だ。
リビングのソファーへ向かい、兄さんとユキさんは、向かいのソファーに座った。
兄さんは自分の前にアイスを3つ並べる。
「兄さん、そんなに食べて寒くならないの?」
「別に大丈夫だと思うけど。なんで?」
「いや、すでに寒……」
キイン、と足が冷えて、思わずアイスを机の上に叩きつけた。
「どうしたんだ?」
兄さんは不思議そうな顔をしている。
「な、何でもな、い……」
下を見ると、足首から先がキラキラと輝いている。これはガラスの靴ではない。氷の靴だ。刺すように冷たくて、身体が震える。
「どうしたんだよ、涼太。やっぱりバニラも食べたいのか?」
——ちっがう! 横にいる彼女が足を凍らせたんだよ!
段々と足の感覚が無くなっていく。これは氷を消してもらわないとマズイ。凍傷になりそうだ。
「ユキさ」
「雪?」
ユキさんが冷たい目で僕を睨みつける。隣に兄さんがいるのに、猫をかぶるのを忘れているようだ。
——今だ、兄さん! 隣を見て!
兄さんを見ると——アイスに夢中で、僕の視線にも気付かない。
——兄さんんんん……!!
やっぱり兄さんは鈍すぎる。だから雪女に狙われるんだ。
でもそんなことよりも、もう足が限界だ。
「凍、る……」
視線を上げると、何かがキラッと光った。
——げぇっ! 兄さんの後ろに
鋭利な先端が、僕に照準を定めている。6本の太い氷柱の先端が、ギラギラと輝いている。攻撃力が高すぎるだろ。
それでも兄さんは気付かない。相変わらず、美味しそうにアイスを食べている。
——兄さん……?
思っていた以上に兄さんが鈍い。これは、ユキさんが吹雪を起こしているところを見せたとしても、彼女が雪女だと気付かない可能性がある。
——あ、足がぁ……!!
本当に、足が限界だ。もう感覚がない。
「ちょっと、トイレに行ってくる」
兄さんがアイスを机の上に置くと、氷柱と冷気は、さぁっ、と消えた。ただ、僕の足は凍ったままだ。
兄さんがリビングを出てドアを閉めると、ユキさんは足を組んで、ふんっ、と鼻を鳴らす。兄さんがいる時とは別人だ。
「そうだ。やっぱり足だけじゃなくて、全身を凍らせてみましょうか。人間にとっては貴重な体験でしょう? 遠慮しなくていいわよ」
「いいえ、結構です! お気遣いなく!」
秘密を共有すると、仲が深まると聞いたことがあるけれど、あれは嘘だ。ユキさんは前よりも、もっと冷たくなった気がする——。
〈了〉


