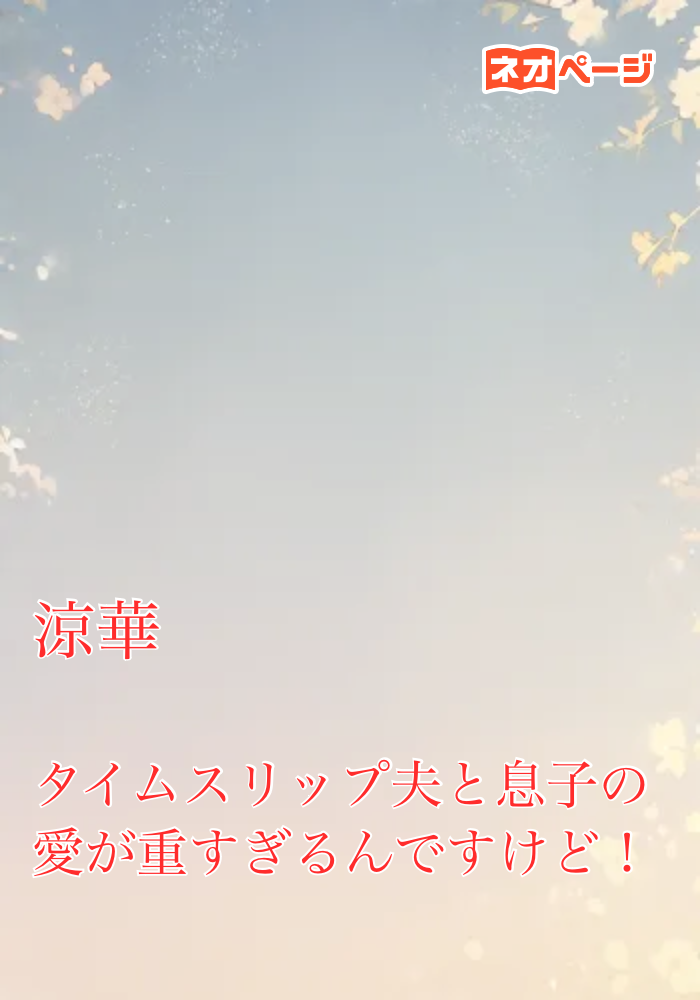
公開日
連載中
ソフィアが目覚めたのは、前世で夢中になった乙女ゲーム「君が未来を照らすから」の世界。
そのルートに登場するのは、冷たく険しい態度を取る夫・エドガーと皮肉屋の息子・アレクシス。
一見すると冷え切った関係に見えるこの家族だが、実は彼らはソフィアを救うために未来からタイムスリップしてきた当人たちだった。
5歳の息子アレクシスは、前世では母を憎んでいたものの、彼女が無実だと知り、後悔から過去に飛ぶことを決意。
一方、夫エドガーは、かつて妻が非情な態度の裏に隠していた真実を明かすため、過去に戻り、妻を守るべく行動を開始する。
だがソフィアは、ゲームで何度挑戦してもバッドエンドしか迎えられなかった「家族ルート」の攻略がいかに困難かを知っていた。
夫の過剰なまでの視線、息子の不器用すぎる愛情表現――それらに戸惑いつつも、ソフィアは一歩ずつ前に進む。
これは、タイムスリップした息子と夫、そして彼らを見守る主人公が紡ぐ、新たな「家族愛」の物語。
果たして彼らは、過去の傷を癒やし、未来を照らすことができるのか――?
ソフィアは静かにパンにバターを塗りながら、目の前の光景を観察していた。
長いダイニングテーブルに座るのは三人。無言で朝食を摂る家族。
一見すれば、冷え切った関係に見えるだろう。
夫のエドガーは険しい表情を崩さず、食事に手を伸ばす。
その仕草ひとつひとつが無骨で、愛情の欠片も感じられない。
そして息子のアレクシス。
5歳になったばかりの彼は、座るなり「これ、また昨日と同じパン?」と文句をつけた。
その冷ややかな声に、普通の母親なら溜め息のひとつでもつくだろう。
だが、ソフィアは違った。
彼女の視線は、夫と息子の背後に隠された真実を見抜いている。
夫のエドガー。
無言で食事をしているが、その瞳は隠しきれないほど熱を帯びている。
ソフィアの小さな仕草一つ一つを、鋭い視線で追っているのだ。
まるで、何かを確かめるように、そして何かを悔やむように。
息子のアレクシス。
皮肉交じりの言葉を投げつけるが、その声音にはどうしようもない愛情が滲んでいる。
ソフィアの気を引きたくて仕方がないのだろう。
だが、素直になれないのは、彼が抱える罪悪感のせい。
「ああ、これ…知っているわ」
ソフィアは心の中で呟いた。
そう、この光景は彼女が前世で愛してやまなかった、あの乙女ゲームそのものだ。
タイトルは「君が未来を照らすから」。
タイムスリップしたキャラクターたちが、過去の罪を背負いながら、大切な人を救うために奮闘する切なくも美しい物語。
プレイヤーは、彼らの隠された事情を解き明かし、散りばめられた伏線を紐解きながら、愛と絆を育んでいく。
しかし、この「ノクス家の家族ルート」は攻略が極めて難しかった。
息子の不器用な愛情、夫の不穏な視線、その裏に隠された真実をすべて理解しなければ、彼らとの関係は破綻し、バッドエンドを迎える。
「バッドエンドルートは涙腺崩壊必至」「ノクス家ルートは心臓に悪い」──そんなプレイヤーの悲鳴が攻略サイトを賑わせた、伝説のゲームだ。
もちろん、ソフィア自身も何度も挑戦した。
彼女は息子と夫の複雑な心情を理解しようと努力したが、どうしてもハッピーエンドには届かなかった。
画面越しのキャラクターたちは、必ず最悪の結末に飲み込まれていったのだ。
「誰か、ノクス家ルートでハッピーエンドを見た人はいないの?」と、プレイヤー仲間たちと嘆き合った記憶すらある。
だが、今のソフィアにとって、これはもうただの「ゲーム」ではなかった。
彼女は転生し、この世界に生きている。
目の前で無愛想に朝食をとる息子も、不器用な視線を送る夫も、もう画面の中の存在ではない。
彼らは生身の人間であり、ソフィアにとって、紛れもない『本物の家族』なのだ。
「あのゲームでできなかったこと、今度は現実で成し遂げる番ね」
ソフィアはパンに手を伸ばしながら、そう静かに誓った。
彼女の目の前には、攻略失敗が当たり前だった世界が広がっている。
しかし今回は、プレイヤーではなく、物語の中心にいる「彼女自身」がその結末を書き換えるのだ。
タイムスリップした息子と夫。彼らの抱える罪と苦悩を解き明かし、悲劇を覆す――。
新しい物語の幕が、静かに上がろうとしていた。
「さて、どうしたものかしらね」
ソフィアは微笑みを浮かべながら、再びパンに手を伸ばした。
彼らの事情を知っているからこそ、今度は違う結末を紡ぎたい。
ただの「ゲームの記憶」に終わらせるつもりはない。
そのとき、不意にエドガーが顔を上げた。
「今日のスープ、いつもより美味いな」
その声は低く、まるで無理やり捻り出したようだったが、確かに彼女への気遣いが込められていた。
アレクシスも、パンを一口齧りながら言った。
「まあ、これくらいなら悪くないよ」
その態度はどこか照れ臭そうだった。
――家族としての第一歩。
ソフィアは微笑みながら、心の中で呟いた。
「この物語、今度は私が書き換えてみせるわ」
そして、新たな朝が静かに始まった。


