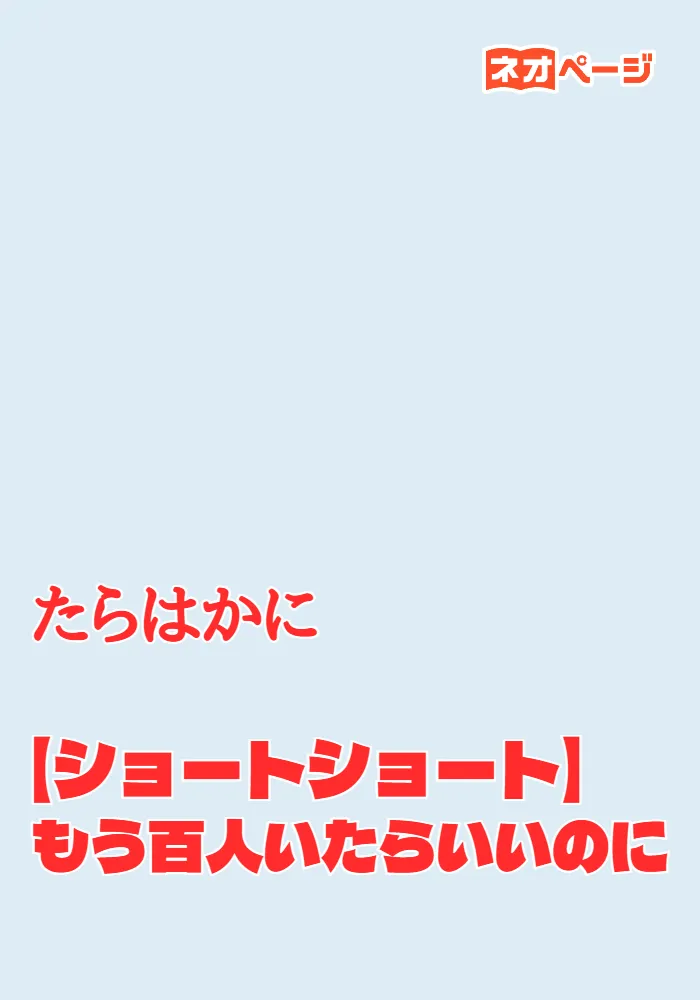
公開日
完結済
もう百人いたらいいのに
眠い目をこすって教室に入ると、いつもの自分の席に座った。そしてチャイムが鳴るといつものようにつまらない学校生活が始まる、はずだった。
ヨレヨレの白衣を着た担任の角田が教室に入ってきた。その後をパリっと新品の白衣を着た角田が入ってきた。そして二人の角田は教壇に並んで立ち、今日の出席を取り始めた。
まるで双子のようにそっくりな二人の角田が教壇に立っている。違っているのは白衣の汚れと寝ぐせくらいだった。角田(右)は学級日誌を手に持ち、角田(左)は黒板に文字を書き始めた。僕に見えている角田の像が二重になっているわけではない。まちがいなく角田が二人いる。
僕は教室を見渡した。角田の異変に誰一人反応している人はいなかった。昨日学校を休んだだけで世界が変わってしまったのだろうか。すると角田は僕に向かって交互に声をかけてきた。
「田中、まだ具合が悪いのか?」
「昨日休んでたんだから無理するなよ」
「それとも、まさか仮病か?」
「バカは風邪ひかないっていうしな」
角田(右)と(左)の笑い声がユニゾンで教室に響いた。性格の悪さも増幅している。隣の席の寅井が僕に囁いた。
「角田、昨日アレだったんだって」
「アレって、アレ?」
寅井は頷いた。アレとは国が発表した分裂症の事だ。
【総務省からのお知らせです。朝起きると自分が二人になっている場合があります。幽体離脱や細胞分裂ではありません。様々な陰謀論がSNSで発信されておりますが、東都大学の研究では現在の所【超自然現象】と結論づけました。落ち着いて近くの区役所へご連絡し、新しく生まれた方の住民登録を済ませてください】
驚きのあまりため息をつくと、僕の前に座っている生徒が後ろを振り向いて僕に話しかけてきた。
「角田のダジャレが二倍でウザかったぜ」
その顔は寅井だった。
更に僕の背中をトントンと叩く者がいた。恐る恐る振り返ると寅井がにこやかな笑顔で話しかけてきた。
「昨日授業中に二人目の角田が後ろで見張ってるの、最悪だったよ」
知らない間に寅井包囲網の中にいたようだ。
突然、二人の角田が同時に寅井ズを指さした。
「そこの寅井と寅井と寅井! 私語はやめろ!」
「私語は死んだ後にしとけよ」
「死後だけにな」
角田(右)(左)は再びユニゾン笑いをした。
角田や寅井の増殖でいつもとは違った学校生活を送り、ようやく帰宅した。ネットでは今日も有名人や著名人が分裂したというニュースが次々と流れている。分裂症は日本中で混乱を生んでいるが、僕はこの状況を前向きに受け入れていた。
いつもより早い時間に教室の席に座り、ドアから入ってくるクラスメイトを眺めていた。五人に増えた寅井がラインダンスをしながら入ってきた。でも僕が期待していたのは彼らではない。
「おはよー」
明るい声で涼子が一人で教室に入ってきた。僕は心の中で軽く舌打ちをした。
涼子にフラれたのは先月だ。告白した時に、彼女はこう言った。
「田中君はとっても素敵な人だから嬉しいよ。でもね私には雄二がいるから」
「そっか、雄二と」
「ごめんね隠してて。もうしないから」
「大丈夫、僕は涼子が幸せならそれでいいから」
「――もし私が二人いたらよかったのにな」
あの言葉は、分裂症が日本中蔓延する前の事だった。だから彼女のことは諦めたつもりだった。でもこうなったら話が違う。今日は増えなかったが、また明日に期待しよう。
次の日、涼子は増えなかった。一方、寅井は六人に増えた。
また次の日、やっぱり涼子は増えなかった。一方、寅井は八人に増えた。
そのまた次の日、相変わらず涼子は増えなかった。一方、寅井は二十三人に増えた。
来る日も来る日も寅井ばかり増えていく。増えすぎた寅井用の机は置けなくなり、余った寅井達は教室の後ろで一列に並んで授業を受けていた。これ以上増えたら寅井だけのクラスができるかもしれないと噂され始めた。
そして一か月経って、少しずつ社会が分裂症に適応し始めた。僕の好きだったアイドル、可愛花恋は七人に増えてアイドルユニットとして活動することになった。とある野球チームは四番打者が三人になっているそうだ。そして寅井は七十人に増えて、沢山の寅井たちは体育館に集まって教室の授業を中継しながら受ける事になった。
そして分裂症に人類が慣れ始めたある日。
今日も涼子は一人だった。しかし僕は思う所があり、涼子を放課後に理科室へ呼び出した。
「話って?」
「涼子はさ、まだ隠しごとしてるよね」
「もう雄二の事は言ったよね」
「違う、それじゃない。――本当は分裂してるよね」
涼子は僕の言葉に驚いた様子だった。しかし僕は続けた。
「分裂する人の特徴、知ってるだろ」
分裂する人々の特徴が分かり始めていた。分裂している人々は何かしら優秀な能力を持っている。
「角田は元数学の世界大会出場者。寅井は陸上で全国に行っている。だから分裂した。なのに涼子が分裂しないのはおかしいだろ」
「なんで? 私が分裂するはずないじゃない」
学校一の美形と言われ、全国模試でベストテンに入る涼子が普通のはずがない。
「絶対に涼子は分裂してる。僕には隠しごとはしないって言ったじゃないか」
すると涼子は観念したようにため息をついた。
「やっぱり田中君には」
理科室の後ろのドアが開き、二人目の涼子が入ってきた。
「嘘がつけないね」
三人目の涼子が教壇の下から現れた。
「でも」
四人目の涼子は廊下側の窓から。
「言いづらくて」
五人目の涼子は準備室の陰から。
「ごめんね」
六人目の涼子は天井にしがみついていた。
「これだけ増えてるのかよ。だったら一人くらい僕と……」
すると、それぞれの涼子の背後から雄二が顔を出した。
「雄二も増えてるの」
僕は愕然とした。
「そ、そんな。じゃあ雄二より涼子の数が多くなったら」
突然、校庭側の窓の外から僕の名前を呼ぶ声がした。窓から校庭を見ると、そこには運動会でもするかのように沢山の雄二達が列になって並んでいた。パッと見た感じで百人近くいる。
涼子達の横にいる雄二達は申し訳無さそうに頭を下げた。
僕は目の前の現実を受け入れきれず、二人、いや何人いるかわからない涼子と雄二のカップルをおいて、理科室を飛び出した。
校門を飛び出すと公園には涼子と雄二のカップルがブランコとすべり台とジャングルジムにいた。すれ違うカップルの二組のうち一組が涼子と雄二だ。駅前の牛丼屋は寅井で溢れかえっていたが、お洒落なカフェの客の九割は涼子と雄二のカップルだった。今までどこに隠れていたのか。なにが「もし私が二人いたらよかったのにな」だ。
交差点に立って赤信号を待っていると、道路の向こうで立っているのは全て涼子と雄二だった。僕は振り向いて逆方向に走り出した。
突然、僕は右手を掴まれた。振り向くとそこに涼子がいた。
「離せよ」
「いやだ。話があるの」
「話は無いよ。こんなの見せられたら。何が『もし私が二人いたらよかったのにな』だよ」
「だから。私、二人目の涼子。最初に増えた涼子だよ。田中君のために」
こうして僕は涼子と付き合うことになった。
そして週末。
今日は野球の日本一を決める試合があるらしい。優勝争いをしている二チームは全て同じ選手だそうだ。また、七人グループになった可愛花恋ちゃんは、全国五大ドームとアリーナ五ヶ所で同日同時刻ライブを来月末に開催するらしい。なんでもバックダンサーも全員可愛花恋ちゃんだとか。
しかしそんなことはどうでもいい。
今日は涼子と初めてのデートだ。
いつもより三十分早く目が覚めた。すぐにベッドから起き上がり一階への階段を駆け下りた。すでに父と母は朝食を食べていた。
「今日は朝ご飯いらないから」
父と母は不思議そうな顔をした。僕が休みの日に早起きするなんて珍しいのだろう。
「なに言ってるの、さっき食べて出かけたじゃない」
母の言葉を咀嚼するのに十秒かかった。その直後、自分の部屋に走った。スマホも昨日用意していた勝負服も無かった。僕は今起こっているであろう事実に愕然とし、慌てて家を飛び出した。
まだ間に合うかもしれない。やっと、やっと涼子と付き合えるのに。まさか雄二じゃなくて自分に邪魔されるとは。
僕は待ち合わせ場所に向けて全力で走り始めた。すると自転車に乗った僕が、汗だくの僕を颯爽と追い抜いていった。更に周囲に立ち並んでいる家の玄関から僕が飛び出した。道路のマンホールや側溝、電線の上からも僕が現れた。混乱している僕の耳に地響きのような爆音が聞こえてきた。振り向くと、何百人もの僕が鬼のような形相で僕を追いかけてきた。


