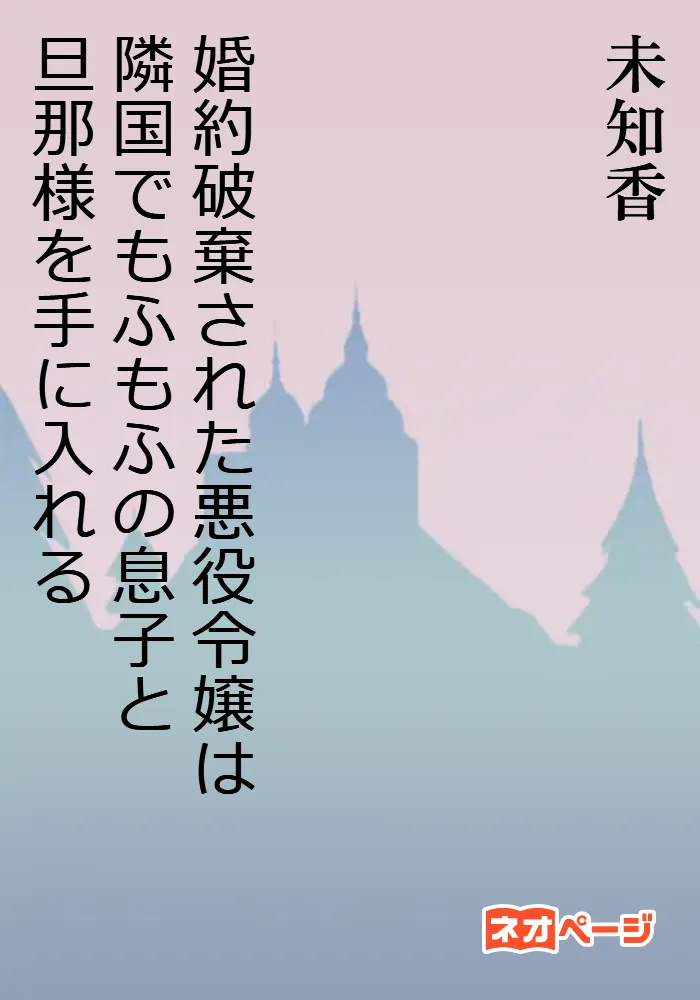
公開日
完結済
……そして、今まさに断罪されている悪役令嬢だった。
婚約者は憎しみを込めた目でフィリーナを見て、婚約破棄を告げた。
ヒロインであろう彼女は、おびえるように婚約者の腕に顔をくっつけて、勝ち誇ったように唇をゆがめた。
……ああ、はめられた。
断罪された悪役令嬢が、婚約破棄され嫁がされた獣人の国で、可愛い息子に気に入られ、素敵な旦那様と家族みなで幸せになる話です。
前編 婚約破棄の罠にかかる
確かに乙女ゲームは好きだった。
なんなら乙女ゲームのモブに転生とか憧れてた。
でも、転生先は悪役令嬢で、このタイミングとかいったいどうしろっていうの……?
私は途方に暮れていた。
「フィリーナ・ラエネック。残念ながら君とは婚約破棄だ。君が行った悪行についてはこちらに証拠が揃っている。侯爵令嬢だとは思えない所業だ」
良く響き渡る低い声が、しずかな学園の講堂に響き渡る。
冷たく侮蔑を含んだ声が、私に容赦なく降りかかる。
ゲームで聞いた時はときめく声だったけれど、その冷えた嘲笑は自分に向けられるとぞっとするばかりだった。
今、私は彼の前に這いつくばっている。貴族令嬢としてはあるまじき姿だ。
私の前には一人の少女と妙に顔の整った五人の男性がいる。更に私達を取り囲むようにたくさんの生徒たちが遠巻きに私たちを見ている。
学園の食堂の中には、たくさんに人が居るが、しかし誰も私に手を貸そうとはしない。
当然だ。
彼らは乙女ゲームの攻略者たちで、王族を含む高位貴族だ。
私は今まさに断罪されている悪役令嬢だった。
中心に居て私に冷たく告げているのはテオフィール・リシュリュー。私の婚約者だった人だ。
金色の瞳に金色の髪。傲慢ともとれる程の自信に満ちた顔は、上に立つものとしてのカリスマとなっている。
王太子である彼は、当然のように攻略対象者だった。私は彼のことが好きで好きで、けれどどんなに頑張って努力しても関係は変わらなかった。
いつでも私には優しくなかった彼は、ついに運命の相手と出会ったらしい。
彼の隣に居る小動物系の可愛い女の子が、きっとこの乙女ゲームのヒロインなのだろう。
ゲームでは名前はなかったけれど、確か彼女の名はイリス・ツーボン、伯爵令嬢だ。
「……テオフィール様、私は」
「大丈夫だ。君は私の後ろに隠れていればいい」
「ありがとうございます。あの、私にはテオフィール様が居るのですから……頑張りますわ」
「無理はしないでくれ。傷ついた君をこれ以上つらい目には合わせたくはないのだ」
「そんな……。でも嬉しい、です」
彼女はそっとテオフィールの服の裾を掴み、うるんだ目で私の事を見ている。しかし、その目の奥には愉悦が潜んでいた。
おびえるようにテオフィールの腕に顔をくっつけて、勝ち誇ったように唇をゆがめた。
……ああ、はめられた。
フィリーナとしての記憶をたどっても、彼女を虐めたりなんてしていなかった。
私の顔はいかにも悪役令嬢だったし、嫉妬から嫌味を言ったけれどそれだけだ。褒められた行動ではないが、婚約破棄をするには罪が軽すぎるはずだ。
「何とか言ったらどうだ!」
グラードが私を睨みながら見下ろす。大柄で筋肉質な彼はテオフィールの側近であり、こちらも攻略対象者である。
この男に突き飛ばされ、私は前世の記憶が戻ってしまったのだ。
……記憶がよみがえった為にまだゲームと同じだと冷静になれるだけ、感謝するべきなのだろうか。
そもそも婚約破棄するとはいっても、まだ王太子の婚約者である私を突き飛ばして床に這いつくばらせるとか、貴族の男としてどうなの?
私が不快な顔を隠せずに睨むと、グラードはかっとしたように怒鳴った。
「イリス様がどんなにつらいかわからないのか!」
ゲームでは大型犬のように可愛かった彼だが、今はただ乱暴者にしか見えない。無駄に筋肉質な体格が、圧迫感があって怖い。
私がびくりと肩を震わせると、ヒロインは眉を下げて見せた。
「そんな言い方したら、フィリーナ様が可哀想……」
元凶の彼女は弱弱しく震える声で、定番の台詞を言う。
「ああ、すまない。イリス様のお気持ちを考えたら……」
私には怒鳴ったグラードがしゅんとしたように身体を小さくしている。
「私の為に……ありがとう」
ヒロインが感動したように笑い、グラードが照れたようにはにかんだ。そんなヒロインを愛おしそうに見て、テオフィールは彼女の肩をなでた。
「君は優しいな。君がされたことを思えば、こんな事ぐらい当然なのに」
微笑まれ、ヒロインは急に顔をぐしゃりとゆがめた。
「……それでも、わたし、わたし」
「泣かないでくれ」
大きな目から涙が溢れ、テオフィールが悔しそうに彼女を抱き寄せる。そのままヒロインは声を殺すように、すすり泣いた。
それはしんとした空気の中で、悲し気に響き渡る。
周りの空気が一気に彼女に同情的になったのがわかった。
私から見ても、抱きしめてあげたくなるような可憐さだ。
「……駄目だわ」
ここで悪役令嬢である私が反論したところで、よりひどい事になるだけだろう。
皆が私に憎しみに満ちた視線を送り、小動物のような彼女は、ちらりと私を見て微笑んだ。
この茶番じみた断罪を、私はどうにもならない気持ちで眺めていた。
*****
悪役令嬢が婚約破棄や誤解を覆せるはずもなく、私は色々な現実に押しつぶされそうになりながら学園から家に帰ってきた。
そして、家に着きほっとすると、この婚約破棄は侯爵家への影響もあると気が付いた。すぐに父に報告しなければいけないと、私はそのまま父の執務室に重い足取りで向かった。
父は若い頃に侯爵位を継ぎ、王城で宰相としても働いている。冷静で怜悧な父は、皆に恐れられていると同時に影響力がある。
ゲームでは何度も見たが、実際に目の前にするとできる人の圧がすごい。どうなるのだろうと心臓がどきどきとする。
しかし、当然説明しないわけにはいかない。たどたどしく事実を伝える私の言葉を意外にも父はじっと聞いてくれた。
「……ということなのです。大変、ご迷惑をおかけして申し訳ありません」
「謝るな。お前のせいだけではない。……ああ、そうだな。ちょうどよかったんだな」
私が一通り話し終えると、父は拍子抜けするほど軽い口調で言った。
「どういう事ですか?」
「お前はおそらく隣国であるグラッサーグの王へ嫁入りとなる。……戦争に対する莫大な賠償の一部に令嬢の嫁入りが含まれていた」
「戦争に対する莫大な賠償? 戦争では多少の賠償があったとは聞いていましたが……初耳です」
「惨敗だという事を隠しているからな。グラッサーグへの嫁入りなど、普通の貴族は応じないだろう。公にしていない以上、グラッサーグという獣人の国への嫁入りだと蔑む目を逃れることは出来ない」
「確かに、獣人は本物の獣のようだと」
「実際は違うがな。知性も品位も力もある。しかし、偏見というのは難しい。……この事もあってお前との婚約破棄をすんなり認められたのだろう。罠にかかったという事だ」
「そんな裏があっただなんて」
「諦めろ。……お前が浅はかだったのだ。相手の女の方が上手だった。妃になる為には、そういう腹黒さは必要だ。更にお前の悪行を我が家の落ち度として、王家はこちらの力も削ぐつもりだろう」
「っ……申し訳ありません」
転生前の記憶を思い出して混乱していたとはいえ、あの場で家に迷惑をかけてしまう事を思いつかず悔しくなった。
父が築いてきたものを、私が壊してしまう。私にだって、何かできたかもしれなかったのに。
ただ断罪という場に呆然としていた自分が恥ずかしくて、悔しくて涙がにじんだ。
悔やみぎゅっと手を握る私の肩を、父はそっと撫でた。
「このままにすることはない。安心しろ。フィリーナ、お前をしあわせにすると言った言葉を反故にするなど、死に値する」
私と同じような悪人顔の父が、顔に似合うセリフを言う。
「お父様……」
「お前は私の可愛い娘だ。この素直なところが可愛いというのに」
私の事をぎゅっと抱きしめてくれた父の体温に、私の目からは涙が零れた。背中をとんとんと叩いてくれる手つきが優しく愛情を感じ、泣きやみたいのにどんどん涙が流れてしまう。それを父がそっとハンカチで拭いてくれる。
温かな父に手を回しぎゅっと抱きしめた。
この世界がゲームだと思い出していても、断罪は怖かったのだと、今さらながらに思った。
前世の記憶が戻った分客観的になれた部分があるとはいえ、私はテオフィールが好きだった記憶も確かにあり、断罪は苦しかった。
「お前にはグラッサーグについて教えておこう。大方の貴族が思っているようなところではない」
「隣国だというのに、あまり交流がありませんよね。……確か獣人がたくさんいるんですよね」
「その通りだ。この国はグラッサーグを獣人の国として蔑んでいるが、おそらく文化としてもこちらよりも上だ」
父から聞いた隣国の話は知らないことだらけだった。
隣国であるグラッサーグは獣人の国として栄えている国だが、資源が豊富で大国だということだ。獣人といっても、技術も進化していて大きな国として力があるらしい。
軍事的にも、私達には計り知れない不思議な力を持っているという報告が宰相である父にあがっている。
私たちが住む国であるヴァライサよりもずっと規模が大きく、力がある。そう、父は認識していた。
隣国として、今後安定した関係を築いていくべきだと考えていた。
しかし何を血迷ったか陛下が戦争を仕掛け、あっという間に負けてしまった。
戦争があったことは父が多忙になった事で知っていたが、そんな状況になっていただなんて。
戦争自体は一カ月程度でしかなく、それも膠着状態になってしまった為に終戦となったと聞いた。
結局王族同士で話し合い賠償金を多少支払うことで手打ちになったと発表していたが、実際は従属国になったという事だった。
ゲームにはそもそも隣国自体が出てこない。
「全く知らなかったわ……」
「無能が隠しているのだ。このような大事いつまでも隠しておけるわけがないというのに」
無能というのは陛下の事だろうか。
……うち、反逆罪とかにならないかな。
父の言い草にひやひやしながら、私は疑問を口にした。
「そんな力がある大国が、従国扱いになった国から嫁入りを望むのは何故でしょう? つながりを求める貴族へではなく、王族への嫁入りなのですよね?」
「何か理由があるのだろうが、知らされていない。……こちらでどうにかなるように手を打つから、待っていてくれ。それでもつらかったら何を置いても逃げてこい」
「ありがとうございます。……ごめんなさい」
「いいんだ。無能はこの機会に引いてもらった方がいい。こんな事をした無能たちに対し、私がこのまま黙っているとは思わないでくれ。それと、お前は浅はかなところは少し学ぶように。……まあ、少しでいいからな」
父は厳しい顔で苦言を言い、その顔のまま私の頭を撫でるので笑ってしまった。
知らない国に行くのは不安だけれど、父は味方だ。
断罪され婚約破棄もされ、急に知らない獣人に嫁入りする。
だけど、それでもこの状況は最悪じゃないと感じられて、嬉しかった。


