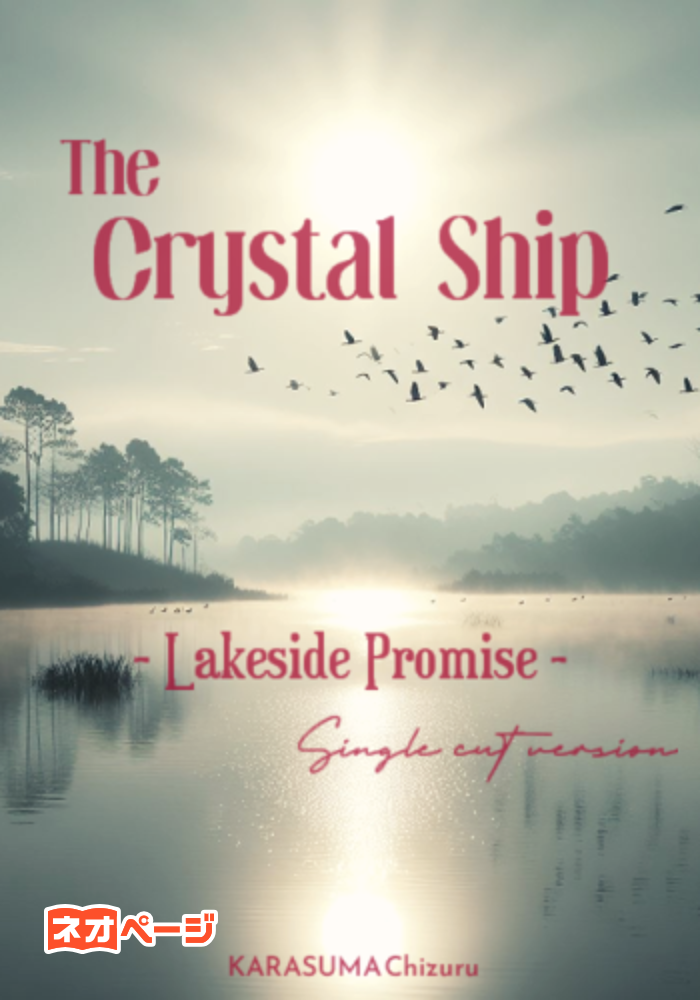
公開日
完結
湖畔の別荘で休暇を過ごしていた五人は、リヴィとジョシュだけを残していったん解散することに。押し負けるようなかたちでリヴィと付き合っていたジョシュは、ライアンにうんざりしてきていると打ち明けた。もう別れろと助言をし別荘を後にしたライアンだったが、ジョシュから動揺した声で電話がかかってきて――。
※【カクヨム】【ステキブンゲイ】でも公開しています。
※ 本作品収録のオムニバス短篇集〈 10 Love Songs and Stories -君を想いて-〉は【カクヨム】【pixiv】でも公開しています。
※ 作者は未熟です。加筆修正については随時、気づいた折々に断りなく行います。が、もちろんそれによって物語の展開が変わるようなことはありません。
※ この物語は、法律・法令に反する行為を容認・推奨するものではありません。
カバードポーチから入ってすぐ、右手に位置するリビングの家具はすべて奥のダイニングルームに押しこまれていた。薪ストーブが程良く暖めている室内にはギターアンプやベースキャビネット、ドラムやキーボードなど演奏に必要な機材や楽器が置かれている。ゆったりと広く天井が高いアメリカンカントリースタイルの室内は、宛ら七〇年代にどこかの片田舎にあったスタジオのようだった。
建物の半周を囲むデッキに繋がる掃き出し窓は、鳴り響く音にびりびりと微かに振動している。窓の外は紺青の緞帳と静寂に包まれていたが、バンドは誰にも気兼ねすることなく演奏を続けていた。
裏手は鬱蒼と茂った森、表へ出れば月の道が静かに揺れる水面。
ここは湖畔にひっそりと一軒だけ建った、まるで隠れ家のような別荘である。他には誰もいない――いるのは、今は森の木々に隠れて眠りに落ちようとしている鳥たちだけ。そして、辺りを照らしているのは窓から漏れる灯りと、月だけだ。
「――喉渇いちゃった。ライアン、飲み物取ってきてよ。なにか適当に、多めにね」
別荘の持ち主――正確にはその娘、だが――リヴィは、そう云ってマイクスタンドの前から離れた。ぴく、とリヴィのほうに顔を上げるとライアンは「ビールでいいか? みんなも」と尋ねながら、ベースのストラップを脱ぐように外した。
「あ、俺はコーラでいいや。まだ演るだろ?」
「悪いな、ライアン。俺はビールで」
ドラム担当のティムとギターのブレイデンがそう答えると、キーボードの前に立っていたジョシュは「あ、じゃあ俺も――」と、ライアンに向かって云った。
「手伝うよ。ひとりじゃ大変だ」
「いいよジョシュ。そんな遠くへ取りに行くわけじゃないし」
「そうよ。私はライアンに頼んだの」
リヴィがそう云ってジョシュに近づき、両腕を彼の頸に掛けた。それを見て、ライアンは作り笑いをしながら目を逸らした。
「ビールの五本や六本くらい、ひとりで簡単に持てるわよ。優しい人ね」
でも優しいのは私にだけでいいのよ、という媚びた声と、まったくいつもいつもお熱いねえ、という脳天気なティムの声を背に、ライアンは黙ったままキッチンへと入っていった。
五人は同じ大学の学生で、十二月の今は長い休みに入ったばかりである。
リヴィは欲しい物はすべて手に入れてきた、資産家の親を持つ我儘娘の典型的なタイプだ。髪はブロンドに染め、身に着けているのはブランド物ばかり。
とはいえ、
そんなリヴィの気紛れでバンドを始めようということになり、誘われたのがこの顔触れだった。
もっとも、ライアンはジョシュのおまけのようなものだった。ライアンは回想した――リヴィのお目当ては最初から優しい面差しのジョシュで、自分はジョシュが是非一緒にと推してくれた結果、ベース担当になっただけだ。彼女はきっと、ジョシュと付き合いが長く仲のいい自分のことは、邪魔者くらいに思っているに違いない。
「さっさと持ってきなさいよ。遅いわよ、ライアン。あ、出したぶん、ちゃんと冷やしておいた?」
「あとで俺がやっとくよ、リヴィ。ライアン、いつもすまない」
ジョシュは少し申し訳無さそうに云った。どうやら自分の恋人が、自分の友人にぞんざいな扱いをしていることには気づいているらしい。
否、ティムもブレイデンも気づいていないわけがなかった。ただ、味方する側を間違ってご機嫌を損ね、日々の旨い食事や酒、煙草に
「かまわないさ」
簡単に応えて、リヴィがジョシュに撓垂れ掛かるのが視界に入らないように顔を背ける。そしてその仕種をごまかすように自分のビールを開けると、ライアンはそれをぐい、と呷った。
休憩を挟んでまた一頻り演奏し、すっかり夜も更けた頃。五人は音楽をかけ、ジョイントを廻していた。滞在中はジョシュとリヴィが使っている一階の主寝室で、皆は床に坐りこみ、ベッドや壁に凭れてくすくすと笑っている。
たわいも無い話をし、カーテンを開け放った窓から覗く月明かりに浮かぶ景色にうっとりを目を細める。至福の時間だ。
「夏なら泳ぐのになー」
「泳いでくれば? お魚さんが遊んでくれるわよ」
酷ぇな、もう寒いし水も冷たいだろーとティムが笑う。
「泳ぐのはともかく、魚がいるなら釣りはできそうだな」
ブレイデンがそう云うと、リヴィは顔を顰めて首を横に振った。
「できるけど、釣れるのはマスキーくらいよ。冬場は浅いところにいて狙いやすいってパパが云ってたけど、食べても美味しくないし、それに釣りなんてつまんないわよ」
「マスキーパイクか……。確かに、ありゃあ食っても旨くないな」
「獰猛で、人に噛みついたりもするらしいしね」
「えっ、まじ? でかいの?」
アウトドアには無縁そうなティムが尋ねると、ブレイデンは両腕をめいっぱい広げてみせた。
「ああ、でかいやつは7フィートくらいあって、ボートに釣りあげてうっかり喜んでると、足の指を喰いちぎられたりするんだ」
「おっかねえ……絶対やるなよ、釣りなんか」
ブレイデンはたぶん大げさに云っているんだろうと思いつつ、ライアンはスマートフォンで『
「ほんとだ。見た感じ、旨くもなさそうだな」
「興味があるなら泳いで獲ってきなさいよ、ライアン。あなたのことは止めないわ」
ジョイントを吹かしながら、さもおかしそうに云うリヴィに、その隣にいるジョシュが困ったようにこっちを見る。目が合って、ライアンはいいんだ、慣れてるというように僅かに首を振ってみせた。
「ねえ、釣りなんかどうでもいいけど、一度いいお天気の日にボートに乗りましょうよ」
「寒くないか? それに、ボートから落ちたら喰われるんだろ」
「落ちないってば。それに、私を食べていいのはジョシュ、あなただけよ」
女王様の台詞にやれやれと目を見合わせて肩を竦め、ブレイデンとティムが腰を上げる。
「さて、そろそろ寝るとするか」
「あ、俺もー。じゃあおふたりさん、おやすみぃ」
「おやすみ」
「俺ももう部屋に戻るよ」
おやすみ、と云いながらふたりに倣い部屋を出ると、ライアンは後ろ手に閉じたドアに凭れ、溜息をついた。


