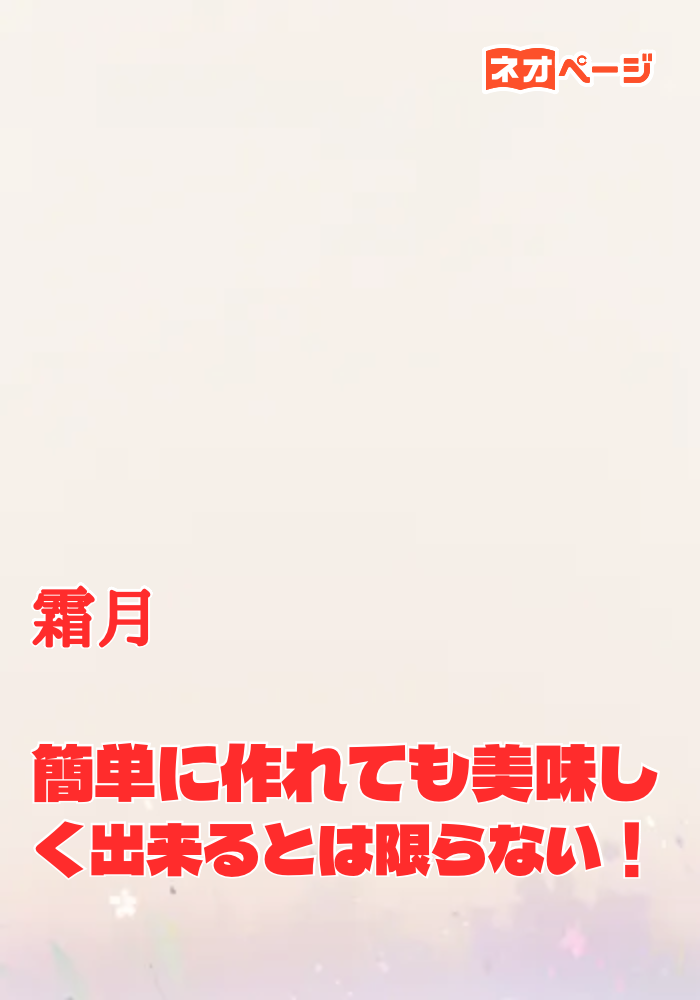
公開日
完結
なんと、普段ご飯なんか作らない彼女が夕飯を作って待っていた?!
その出来栄えは?!
さぁ、食え!! 湊!!!
僕の嫁は料理が出来ない。いや、まだ入籍をしていないから嫁ではない。料理は疎か、掃除もあまり得意ではない、今後、妻になる予定の10歳年上の彼女。
世の中的にはキャリアウーマンと呼ばれる類の女性であり、僕より収入が高い。今一緒に住んでいる家だって、彼女の家だ。
23歳の僕はそんな、彼女の言動の全てを許容している。たとえ、料理が作れなくても、家の掃除を微塵もしなくても、喉を通らないような不味い弁当を僕に渡して来ても、理解不能な考え方を押し付けられても、全てを愛している。
今日も仕事が終わり、愛する彼女の待つ家へ帰る。帰ったらまずやることは料理。共働きのため、惣菜を買って来てくれることはあっても、彼女は仕事のある日は、夕飯を作ることは、ない。
それでも良いと思っていても、少し寂しいこの頃。
玄関扉の前までくると、今日はいつもと違った。
「ご飯の良い匂いがする……」
鍵を差し込み、部屋へ入ると、キッチンに立つ彼女の姿が目に入った。ぉお!! 料理をしているではないか。衝撃。婚約してから、こんなこと一度でもあっただろうか?
いや、ないな!!!
彼女のそばにより、フライパンを覗き込む。なんの魚かは分からないが、小麦粉がまぶされた魚がバターで焼かれている。こ、これはムニエル!!!
「ムニエル?」
そっと後ろから抱きしめ、彼女に問う。
「あぁ、ムニエルだ。調味料で味付けし、小麦粉を振りかけてバターで焼けばバカでも作れる、と書いてあった」
「いや、そんな風には絶対書いてないでしょ……」
キッチンカウンターの上に置かれたスマホを手に取り、内容を確認する。表示されたレシピには『簡単に作れる』と記載されていた。どういう解釈の仕方してんの。めちゃくちゃ過ぎでしょ。
「
皿が2枚渡され、受け取る。魚の乗った皿をテーブルへ運ぶ。きつね色に焼かれた魚の上にはチーズが乗っており、出来立てのあたたかさで、とろりと溶けていた。美味しそう。
テーブルにご飯、味噌汁、箸と順番に並べていく。向かい合って席につき、手を合わせた。
「「いただきます」」
僕が箸を取ると、彼女はニコッと笑い、口を開いた。
「早く食え、湊」言い方!!!
「言われなくても食べますって……」
まだか、まだかと目を輝かせ、僕のことを見つめる彼女は、33歳のくせに子供のような無邪気さがある。その可愛らしさにいつも全てを許してしまう。
皐の期待に応えるかのように、魚に手をつけた。
「……こ、これは……」
「なんだ、言ってみろ」
口の中にある魚を飲み込む。テーブルに置かれたコップを掴み、口内へ水を流し込んだ。ごくごくごく。コップをテーブルに勢いよく置いた。
「魚そのものから海を感じる。まるで僕自身が、魚にでもなっているかのように、海水が口全体へ広がる。そして、そこに混ざる野生的で爽やかな香りと濃厚なコク。それが調和され、口内で聞こえないメロディーが奏でられる!!! とても水が進みます。(訳:塩辛くてクソまずい)」
「素直に不味いと言ったらどうだ」
黒い瞳が僕を見つめる。不味いなんて、言えないさ。だって君が一生懸命作ってくれた夕飯なんだから。
「不味くないよ、美味しいよ」
「そうか、なら私の分も食べるんだな」
僕の皿の上に、皐の食べかけのムニエルが積み重なる。
淡白な味の魚は塩気が引き立ち過ぎて、魚本来の良さなど、感じることが出来ない。皿の上に乗せないで。僕も自分の分で精一杯だから。
「…………(要らない)」
「ありがとう、ゆっくり食べてくれ」ひどい。
ひどい。欲しいなんて言ってないのに。
立ち上がり、どこかへ行こうとする彼女の手を掴み、引き止めた。
「ご飯、作ってくれてありがとう」
席を立ち、彼女のそばにより、抱きしめる。小さくて、小柄な彼女はすっぽりと腕に収まった。
お気に入りだと、自慢するほど気に入っていたはずの白いブラウスは、脂が跳ね、染みになって汚れている。着替えないで作るほど、急いでた?
「どう致しまして。もう二度と作らない」
「そんなこと言わないで、また作ってよ」
腕の中から見上げる彼女にそっと唇を重ねる。少し開いた口唇に導かれるように、舌を差し込み、絡め合う。
「ん……はぁ…んっ…んん… はぁ……」
快活なメロディーと共に、お風呂の湧き上がりを知らせる音がリビングに鳴り響く。
唾液が混じり合い、甘い吐息を漏らす彼女の耳には、そんな音楽、もう聞こえやしない。
さぁ、今度は君が可愛い鳴き声を奏でる番だよ。
彼女の肩に手をかけ、優しく床へ押し倒した。


