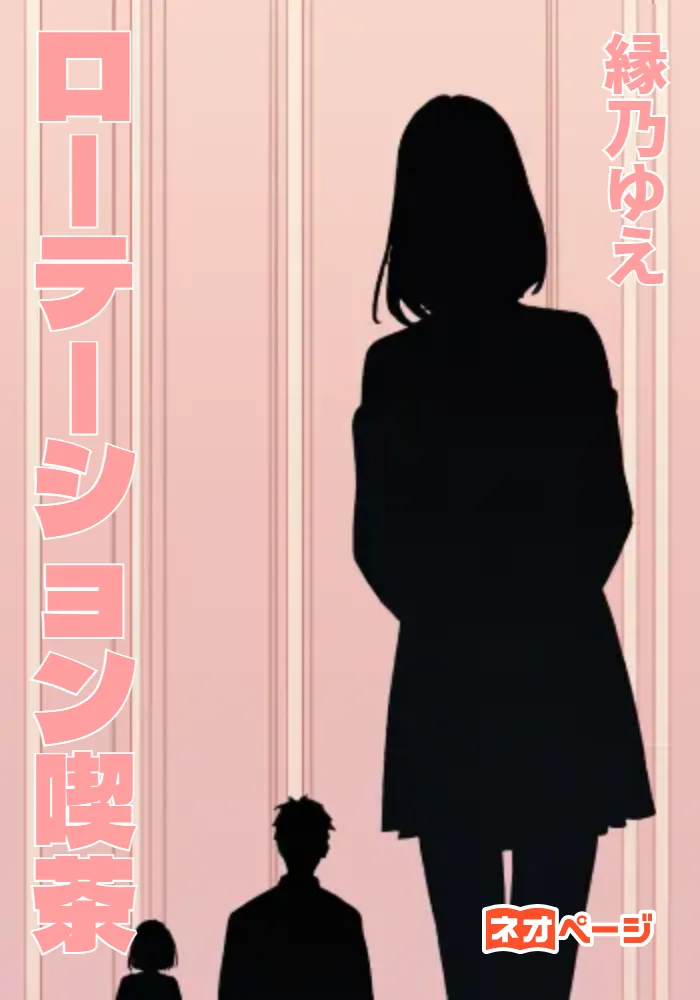
公開日
完結済
紅見喫茶店で働くアルバイト達が自分達のラジオで店内を盛り上げろと店長に言われて、その喫茶店の常連客達がまたそのラジオのリスナーになり紅見喫茶店を盛り上げていく物語。
※小説家になろうに重複投稿しています。
きっかけ、始動
原因はその喫茶店が普通の喫茶店だからだ。日替わりランチもそこそこ美味しいし、店員も至って普通に働くパートのおばさんや高校生のアルバイトの子が多い。普通の常連客だっている。一人だけ少し変わった常連、
そんな普通の紅見喫茶店、店長はどうしたらこの『びーじーエンム』とか言うバックグラウンドミュージックが訳の分からない今時の音楽ではなくなるのか、そのおケネの問題も解決したいところだった。
カラッランと店の手動ドアが開くと鳴るようになっている音が鳴った。
「あ、川田さんいらっしゃい」
店長は開店か閉店間近にいつも甚兵衛でやって来てはお決まりの席に座る川田さんに言った。
もう店には店長と副店長とお客の川田さんしかいなかった。
川田さんはいつも店長の定位置の一番近くに座る。そして、店長のことを『マスター』と呼ぶ一人だった。
「マスター、コーヒーひとつね」
「はい」
と言ってコーヒーを出すそんな間柄な二人だった。
副店長もこの二人の間柄についてそんなに深くは知らないというか知らなくて良いと思う。
店長は副店長のことを『ふくちゃん』と呼ぶ。ちゃん付けなのは副店長が女だからであろう。
「あー、ふくちゃん、ついでに川田さんも聞いてくれる?」
「ついでかい」
川田さんにしては少し突っ込んだ発言だ。
「あの、ね……ふくちゃん、この音楽知ってる?」
店長は店で流れる音楽がどこにあるのか分からないが自分の一番近くの頭上を適当に人差し指でふらふら指しながら言った。
「まあ、一応は」
「川田さんは!」
「うーん、どっかでね」
そんな二人の回答に店長は、
「俺は一度もっ、聞いたことねぇヨ!」
と叫びそうな感じで言った。
「そうなの?」
川田さんはコーヒーをミルクでぐるぐるしたいな~と思いながら皿に付いてるはずの小さいスプーンをちょっと探してみた。
それを見ていた副店長は、
「そこにあるじゃないですか」
と店長の話をぶっちゃけどうでも良いと思っていた。
そんな二人の態度に店長は、
「で、提案です!」
と二人の注目を集めるためにも右手を上げて言った。
「このびーじーエンムをバイトの子を使った何かに変えようと思いマス!」
二人はキョトンとした。
「ああ、『ビージーエム』ね」
「ああ」
副店長は川田さんの言い直しでやっと店長の言った言葉を理解した。
「おケネ掛かるの嫌じゃない?」
店長はそんな二人に向かって少し可愛くを意識して言ってみた。
「ああ、おケネ? ……お金か」
「ああ……」
「何、その下がり気味な態度」
店長は少し機嫌が悪くなったらしい。
「おじちゃんがそんなそっぽ向いたって全然って感じだけどねー」
「そうですね、でも、まあ、店長がそうしたいって言うならそうしても良いんじゃないんですか?」
「そうっだねぇ、何かねぇ……ラジオとかどうよ?」
「良いですね、ラジオ。この店内限定だけの店内ラジオとか」
川田さんの案に賛同しておこうと副店長は一瞬で判断した。
「お! じゃあ、その案でいくかな。もちろん、そのラジオを一から作るのはバイトの子で決まりだな」
「自分ではやらないんですか?」
「おらは聞いてるのとか裏方が好きだから」
「そうねぇ、俺も聞いてるほうが好きだな」
川田さんのコーヒーがもうないのを見ると店長は注ぎ足した。
「でしょ、だよね。という訳でふくちゃんは今まで通りでよろしくね」
「はい」
ラジオじゃなくてよかったぁ……なんて思った事が二人にバレないようにして言った。
「という訳でびーじーエンムの代わりに『店内ラジオ』というのをやる事になったので今、この話を聞いて辞めたいと思ったバイトの奴は今すぐ辞めてくれて構わない」
そんな事を言わなければ良いのにとあの数日後に緊急集会を開いた店長の横に立っていた副店長は思った。
パートのおばちゃんは自分に関係ない事で良かったと思っていた。
予想通り大半以上のバイトの子が辞めた。
残ったのはアシスタント希望と勝手に店長に言われた高三の少女、きのみと時々、週二から三になったばかりの大学生、雑用係と言われる事を望んでいるんだなと皆から思われているのを本人は知らないでいる青年、あとはメインをやる事になった二十歳以上のバイト数名だった。
「で、店長、その『店内ラジオ』ってどうやってやるんですか?」
「知らない」
質問したバイト歴五年の
「そういうのしっかり考えてからにして欲しいですよね、やっぱり」
きのみはラジオ反対派らしいが何故か残ることになってしまったのに少し、落ち着いていた。ラジオやってみたいって思っていたかもしれない。
「そういうのはほら、調べれば何とかなるもんだよ」
「で、誰がそれを調べてやるんですか?」
ほのかと同じくバイト歴五年の
「ほら、だから、君がいるじゃない?」
「え? オレですか?」
「そう。オレだよ、オレ」
ああ。と皆が納得した。
「はい、じゃ、君よろしくね!」
肩をポンと叩かれた皆の雑用係、
以後、ラジオの描写は全くなくなるがそれらしさを出す事ができるというならばメイン達と時々、登場するアシスタントのきのみのトーク、そして、リスナーと呼ぶべきお客さんのお便りが主になるのだろう。
「何、書いてんですか? 店長」
「ん?」
それまでカチカチとキーボードを叩いていた店長は副店長に言われて手を止めた。
「内緒と言いたいところだけどね、教えちゃうね」
「いや、じゃ、聞きません」
副店長はしまったという顔を露にしないように注意した。
「このブログを読めばなんと苦労した喫茶店! ということで客もウほほっほ~なわけよ」
「そうですか、でも、確かに徐々にお客さんの数増えてるかもしれませんね。あの子達の頑張りで」
うん、うんと頷く店長はやはりおじちゃんでしかなかった。
*
「はー、やんなっちゃう」
「ああ、今日、ほのかの当番だっけ」
「そう。なんで私達が自分で考え、やんなきゃいけないわけ? 初回なんてあれ、放送して良いの? レベルだよ? まあ、私達は素人だしさ、しょうがないけどさ、誰が店内ラジオなんて聞くのよ。ビージーエムは別に聞かなくても良いから流してるわけでしょ! 一人で来るお客さん用でしょ。だったら、店長が一人でマイク持っておじさんビージーエムでも何でもやれば良いのよ。私達はただのバイト、だから、店長には逆らえないってだけで……ああ、やっぱ、あの時、辞めればよかった」
がっくしと言いたそうなほのかは同じバイト歴仲間の柚野に愚痴った。
「でも、辞めなかったのはそれなりの理由があったからでしょ」
「そ。なんだよね、ここ、時給だけは良いからさ。辞めたくても辞めれないってか最近、客数増えてきてまた、時給上がったからさ、居続けちゃうんだよねー」
「それが店長の策略だったりして」
ほのかと柚野ときのみが女子更衣室でバイト服といっても自前のエプロンと三角巾に着替えるだけだが着替えていると女子更衣室の見えない防止策水色カーテンの向こうのドアがガチっと開いた。
その時、一瞬、皆身構えたが、
「おはようございます」
という女性の声に安堵した。
柚野は一息してからドアを閉める
「なんだ、遅いぞ、たい」
「すみません、ちょっと歩いてきたもんで」
そう言って入って来たのはバイト歴二年の田井しのぶだった。彼女は数日前からダイエットを始めたらしい。が、食べ物大好き人間なのでその効果はあまり現れていない。
「私もダイエット始めようかな?」
「きのみはそのままで良いんだよ」
ほのかと柚野は同時に言った。
*
「はい、始まりました! 『ほのかのホッとラジオ』今日はここ、紅見喫茶にいらっしゃって下さったお客さんことリスナーさんのお便りをご紹介したいと思います。えっと」
ほのかは読むお便りを探した。
「あ、ラジオネームは名無しさんから。『今日のコーヒーも上手いです』ありがとうございます。そうなんですよ、この喫茶店のコーヒーインスタントじゃないんですよ。はい、次のお便りは」
うん、うんとレジで立っている店長は頷くしかできないのだろうかと副店長は接客しながら思った。
「……ほのかさんもなんか名前変えれば良い? じゃ、『なのか』にします。今日から『ほのかのホッとラジオ』は『なのかのホッとラジオ』になるのでそのつもりで」
それは不味いと思った店長はほのかに向けて手でバツの字を作りながら何度もダメを強調した。
「あ。店長が反対しているのでやっぱりほのかのままでいきますね」
店長が決めた事には誰も逆らえない。というか逆らわない。そうしないと店長が厄介だからだ。それが紅見喫茶店長以外のルールだった。
「はい、ということで今回も無事に終える事が出来ました。引き続き、紅見喫茶でお寛ぎ下さい。お相手はほのかでした」
という風にメイン達三人は一日おきのローテーションを組んで一人、十五分から三十分以内での持ち時間で店内ラジオを回していた。
それが後に『ローテーション喫茶』と呼ばれるようになる由来だった。
ほのかは本名のまま『癒やし』を目指してやることになった。
他、二人もそれぞれ自分で考えた案で頑張ることになった。
柚野はユズノと名乗り、紅見駅周辺のイベント情報等をお知らせするラジオをやり、田井はのぶ子と名乗り、『食』に関してのラジオをやった。
この店内ラジオには放送方法が二種類ある。
一つは店の休み等を利用してメイン達が事前に収録したものをビージーエム代わりに流す方法だ。これは生放送以外の時に店内に流すのが目的だ。このビージーエムがなければ生放送以外はとても静かなものだと店長が判断した為だ。
もう一つが生放送だ。
この店内生放送は最も客入りが悪いと思われる頃と言う店長の提案で当初は夕方の四時くらいだったのだがそれでは仕事の関係上、無理だという多数の常連客の意見を反映し、仕事終わりの方も聞くことができるであろう午後六時半になった。
紅見喫茶店が休日とする水曜日以外はほぼ毎日生放送することになっている。
もちろん、メイン達も自分の出番がない時はしっかりと本業のバイトをやる事になっている。
「お待たせしました。アイスコーヒーです」
「あ、ありがとう。あの、その、そのエプロンってあの、ユズノさんの何ですか?」
「そういうのは違う所でやって下さい」
それを見ていたほのかはもっと良い人が来れば良いのにと思った。
だが、そうは思ってもどうする事も出来ない。何故ならば、お客さんを『選ぶ』というのが働く者には出来ないからだ。
こうしたメイン達の気持ちを自身も女性として察知した副店長の
「店長、一般のお客様の方に迷惑を掛けない為にもここは一つ、店内ラジオを求めてやって来るお客様の方には何か特別な事をした方が良いんじゃないでしょうか」
「うーん、もっと具体的に言ってみてよ」
よし、店長が食い付いてきた! と千色は心の中で軽くガッツポーズをしたが、店長の言う具体的案等一つも考えていなかった。こうなったら適当な事でも出しておく事にした。
「具体的にはですね、つまり……会員制、メンバーカードか何かを発行して優先的にその方は店内ラジオで読まれるとかですかね」
苦し紛れの案だ、反論されても仕方ないと千色は店長の返答を待った。
「ふん、会員制ね……まあ、店内ラジオに投稿するリスナーさんなんてそんなにいないだろうからね。やっても良いんじゃない?」
「え?」
予想外の展開だ。千色は店長の考えを読むべきかどうか考えた。
「あの、店長? でも、どうやってその会員制をやって行くつもりなんですか」
「ああ、まあ、店内の目立つ何処かにでも『店内ラジオ会員制始めました。これでリスナーのあなたももうラジオネームに困りません』ってな感じでポスター作って貼っとけば良いよ」
自ら出した適当案に店長の思い付き案をプラスされた。
(なんと適当な! こんなんで良いのかな、本当に)
千色はこれからはもっと先の事までちゃんと考えてから店長に話そうと学んだのであった。
それから一週間が過ぎ、店長の呼び掛けで店内ラジオのメイン達ときのみ、迫平が休日の紅見喫茶店に集められた。
「はい、今日はせっかくのお休みの日ですがふくちゃんの提案により明日から『会員制』を始める事になりました! ということで今日はそのポスターを一人、一枚、皆に作ってもらいたいと思います」
「えー」
店長のその話に集められた皆は文句の代わりに嫌そうな声を出した。
「ここは学校じゃないんだ! 『えー』は学生の特権だ」
その店長の言葉に迫平はおずおずと手を上げた。
「あのー、それじゃ、オレその特権ってやつ使っても大丈夫なんすか?」
「ダメに決まってるだろ。迫平はもう大学生なんだぞ。もう、大人じゃないか、それに」
店長の話がまだ続きそうなところで柚野はきっぱりと言った。
「もう、そんなくだらないこと言い合ってる暇があったらさっさとポスター書いちゃいましょうよ」
「そうですよねーってなんかその店長の話からすると『会員制』って新メニューみたいな感じですよね」
そう言うきのみは何色で書こうかなと少しわくわくなようだ。
ほのかは無言ですらすらと書いている。
田井も何とか書いてるようだ。
迫平もポスターを書こうとしたところ、店長に止められた。
「迫平はポスター作ってもらうために呼んだんじゃなくて出来たのを貼ってもらうために呼んだんだ。ほら、迫平の方が身長あるから脚立使わなくて良いじゃん」
何それ! 迫平はそんな事でオレは呼ばれたのかと落ち込んだがそれでも休日出勤の手当てが出るので良いかと思う事にした。
その心持ちが皆から雑用係でも良いんだと思われる要因になっていると気付かない迫平である。
そのポスター効果もあってか順調に店内ラジオは会員数を増やしていったのであった。
「よし、これからもジャンジャンやっていきましょ!」
店長だけどうしてこんなにテンション高いの? と紅見喫茶店長以外の店員達はまだ一滴も酒を飲んでいない店長に疑問を持ったがそれはいつものことなので始まったばかりの今年の忘年会を楽しもうと思うのであった。


