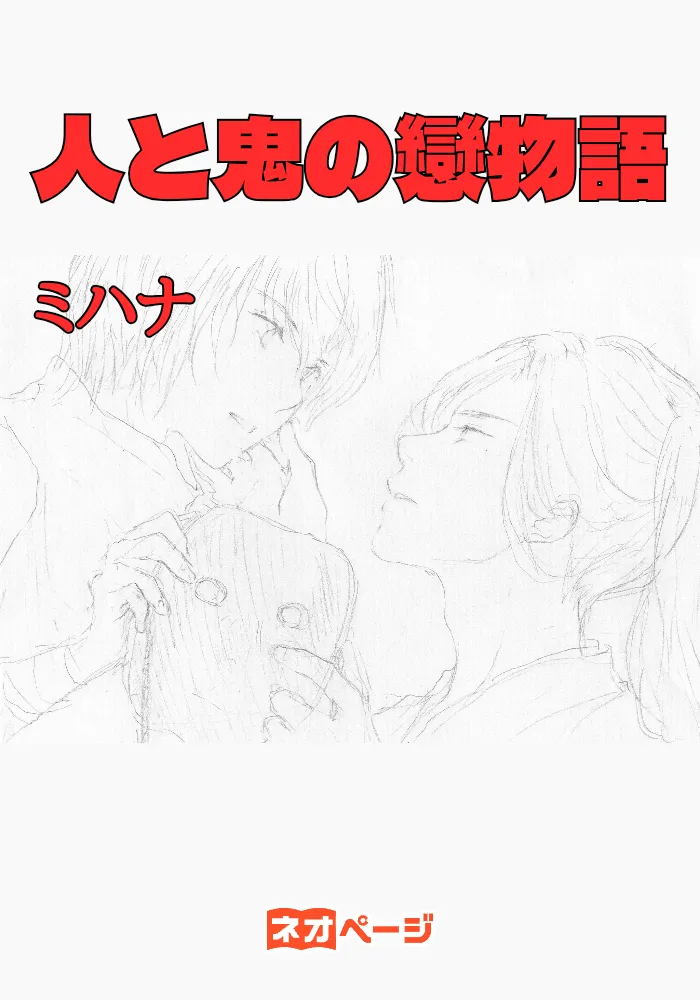
公開日
連載中
それは昔昔、そのまた昔。
人が神や人ならざるモノを信じていた刻(とき)の語らざれざる物語り―――。
とある山には〔鬼〕が棲むとされていました。
その山は人里離れた村の外れに
いつからか山の入口には祠が建てられ村人は山を祀り〔鬼〕が降りてくる事がないよう供物を捧げていました。
村人は農作に勤しみ時折村に降りてきた狐や兎などを狩って暮らしていたのでした。
ある日のこと。
祠の供物の中にあった果物をかじりながら〔鬼〕が歩いていると沢に何かが引っ掛かっているのが見えました。光沢のある何かが陽に反射した川面に写りこみゆらゆらと揺れています。
興味を覚えた〔鬼〕が沢に降り近寄って見てみるとそれは人の子でした。光っていたのは艶のある濡れ羽色の髪で見たところ子どもは気を失っているだけのようでした。
このまま放って置けば鳥や獣達の獲物にされてしまいます。
〔鬼〕はその子どもを助ける事に決めました。気まぐれ心を興したのです。
沢から引っ張りだし自分の塒(ねぐら)に連れてかえり、世話をしました。
足も怪我していたので薬草を採って煎じ、三つの朝と三つの夜を迎えましたが子どもはまだ起きません。
もう手遅れだったのかと肩を落としつつ迎えた四つ目の朝にようやく子どもは目覚めました。
「……ここは…」
子どもは体を起こして辺りを見回し、この場所が広い奥まった洞穴の中であり火が焚かれ明るさが辺りを照らしている事に気付きます。洞穴は深いのか奥までは見通せませんが。
傍らには様々な木の実や竹をくり貫いた水入れが置いてあり誰かが看てくれていたのだとも分かりました。
空腹を覚え赤い実を一つ摘まみ水を少し飲むと山から足を滑らせて落ち、川に呑み込まれたことまで思い出し身を震わせます。
助かったとはいえ子どもは死の淵を垣間見たのですから当然だと言えるでしょう。
その時に洞穴の入口に人影が見えました。
咄嗟に身を低くし、武士の子どもは拠り所であった短刀を探しますが滑落した時に落としたようでありません、仕方無しに
「おまえは誰だ。」
「ぼくは〔鬼〕。君を沢から引っ張りここにはこんだ」
姿を見せた〔鬼〕と名乗るものは子どもよりもいくらか長い
ですがよく見ると〔鬼〕も子どものようです。
小さな手が洞穴の奥を指さします。
「君のものはそこにあるよ。
お山の入口までおくるからついてきて」
言うなり身を反転させて立ち去ろうとする〔鬼〕を子どもが荷物を掴んで追い掛けますと少し下ったところで見つけました。
追い付く前にはまた下りていきますが子どもがもたついていると辛抱強く立ち止まっている為見失うことはありませんでした。
山を半ばまで降り、先が見通せる岩場までくると〔鬼〕は振り返り指を下に向けます。
「ここ降りたら祠につく」
「…っはあ…助かった。ありがとう。」
急な坂と獣道で子どもの息は絶え絶えでしたが送ってもらったことや助けてもらったことへの感謝は忘れない律儀な子どもでした。
言われた言葉に〔鬼〕は首を傾げます。村人から忌み嫌われる〔鬼〕は感謝など一度も言われた事がありませんでしたので何故子どもがそのように言ったのかも判らなかったのです。
「君はぼくが言ったことを信じるの?ぼくは〔鬼〕なんだよ?こわくないの?」
「怖くない。おまえはおれを助けてくれ、ここまで連れてきてくれただろう。恩人だ。
それに鬼には角がある。おまえにはない。」
子どもは子どもなりに絵草紙などで鬼を知っていました。武士の子どもなれども少しは学があったのです。角がないなら鬼ではないと言い切った子どもに〔鬼〕は驚き仮面の下で目を見張りました。
「………そんな風にいうのは君がはじめてだ。へんな子どもだ」
「おまえも子どもだろう。」
「ぼくは子どもじゃない、〔鬼〕だから。〔鬼〕には年なんてないんだよ」
そう笑いながら嘯く〔鬼〕に子どもは唇を鶫つぐんでしまいます。どうやら子どもは口がよく回る方ではないみたいでした。
話が終わったと思ったのか〔鬼〕は身を反すと来た道を登ろうとするので子どもは引き留めます。
子どもの周りは大人や年の離れた兄ばかりでしたので同じ年頃に見える〔鬼〕とまた会いたかったのでした。
「また次に会えるか。話がしたい。」
次を望む子どもに〔鬼〕は呆れながらもまた気まぐれ心で右手首に巻き付いていたものを子どもの左手首に巻いてやります。
それは蔓や色とりどりの糸で細く編まれた編み紐でした。
「これは結びの紐。切らさずに巻いていれば、いつか会えるかもね。
じゃあね、可笑しな子」
〔鬼〕はもう振り返る事なく登っていきました。子どもは結ばれた編み紐を指で名残り惜しく辿っていましたが、やがて祠へと下りていったのでした。
それから子どもは隙を見ては山の入口の祠に顔を出すようになりました。結びの紐は狐狸らの拐かしやたぶらかしを避ける目印にもなったのです。
子ども達は何度か逢瀬を楽しみ山で遊んだりしました。行けば必ずしも会えるわけでもなく〔鬼〕が出て来てくれなかったりと空振りもありましたが、それでも交遊は深まっていきました。
いつまでも〔鬼〕の仮面は外されないままでしたが子どもは無理に暴くことはしませんでした。
そして子ども達が健やかに成長し背も伸び青年と呼べる年月になった頃、起こるべくした別離が彼らを襲ったのです。
武士の青年は大人の仲間入りをし、仕える当主に仕えていました。青年の家系は代々連面と続く武士の家系で当主である一族の流れを継ぐ分家でありました。
その現当主が床に伏せ、次期当主となった男が我が物顔で我が儘放題になったのです。
年貢の取り立てを一月も早め相当量にならなければ村人を罰っするという形で器量が良い娘や妻なども男に取られていきました。
村人達は男に憤慨しましたが一揆を起こす前から企ては潰されていき、成すすべがありません。
そのような刻でした。
男が山の入口の祠に気付き、供物が捧げられているのを知ったのは。
男は迷信や呪いや神、または人ならざるモノも妖怪の存在も信じておらずあらゆる意味で豪気な男でありました。
男は「山を焼き、何かが居れば一つ残らず討伐せよ」と命を下したのです。
これを聞いた青年はなんとしてもこの事を〔鬼〕や山にいるモノ達に伝えねばと思いましたが、こう物事が差し迫った刻程忙しくなり中々抜け出してはいけず歯痒くもどかしい想いを抱えておりました。
実は青年が人ならざるモノと通じているのを知った血の繋がらない兄達の画策によるものだったのです。
年の離れた血縁のない兄達は若くも武芸に秀でた青年を疎んでいたのでした。
一方、お山の方でも動きがありました。
斥候役の烏天狗達が一部の村の状況を伝聞してきたのです。
彼らが見聞きしてきた現状の報告を受け、お山のモノ達はここを離れる決断を下しました
。
〔鬼〕も人々の心が読める力を持っていた為、烏天狗の伝聞より先に内容に気付いていましたが一つだけ立ち去り難い心残りを抱いていました。
仲良くなった青年と最期に一度だけ会話を交わしたかったのです。
〔鬼〕は人が嫌いでした。ですが自らが助け仲良くなった青年だけは好きでした。
〔鬼〕と知っても恐れず真っ向から己の意思を貫く青年はとても眩しく写ったのです。
人から嫌われ、それを受け入れていた自分が好きになった唯一の人。
もう昔の自分には戻れないのだと憎々しげに笑いながらも〔鬼〕は一人涙しました。
「やっぱり、人とは一緒にはいられないんだね。…………好きになんかならなきゃ良かった………っ!
できれば最期に一回だけでも逢いたいよ……」
捨てられていた〔鬼〕を拾いあげ育てた烏天狗達は恋心を抱いた〔鬼〕を心配そうに見つめていました。
そして最後の機会を与えようと一羽の烏天狗が飛び立っていきました。
武士の青年に会いにいく為に。
一日を半刻ほど過ぎ夜半に掛かるかという黄昏時、青年が仕える城内の庭先に一羽の烏が飛んできました。烏天狗が烏に化けた姿です。
城内は騒然とした騒ぎになりました。烏は死の鳥として昔から縁起が悪いものとされており直ぐに捕らえよ弓を射てと口々に言うも誰もが近寄りたくありませんので追い立てるだけでした。
死は誰しも皆恐ろしいのです。
ただ青年は違いました。
お山のモノを知っている青年は直ぐに烏天狗だと気付き、「自らが捕まえ処分致します。」と言えば反論はありませんでした。
城の裏手は小さな林があります。
そこで烏を離してやると烏は灰白色の髪を跳ねさせた烏天狗の姿に戻り「えらい目にあった」と服の衿を正し、青年は山が焼かれることと討伐隊が組まれていることを話しますが烏天狗に話を途中で止められてしまいました。
「若坊は〔鬼〕の昔を聞いてないよな?全部話してやるから聞いたら自らどうしたいか判断つけろ」
前置きをして烏天狗は秘められた〔鬼〕の秘密を語りだしました。
「あいつは山に捨てられていたんだ、赤子で臍の緒がついたまんまな。だからあいつには親がいた記憶はない。俺らの仲間が拾って、長が決めたんだ。
『見過ごせねえから育てる』ってな。
ただ俺らは天狗だ。だからか異様に成長が遅くて心配してたんだが若坊との交流で刺激になったみたいで大きくなったんだ。
ありがとうな」
一度言葉を切り、烏天狗は目の前の青年を眺めます。衝撃に切れ長の目の中の瞳が大きさを増して色が深まり整った面立ちが青年より子どもに見えました。
青年と言えども人としても年若いため動揺や衝撃、困惑が手に取るように分かりやすく苦笑しながら〔鬼〕が子どもの刻に言っていた言葉を思い出しました。
皆から子どもは若い坊と呼ばれているのだと
くすくすと笑っていて。
『若坊はよく顔に出やすいから好きだよ。この力をつかわなくても傍にいられるの』
仲間達と育てた〔あのこ〕が笑顔でいられる先々に想いを馳せ、全てを語った後への青年の判断に委ねました。
青年は〔鬼〕は名前ではないから烏天狗達がつけてくれたのだと言っていた呼び名だけは教わっていましたので烏天狗に尋ねます。
「さとりは食い扶持がないから捨てられたのか。」
「いや…………あいつは若坊も気づいてるだろうが人なんだけどな、人が持たない神通力を持っていたんだ。
心が読めるんだよ。
村人から鬼だの化け物だの言われて忌み嫌われてな、石や水を掛けられる前に心を読んで逃げたりしてたな。
あいつも悟いやつで自分は〔鬼〕なんだって自ら名乗り始めて。同じ人だと思いたくなかったんだろうな………。
〔鬼〕じゃあんまりだろ、呼び難いし。だからそうゆう妖怪がいて、そいつと似てるからさとりの呼び名をつけたんだ。
ただ、あいつは自らを,さとり,とは言わないがな。
…………お山が燃やされると知った刻にあいつを村人の中に戻そうと思ったんだけどな。
人の営みの中にあいつの幸せはないだろう。
俺達は仲間だ。情がある仲間は見捨てない」
「だからあいつを連れて山を離れる。もう逢うこともなくなるぞ。明晩だ。若坊、どうしたいかは自ら決めろ。
ただ、あいつは逢いたがってた」
覚悟が出来たら山の祠にくるようにと言い含め、烏天狗は羽を大きく広げ沈む陽の中に飛び立っていきました。
残された若坊と呼ばれた青年は〔鬼〕が抱える昔の話と明晩にはお別れをしなくてはならないことで悩み、心が千々に乱れます。
夜がきましたが悩みに悩んで目がさえてしまい、手慰みにと筆を取り様々に書き付けていきました。
〔鬼〕のこと。
出逢って遊んだ日々のこと。
烏天狗が言った言葉。
自らのこと。
そして書き付けた紙を並べまた悩み、筆をもう一度取って育ての親に宛てて文を綴りました。
青年には血の繋がらない兄達がいます。
実は青年は父である前三代当主が身分の低い下女に手をつけ孕ませてしまい、城から追放された下女が生をかけて産み落としましたが産後に高熱を患い命を落としたために妾の子扱いをされていました。
前三代当主は本妻がいましたが子宝に恵まれず、何人もの妾を持ちその女達に産ませたので兄達だと言われて引き合わされましたが青年と血の繋がりはありませんでした。
その上、青年は妾でもない下女へのお手付きで産まれたので身分でいえば誰よりも下でありました。
兄達は当主への道が開かれていますが武芸にいくら秀でようとも青年には出世の道は元よりないのです。
それでも『仕えて構わない』と仰られたのが既に床に伏せてしまわれた御方だったのです。ですから誠から忠誠を誓う御方がこの世を去られた時点で青年にはいくら次期当主とはいえ傲慢の限りを尽くす男に従事するのは忍耐強くとて限界がありました………。
夜半を悩んで過ごし、寝ずに朝を迎えましたがまだ気持ちは定まりません。
明晩、つまりは朝になってしまったので上がった陽が落ちるまで。
逢いにいきたいのですが最期だと言われますと尻込みをしてしまうのです。本当に青年は心も若い青年でした。
烏天狗の言うように村人として身柄を引き取っても青年には護りきるすべも地位もありません。それでも青年に〔鬼〕を諦める気はなぜか露ほども起きません。
どうしたらいいのか。
それだけを考えて一日過ごしました。
心ここに在らずな体でいる青年を見て周りは「死の鳥を捕まえたからだ。心がさらわれてしまった」と騒ぎ、ついには部屋へ戻って謹慎を言い渡されてしまいました。
ぼんやりした姿で部屋に戻る青年は幽鬼にとり憑かれたように見え、皆はたいそう怖がりました。
そして、約束の一刻前。
青年は育ての親に宛てた文以外の書き付けたものを全て火にくべ、先代当主に賜って寝る刻以外は腰から外したことのない刀を抜き、刀置きに掛けてから屋敷を後にしました。
決意は固く、振り向くことはありません。
ただ一言「ありがとう御座いました」とその場で頭を深く下げて去っていくのでした。
お山の祠に着き、青年は近くの手頃な岩に腰を据え〔鬼〕を待ちます。
陽は傾きかけてはいますがまだ宵闇は訪れません。青年はそのまま想い人がくるまで待ち続けました。
陽が大分陰り辺りに闇が漂い始めた頃、ふいに梢の木々が鳴りを潜め
「いい夜だね」
気づくと青年が腰かけた岩の反対側に、待ち人が対面しあう様に座っていました。
咄嗟に振り返ろうとしますが後ろから肩を捕まれてしまうと弱い力ですが振りほどけません。
「振り返らないで聞いて。
おれ達はこの夜を最後にこの山から消えるよ。祠はおれが山を下りて里に行けないようにまじないが掛かってるから山が燃えたら祠も壊してね。
若坊が気にすることはないよ、そもそも一つ所にいすぎた。
本当ならきみを助けたあの刻に棲みかをかえるべきだった」
「…さとりと逢えて、おれは良かった。逢う度に次が待ち遠しく思えて日々楽しかった。」
「おれも………若坊なら、人を信じてもいいかなって思えたよ。
だから、………っ」
肩を掴んでいた手が震えているのに気付き、青年は自らの左手を重ねました。
お互いの温もりには違いが無く、〔鬼〕は心が締め付けられ言葉になりません。
それでも、最後だからと震える唇を開いて告げます。
「………っ、おれは、若坊が好きになったんだ。はじめて人を戀しいと思ったんだよ…。
こんなこと言われても困るだけだよね、でもありがとうって、言いたかったんだ…っ」
うつむき肩に添えるだけになった手を掴んで青年が〔さとり〕を引き寄せ、仮面を繋いでいる紐を指を絡めて引っ張りました。
外れた仮面が地に落ちたことで〔さとり〕は慌てて離れようとしますが青年の腕の力は強く、抗おうとすればするほど青年の胸の中に抱き込まれてしまいます。
「!いや!外さないで……っおれ、人とちがうから、…みないで……」
顔を隠す手を青年が掴んで外すと、月明かりに照らされた〔鬼〕が涙を流している姿がはじめて暴かれました。
陽の色より鮮やかで緋より深く、艶やかに輝く髪。
髪を透かし涙で潤んだ目はどんな紅石よりも美しい輝石、その輝石から溢れる涙は透き通って白い頬から滑り落ちていきます。
人には持ち得ない色は神秘性を湛えて青年の前にありました。
青年はこれほどまでに美しいものを見たことがありませんでした。
魅射られるとはこうゆうことを言うのでしょう。
〔鬼〕は唇に触れた柔らかさに目を溢さんばかりに見開きました。
何をされているのか分からず動けずにいれば離れていく唇を追っている自分がいて〔鬼〕は白い頬を紅色に染め上げます。
間近に変化を備に見つめ、青年は柔らかく口の端を弛め「ようやく面の下が見えた」と顔を綻ばせ。
「………おれもさとりが戀しい。離れがたい。
さとりはおれが見たものでいっとう美しい。」
頬に触れもう一度唇を重ね、さきほどより少し長く接吻しました。
〔鬼〕は唇が離れた刻に囁くような声で呟きます。
「……やっぱり、きみは可笑しな子だね」
「もう子どもではないがな」
そうして二人でくすくす笑いあい、お互いを抱き締めました。
「…………もう、行かなくちゃ。若坊と逢えて嬉しかったよ」
名残り惜しく体を離し、立ち上がり繋がれた手をほどこうとする〔鬼〕の手を青年が掴みなおします。
困って佇む〔鬼〕に青年は自ら決めたことを伝えました。
「さとりが〔鬼〕と言い張るのなら、おれをさらえ。〔鬼〕は人を拐かしさらうものだろう。おれを連れてさとりは〔真の鬼〕になれ。ともに〔鬼〕になろう。」
これが悩んで悩みきった上に青年が出した答えでした。
青年には〔鬼〕を諦めきれません。
なら、一緒に〔鬼〕になってしまえばいいと。
ひきかえに〔人〕であることを捨てることになりますが青年なりにもう忠義は尽くしました。
青年は戀しい〔鬼〕(ひと)とともにいる先を選んだのでした。
〔鬼〕は青年に昔結んであげた結びの紐に唇を寄せ、泣きはらした紅石の目でにんまりと笑いました。
「じゃあ、〔鬼〕らしくさらってあげよう………悔やんでもおそいからね。ぜったい獲物は離さないから」
幸せそうな二人を木々や木陰から見ていた烏天狗達は皆で嬉しげに笑いあったのでした。
それから、この青年の姿をみたものは誰もいません。
これで語らざれざる昔話はおしまいです。
終わり


