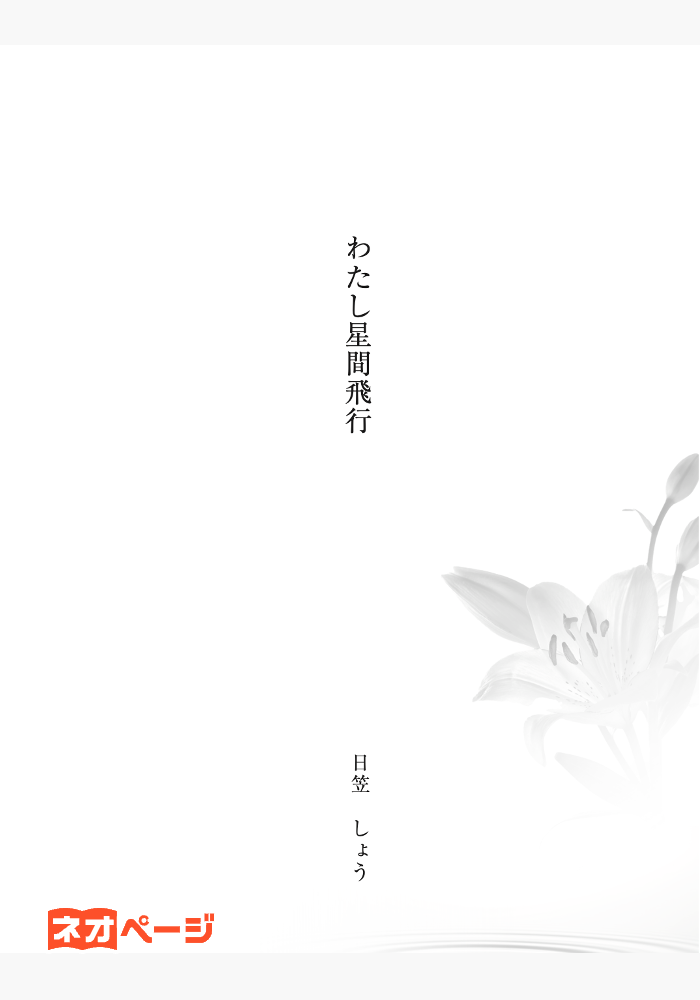
公開日
完結
「いやだよ」
かろん、とグラスの氷が鳴った。珈琲の冷たく澄んだ黒色にそっくりな瞳が、私を籠絡せんと見据えている。押し負ける気がしたので、顔を背けた。
「絶対にやらないよ」
「そう言わずにさ、ササッ」
私の前にあった珈琲を、詩音がさらに寄せてくる。賄賂のつもりか。
ちゃぷん、と水面が揺れる。深い深い黒。星浮かぶ宇宙を思わせる、潤んで煌めく2つの目。不安そうな、だけども私を信頼しきっているこの目が好きで、最初のお願いを必ず断っていた時期がある。すぐに不毛と気づいて辞めたが。
私を囲む黒色を少しでも減らしたくて、ミルクを注いだ。
「ブラック派じゃなかったっけ?」
「うるさいな」
「どうしてもお願いできない?」
詩音が居住まいを正す。
「七花じゃなきゃ、いやなの」
あーもう。ダメだよ! あーダメ! そんな顔をされたらもうおしまい! 試合終了! どれだけ堅牢に守りを固めたって、見つめられたら七花城は呆気なく落ちるのみなのです。
9年前の私、つまり19歳の私が頭の中で騒ぎ、勝手にしょぼくれている。
わかるよ、私。
詩音は氷の彫刻なんて呼ばれていたこともあったね。どこまでも静謐で、冷たいほどに綺麗で、あっという間に壊れそうなくらい儚げで。
でもそれは、遠くから見ているだけの人たちの感想だ。
私は知っている。本当の詩音は氷なんて似合わない、無垢で無鉄砲で無遠慮で火の玉な生き方をする。子どものように、今その瞬間を楽しむことに全力を捧げる。そのときの詩音は格好良くて、可愛くて、愛おしいのだ。
私だけが、知っていた、はずだった。
「……もう何年も触ってないんだよ。指だってふにふにだし」
「ほんとうに?」
「さわるなっ」詩音が伸ばした手を軽く払う。「ほら、仕事も家のこともあるから、練習する時間も取れないかも」
「2カ月あるんだよ、いけるいける」
「結婚式の余興なんだから、もっと上手い人とか……というか、旦那さん私とパート被ってるじゃん。旦那とやりなよ」
「二人で練習したら誰が育児するのさ」
「……曲だって簡単なのしか無理だよ」
詩音が悪戯っぽく笑う。
「その悩みはすでに傾いている人のだよ、七花」
「〜〜〜〜っ!」
「卒業以来、6年ぶりの再結成だ。ライブしようよ、ね?」
ごめん、19歳の私。何も変わってなかった。きらきら輝いていたあのときみたいに、私はまた籠絡されたのだ。
失恋相手の結婚式の余興のライブなんて、字面だけでも地獄なのに。
無事、詩音の頼みを断りきれなかった私はしぶしぶ話を進めることにした。
「曲は決まってるの?」
「まあ、なんとなくは」
「結婚式なんだから無難に——」
「bad dayとか」
「メロディはそれっぽいけど、意味知ってる?」
「School Food Punishumentとヲワカがいいかな」
「却下」
ストローに数滴分の珈琲を溜めて、飲み口を指で塞ぐ。そのままストローを水面から離すと、圧力で中に液体が留まる。それをストローの空袋に垂らしてしわしわ縮んでいくのを見るのが好きだ。
「まだやってるんだ、その癖」
「スリーピース以外組まないから」
「なんで私とやるときだけ3人にこだわるのさ」
なんで、って。
唇を噛みながら、詩音を睨んだ。当の本人はキョトンとしている。
言ったってどうせ、わからないだろうに。
「意地」とだけ口にした。
「そうか……意地かぁ……意地ならまぁ、仕方ないかぁ」詩音が突っ伏す。意地悪じゃないよね? と上目遣いしてくるのを、見ないふりする。
「じゃあ、わかった。3人ね」
「ドラムは……羽海野?」
「もう声かけた。『七花がいるなら、この3人だね』って言ってたよ」
「わかってるじゃない」
「最後くらい大所帯でやりたかったぁ」
「私以外とやって」
ちりっ、と耳の中がひりついた。最後。それはそうだ。なんならこれは、神様がくれたボーナスステージだ。
あの日、これが最後になるねと3人で語らったときから6年越しに、またあの空間に立てる。時間が止まり、あらゆる光がこちらに飛び込んできて、私たちが世界の真ん中にいる、この世のすべて。替えの効かない、唯一無二の瞬間を味わえる。
あなたと——。
二度と交わることのない分かれ道の、まさに分岐点での出来事になるとしても、そこから先を独りで歩くためのお供くらいはあってもいいだろう。
大切な人の旅立ちを目の当たりにするのは嫌だが、その場にいないのも絶対に嫌だ。せめて思い出だけは、連れ帰らせてもらう。
「やろう。やるよ、バンド」
そうこなくっちゃ、と詩音が指を鳴らした。


