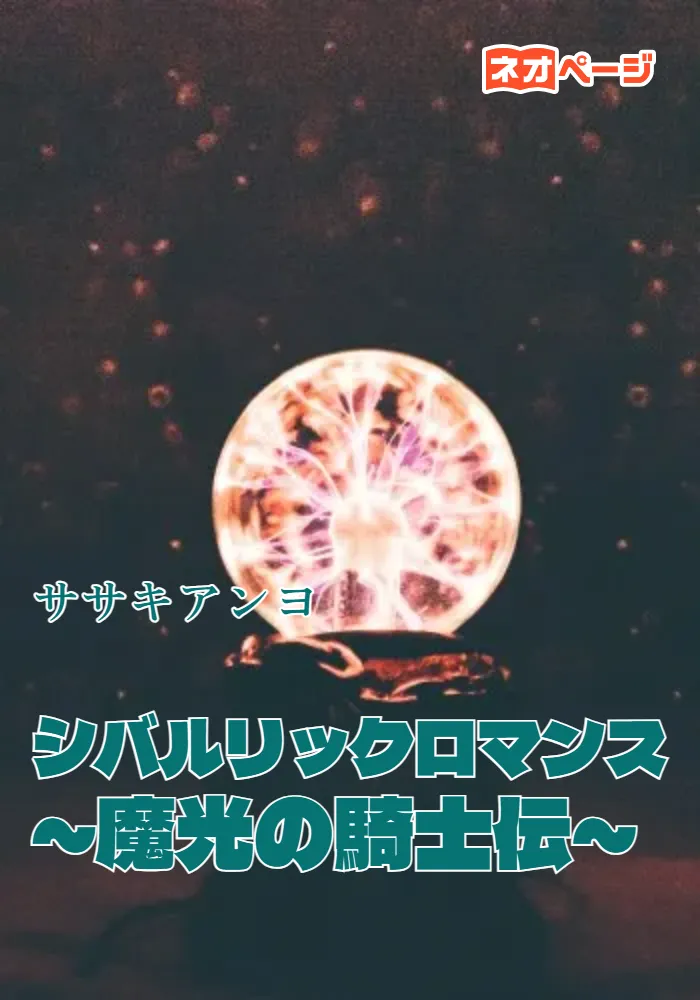
公開日
完結済
プロローグ その光は妄執に近く……
戦が終わったあとの始末と言えば、やることは決まっている。
夕暮れの陽射しが地平線を赤く染め上げる。黒く蠢動する肉塊が屍肉を啄みにやってきたカラスたちを逆に食い荒らす。
上官の判断で、自身の勇気で、部下の配慮で、自らを堕落せしめた騎士たちの成れの果て。ユグドラシルの尖兵どもを薙ぎ払い、コキュートスに勝利をもたらした功績者たち。彼らの活躍あって、女王アリアはこちらにとって有利な条件で和睦したという。
結局のところ、戦争の本分は殺し合うことではない。互いの血を流したあとに交わされる政治の応酬こそが国の行く末を決めるのだ。
(くだらない。ここにオレが命をかける理由は無い。ならば、オレの死に場所は天国戦争ではなかったということだ。ましてや、後始末如きで死んでなるものか)
筋肉を肥大させた紫色の巨腕が地面を抉り切り、昨日ともに焚き火を囲んで不味い糧食を食った仲間たちが弾け飛んでゆく。巧みにその攻撃を避けた黒髪の少年が剣を抜いた。
腐った汚泥のような瞳の少年ではあるが、その刃は磨き抜かれている。刃に光が灯り、その祝光は強く爆ぜて魔浄兵を容易く切り裂いてゆく。胸に大穴が空き、両腕が落ち、その頭蓋は光で消し飛び、辺りに響くような音と共に魔浄兵は崩れ落ちた。
ふと少年は自らに突き刺される視線に気付いて顔を上げる。共に戦ってきた騎士たちのものだ。今しがた潰えた仲間の命に対する慟哭と、傭兵風情が何故生き残っているのだという深い侮蔑。ここに仲間意識など皆無であった。戦友だと少なからず思っていたのは少年の方だけであったようだ。
(ちっ、オレはなんとお人好しなんだ)
少年は無銘の剣を納め、立ち去る。魔浄兵をすべて討伐すれば仕事は終わり。仕事が終われば金が貰える。金が貰えればとりあえず明日からは生きていける。……醜く生にしがみついたとて、もはや自分という存在に意味は無いのだと理解していながら。
それでも、彼は生き残ることを選んだのだった。
ソウル・ティカ・ルシフェル。
それが少年の名だ。コキュートス全土をその範囲に収めたとしても、非常に希少だと言える光属性を宿すルシフェル一族の
傭兵に身を落とした彼も、幼い頃は名高き武門の末裔として大いに自尊心を満たしていた。ソウルの父は、叔父は、祖父は、みな高名なる騎士であった。弱きを助け強きを挫く。コキュートスの護りを担う彼らの栄光はけして消えることは無い。
……7歳になるまで、ソウルは理解していなかった。栄光などという形無きモノがいかに脆く弱々しいモノであるかということを。
♦︎♦︎♦︎
夜。4体目の魔浄兵を討伐したときに負った左腕の怪我の
(戦争は終わった。つまり、オレは金を稼ぐ手段を失ったということだ。今回の報酬で1年は遊んで暮らせるだろう。だが、そのあとはどうすれば良い? しばらくは戦争など起きはしないだろう。コキュートスから出て、戦乱の絶えぬという|天ツ国《あまつくに》へ行くという手もあるが…………)
ソウルを取り巻く懐事情の解決策はいつだって変わらない。屋敷を手放せば良いだけだ。ルシフェル一族が保有する武器を金属に変えれば足しになる。荒れ果てているとは言え、この広大な屋敷はまとまった金になる。
だが、それだけは出来ない。
居ても立っても居られないとばかりにソウルは毛布を払う。不安に駆られて向かうのはいつもの場所だ。部屋から出て、階段を降りる。豪華なシャンデリアの下、この屋敷においては広間となる部分にそれらはあった。
永遠に凍てつく氷像。ジクジクと痛む腕を抑えながら、ソウルは変わり果てた父たちの氷像に縋り付く。如何なる炎を以てしても氷は溶けなかった。魔を打ち消す光の力でも氷は欠けなかった。何者の仕業でこうなったのか分からない。
この状態になった父を、叔父を、祖父を死んだと諦めることが出来ればどんなに良かっただろうか。だが、淡い光が氷像から漏れ出て灯りの無い広間を照らしていた。死体が凍っているのであれば、こんな現象は起きない。彼らは仮死状態になっているだけなのである。
「父上……オレは必ず、この氷を溶かしてみせる。そして誉れ高きルシフェル家を再興する。そのためならば、どんな苦労も厭わない。そう誓ったんだろうが……!」
立派な心意気だ。けれど、ソウルは解決策をいつまで経っても見つけることは出来なかった。
ルシフェル家の財を投じてコキュートスのあらゆる医師や魔術師に見てもらえば氷は溶ける。それは幼さゆえの見通しの甘さだったのだろうか? 後見人すらいない貴族の子から財を搾り取ろうとする汚い大人たちに隙を見せたのが運の尽きだったのだろうか?
何にせよ、事件から10年が経ち、いまのソウルには汚い大人すら近寄らない。傭兵業が無ければ硬くて不味いパンのひとつすら買えない有り様だ。無い袖は振れぬ。誇りで腹は膨れぬ。現実の厳しさに彼の精神は磨耗していた。つい死に場所を探してしまうほどに。
「父上。なぜ、オレをひとりにしたのですか」
そんな風に氷像を叩く彼の姿は、子供のように力無く愚かで、ひどく寂しいものであった。


