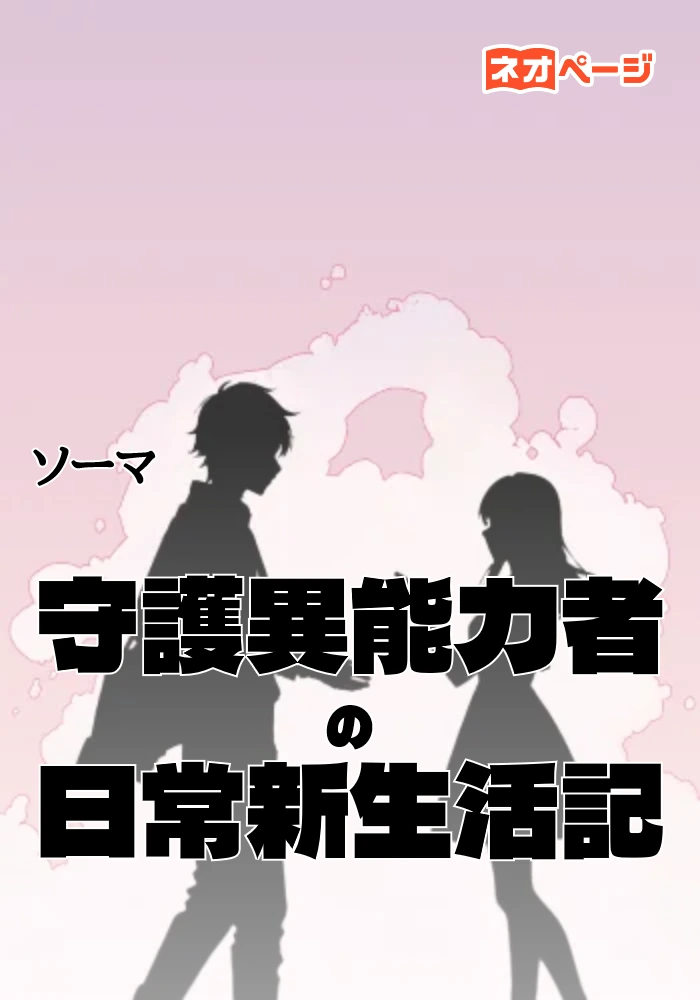
公開日
連載中
普通の人には無い、特殊な『力』を持つ高校生、土神修也。
その力のせいで今まで周りからは気味悪がられ、腫れ物のような扱いを受け続けてきた。
しかし両親の急な転勤により引越しを余儀なくされたことがきっかけで修也の生活は今までとはまるで正反対になる。
「敬遠されるよりは良いけど、これはこれでどうなのよ?俺は普通の生活が送りたいだけなのに!」
ちょっと普通ではない少年が送る笑いあり、シリアス(ちょっと)ありのゆるい日常(希望)生活ストーリー!
…………ゴトンゴトン…………ガタンゴトン…………
電車が定期的に揺れながら走っている。
電車内はほとんど客はいない。そんな電車のボックス席の隅に、彼はいた。
彼はじっと景色を見ている。しかし、景色は彼の頭の中には入っていなかった。
彼の頭の中にあったのは数日前に放たれた父親の言葉。
「はぁ……」
それを思い出し、彼はため息をつく。
「何でこうなったのかなぁ……?」
そう彼、
●
「はあ!? 何だって!?」
数日前、修也の父親が突然言い出した事に、驚き声を荒げ問う。
「どうした?そんなに驚くようなことを言ったつもりはないが?」
一方、彼の父親はあっけらかんとしている。
「突然外国へ転勤と聞けば誰だって驚くわ! しかも、俺だけ日本に残るって、どういう事だよ!?」
「どういうも何も、言葉通りだ」
「いきなりそんなこと言われて、はいそうですかって納得できるわけねーだろ!」
「そうは言ってもお前も高2だ。この時期にバタバタしたくはなかろう?」
「そりゃそうだが……」
「大丈夫だ。お前ならどこに行ってもうまくやれるさ」
そう言い放つ父親。無責任にもほどがある。
しかし、修也には別の気になることがあった。
「どこに行っても……ってどういうことだ? 俺一人でここで暮らすんだよな?」
修也は尋ねた。
「修也、この家が社宅であることは知っているな?」
「ああ、もちろん」
「だから転勤に伴って、この家も出て行かなくてはならないんだ」
「まあ……そりゃそうだな」
「だからお前も転校しないといけなくなってな」
「マテ。それはおかしい。何故そうなる」
堪らず修也はツッコミを入れた。話が飛躍しすぎている。
「いくらなんでもいきなり一人暮らしは無理だろう。お前に家事なんて出来ないだろう?」
「う、確かにそれはそうなんだが……」
修也は運動、勉強はそこそこ出来るのだが、家事はサッパリである。
流石に家電の操作くらいはできるが、それだけではまともな生活を送ることは難しい。
「だから母さんの知り合いで身柄を引き受けてくれる人がいるから、そこで居候させてもらえ」
「なんか犯罪者チックな言い回しだな……いやそれよりも、ただの知り合いには荷が重すぎないか?」
いきなり人ひとりを受け入れるのだ。修也の懸念も最もだ。
「…………それが『ただの』知り合いじゃなかったとしたら?」
「……え? どういうこと?」
「聞くところによると、母さんとその知り合いの人は高校と大学が同じでな」
「別に珍しい話じゃないと思うけど」
「大事なのはこの先だ。どうもこの二人はただの友達という範疇を超える付き合いがあってだな」
「……え?」
「ちょっとここでは言えないレベルの睦まじい仲で……」
「……は?」
「しかし当時はそういうことにまだ偏見がある時代で、二人は周りにバレないようにこっそりと関係を育んで……」
「……」
「……っていう話だったら面白いと思わないか?」
「創作かよ!!」
真面目に聞いて損した。修也は頭を抱える。
「お父さんの戯言は置いといて、快く引き受けてくれたのは本当よ?」
そこに修也の母親がやってきた。
「この前話す機会があったから今回のことを打診したんだけど、今は母子家庭でずっと娘と2人で生活していたから、男手がいると色々助かるって」
「だからって俺に一言もなく決めるなよ!」
「良いじゃない。いきなり一人残されるよりはマシでしょ?」
「ちなみに、もう手続きは済んでいるからな。いつでも出発できるぞ」
「何だって!?」
「だから近いうちにこっちの友人に挨拶はしておけよ」
「はあ……もういいよ……」
修也はため息と共に答えた。諦めたとも言う。
この両親は一度言った事を取り消すことはない。ここまで話が進んだ以上もうどうしようもないのだ。
修也は引越しの準備をするため、自分の部屋に向かおうとした。
「あ、そうそう、修也」
「なんだ? またつまんねー創作話か?」
父親が呼び止める。修也は再び父親に向き直った。ジト目で。
「いや、これはとても真面目な話だ。……なるべく『力』は使うなよ」
「っ! ……ああ、分かってるよ」
今までのふざけた空気ではなく、父親は修也に告げた。修也も頷く。
「じゃあ向こうのご家庭に近いうちにそちらに行くって連絡しておくわね」
母親がそう言って、その場は解散となった。
「あ、そうそうお父さん」
「ん? どうした母さん」
「さっきの創作話……どういうつもりかしら?」
「あ……い、いや、あれは口から出まかせの完全なフィクションで……」
「そんな適当な話をしちゃうお父さんはちょっと矯正と教育と修正が必要かしらね~?」
「し、修也ー! 助けてくれー!!」
「……知らん」
せいぜい痛い目に遭えばいい。修也は心の中で毒づきながら自分の部屋に戻っていった。
●
いい加減座席に座りすぎて腰が痛くなりかけた頃、ようやく目的地の駅名を告げる車内アナウンスが流れた。
「……やっと着いたか……」
座り続けたことで凝り固まった筋肉をほぐすように伸びをしながら修也は電車を降り、改札を出る。
駅前はそれなりに人通りがあり、賑わっていた。
「で、俺はこれからどこに向かえば良いんだ? ……そういや母さんがメモを渡してくれてたな」
母親から渡されたメモの存在を思い出し、修也は自分の鞄を漁る。
「えーっと……」
メモに書かれている内容に目を通していく修也だが、段々とその表情が引きつっていく。
そして……
「分かるかこんなのっ!!」
思い切り地面にメモを叩きつけた。
「どうしろってんだこんな説明で! 分かるわけないだろうがっ!!!」
この場にいない母親に憤慨する修也。
と、そこに……
「あの、どうかされましたか?」
背後から修也に声がかけられた。
「え?」
修也は声をかけられた方向に顔を向ける。
そこには地元の学校の制服と思われる服装をしている少女がいた。
背は修也より頭一つ分くらい低い。
髪は青みがかっていて、肩にかかるかどうかというくらいの長さだ。
着ている制服は真新しい。袖を通すようになってからまだ日が浅いのだろう。
その割にはしっかりとスカートの丈は膝上からさらに少し上くらいになっている。
しかし品の無さは感じられない。むしろとてもよく似合っている。
素朴な感じのする、とても可愛らしい子だった。
「……? あの、どうしました?」
観察の為にじっと見ていた修也が不思議だったのか、小首を傾げて疑問顔になる少女。
「あ、ああ、すまない。何でもないんだ」
「……? そうですか。それで、何か困り事ですか?」
少女は大して気にした様子も見せず、本来の質問に戻る。
「実はついさっきこの町にやってきたんだが、目的地が書かれたメモがあまりにも酷くてな……」
「ああ、さっき地面に叩きつけてたものですね? 見せてもらってもいいですか?」
「まあこんなもので良いんなら」
そう言って修也は少女にメモを渡す。
「えっと……」
渡されたメモに目を通す少女。
その表情が先程の修也と同様段々引きつっていく。
「『駅を出てお日様を背に歩いて塀の上で昼寝をしている三毛猫がいるお宅の角を右に曲がってそこからぶわーっと進んでがーっと走ってどーんって曲がれば見えてくるはずよ!』……えーっと……」
「良いんだぞ? さっきの俺みたいに『こんなの分かるわけないだろ!』って地面に叩きつけても」
「あ、あはは……」
修也の言葉に引きつった笑みを浮かべる少女。
「あ! でもこのメモ、2枚目がありますよ! しかも地図みたいですし、これなら……」
そう言ってメモをめくり、2枚目のメモに目を通す。だが……
「…………えっと……?」
再び表情が引きつる少女。
それもそのはず。2枚目のメモには何かよくわからない幾何学的な模様が描かれているだけなのだ。
「……もう一回言うぞ? 『こんなの分かるわけないだろ! 』って地面に叩きつけても良いんだぞ?」
「あ、あははは……」
「しかし参ったな、これではどこに行けばいいか分からん」
「確かにそうですね……他に何か情報はないんですか? 施設名とか。私、この町に住んでいるのでもしかしたら分かるかもしれませんよ?」
「いや、実は普通の民家なんだよ」
「民家ですか? なんて言う方の家なんですか?」
「『舞原』さんの家……って言っても流石に分からんだろ?」
「えっ? 『舞原』ですか?」
「ん? もしかして知ってる?」
「知ってると言うか……それ、私の家ですよ!」
「え?」
「私の家を探していると言うことは……もしかしてあなたは土神さんですか?」
「あ、ああ……そうだけど」
「わぁ、やっぱり! 話はお母さんから聞いてます!」
修也の名前を聞いた少女が表情を輝かせて距離を詰めてくる。
いきなり美少女と呼んでも差し支えない子の顔が近くに来たことで修也はちょっと焦る。
「初めまして。私、
「あ、ああ……よろしく、舞原さん」
「そんな、これから同じ家で暮らすのに苗字呼びなんてよそよそしいですよ」
「……え?」
「お母さんも『舞原』なんですから、区別するためにも私のことは『蒼芽』って呼んでください」
「……おお?」
蒼芽は随分とフランクな性格をしているようだ。
「その代わり、私もあなたのことを名前呼びさせてもらいますね? えっと……そう言えばまだフルネームをお伺いしていませんでしたね」
「あ、ああ……俺の名前は、土神修也だ」
「だったら、修也さん、ですね」
「……まさか俺に、女の子に名前呼びされる日が来るとは……」
「あはは、そんな大層なものじゃないですよ。それじゃ、行きましょうか」
そう言って蒼芽が歩き出した。修也もそれに続こうとする。
「そう言えば、修也さんは私のことをどう呼んでくれるんですか? 」
が、2・3歩歩いたところで蒼芽が立ち止まり、くるりと振り返りながら尋ねてきた。
「え? えっと……蒼芽、ちゃん……かな? 呼び捨てはなんか偉そうな感じがするし」
「私としては呼び捨てでも良いんですけど……ちゃん付けもなんだか可愛らしいですね。ふふっ……気に入りました!」
「そ、そう? 良かった……」
初対面の女の子にちゃん付けとか、馴れ馴れしすぎやしないか? と修也は危惧したが、どうやら杞憂だったようだ。
「では改めて……これからよろしくお願いしますね? 修也さん」
「ああ、よろしく頼む……蒼芽ちゃん」
「はいっ!」
修也の言葉に、蒼芽は弾ける笑顔で返事を返したのだった。


