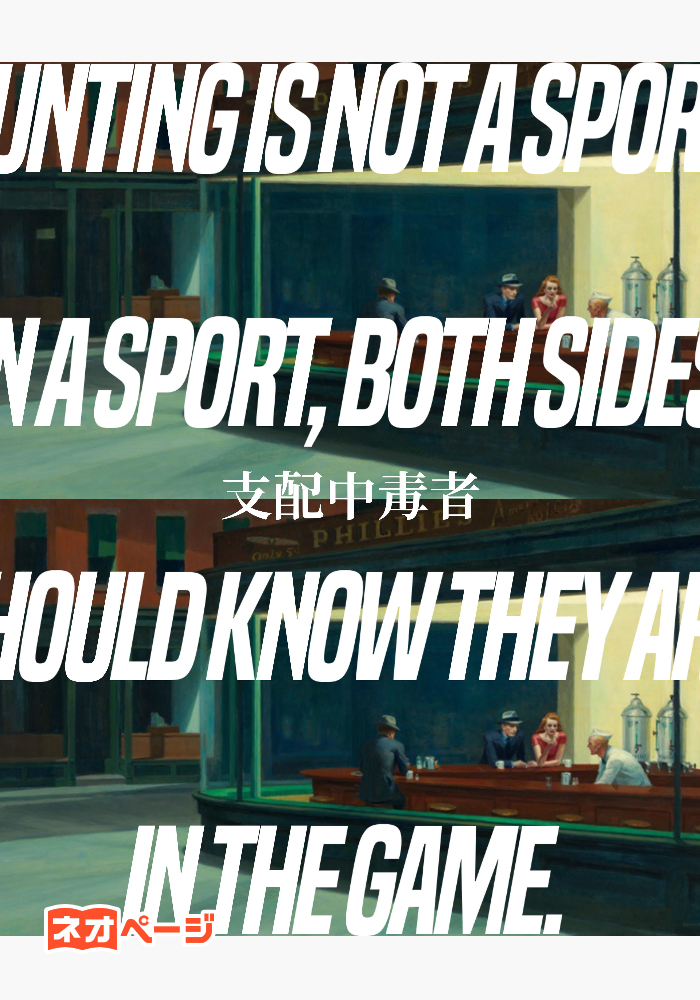
公開日
連載中
「アンタ、俺を理解できるのか?」
「こんな場所今すぐ逃げろ」
三者三様の欲望が渦巻く裏社会の壊れた話。
#01
英語にしたらJust do it.だろうか。薬物中毒の私の親を踏みつけ、私に金属バットを手渡した男。悪魔のような囁きで私を惑わした。
やれ。とにかくやってみろ。アンタならできる。
悪魔のようで神様のような男だった。私はあの日を忘れられない。
父と母は凡庸だった。なんの取り柄もない少年Aと少女Aだった。世の中を疎ましく思いながら男と女は快楽に溺れ、私を産んだ。そのうち男と女は営みよりさらに快楽を享受できる薬物に手を染めた。薬物に懐柔されるのは早かった。
そうかぁ。それは大変だったね。可哀想に……。でもねぇ、わかるだろ? こっちも慈善活動じゃないんだ。払えません。はい、そうですか。それは無理ってもんよ。
薬物がどこから流れてくるのかはなんとなく理解していたけれど、狭いアパートに土足で入ってきた人間たちがいわゆるヤクザという者だということはそのときに実感した。父と母は薬物を買う金を闇金から借りていたらしく、取り立てのヤクザが催促の知らせに来たのがその日だった。それが彼、紺野庵との出逢いだ。靴が綺麗に磨かれていたのを今でも覚えている。
種明かししてあげるとね、元々、同じ会社なんだ。アンタたちが借りた金もその借りた金で買ったヤクも元を辿れば両方同じ会社なの。だからさァ、アンタたちイイ顧客だったわけよ。
テレビの中だけだと思っていた。目の前の男が煙草を咥えると火を灯す役目の人が出てくる。そんなことはフィクションの中だけなんだ、と思っていた。でも眼前の男はさも当然のような顔をして乳白色を吐き出した。
「せんせーい」
「……はいはい」
私は久しく若かりしころの紺野を思い出しセンチメンタルに耽っていた。私はあのときの紺野と同じく煙草を咥え乳白色を吐き出し、闇に染まった。
にへら、と笑った赤髪の男が私を呼ぶ。フランクで脱力感のある口調が特徴の男は下腹部を手で押さえながら部屋に入ってきた。
「刺されちゃったー」
「……君を縫うのもそろそろ飽きた」
「せんせぇ、そんなこと言わずにさぁ〜。ハグしてあげるからぁ」
「君のハグに価値があると?」
「ステイステイ」
センタータンの舌が動き回る。よくもまぁ、刺されておいてそんな元気に喋れるもんだ。
煙草を咥えながらコーヒーを持ちにソファを立つと、彼はへらへら笑いながらステイと私に命令する。片眉を上げながら彼を見れば子犬のように近寄られ、そのままハグをされる。
「俺のハグプラス飴ちゃんあげる〜」
「……君、これ食べられないだけだろ?」
下腹部から出る血液がハグをしたときに私のジーンズに付着した。渡されたのはニッキ飴。紺野のお気に入りの飴だ。
父と母の顔面を金属バットで殴りつけ、血塗れになった私。見るも無惨な原形を留めていない両親の顔面を見つめていれば、紺野から琥珀色に輝くニッキ飴を差し出された。
アンタならできると思ったよ。
紺野は向上心の強い男だった。私に飴を手渡したときには確かにすべての指が揃っていたが、第五指、いわゆる薬指はいつの間にか無くしていた。紺野は「食っちまった」と朗らかに笑っていた。今、美しくしなやかな手は欠損した指を隠すためにか黒色の革手袋に覆われている。
「だぁってさぁ、庵ちゃん、俺これ好きじゃないっす、って言っても何回も忘れるんだよ。イヤになるって」
「……紺野のことをちゃん付けで呼べるのは君だけだろうし、許されているのも君だけだろうね」
私は煙草を指先に挟み、コーヒーサーバーから注いだコーヒーを口に運ぶ。コーヒーを嚥下する音が室内に響いた。
人の性質というのは不思議だな、と考えながら赤髪の男、隆二を見つめる。紺野にはリュウと呼ばれ、特攻隊として重宝されていた。隆二は立場、状況関係なく常にふざけており何度刺されても、何度殴られても倒れない──いわゆる頭がイカれている──強さを兼ね備えている。
「いやぁだなぁ、そんなこと言ってせんせぇだって裏では庵ちゃんのこと好きな名前で読んでそうだけどぉ。イーちゃんとか言ってラブラブしてそう」
「どこ情報だい? 随分と狂っているじゃないか」
私ははッ、と破裂音で笑いながら、へらへらと笑う隆二を見つめる。下腹部からどろり、鮮血が垂れている。隆二なら後一リットルくらいは流れても問題ないだろう。
「庵ちゃんが拾った女はただひとり。それは先生だけ。もう庵ちゃんと寝てたりするんじゃないの?」
「……ヤクザの情報網もそんなもんか。可哀想だな」
「それよりさ〜、そろそろ止血して…、クラクラしてきた」
「よく喋れるなぁと思っていたよ。血は一リットル流したら命に関わる」
「早く言って〜」
部屋に置いてあるベッドに寝転がる隆二。私は煙草を咥えながら戸棚を開ける。闇医者として違法に入手した道具がずらりと並んでいた。私はその中から刃物を手に取る。
「ちなみに──
「いっ゛……!」
隆二の下腹部の刺傷の隣に刃物を突き立てた。
「人はおおよそ十センチメートルの深さで三回程度刺されれば死に至る」
「……だぁー!! イッテって先生! 傷もうひとつ作ってどうすんの!?」
「まだ三回は刺されてない。死なないよ」
刺傷が二箇所になっても叫べる元気があるのはバケモノだな。私は穿った刃物をするり、抜く。ぴしゃり、血が弾け飛んだ。私の服を汚す。
「庵ちゃんに言っといて。労働環境改善しろって」
「……それ言ったら多分先生の仕事が増えるだけだよ」
はぁ。私は溜め息を吐き出す。隆二の傷口を清潔なガーゼで止血し、針と糸で縫っていく。ヤクザという者はどうしてこう血で血を洗うのだろうか。


