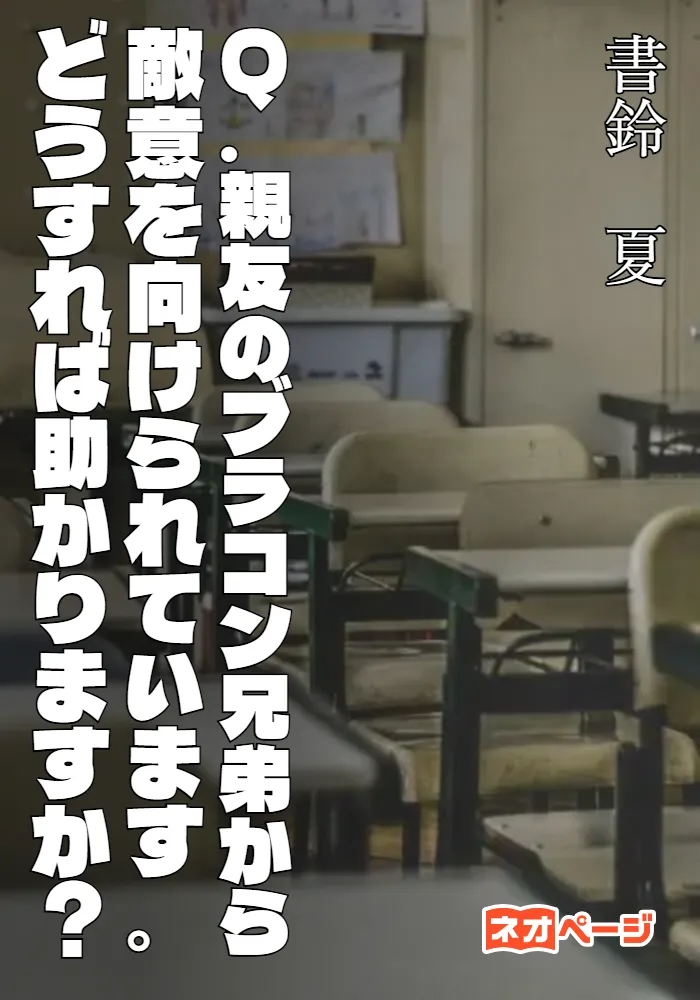
公開日
連載中
それは、親友である八乙女楓真«やおとめふうま»の兄と弟から、尋常でない敵意を向けられることであった。ブラコンである彼らは、大切な彼と仲良くしている茂部を警戒しているのだ──そう考える茂部は悩みつつも、楓真と仲を深めていく。
友達関係を続けるため、たまに折れそうにもなるけど圧には負けない!!頑張れ、茂部!!
なお、兄弟は三人とも好意を茂部に向けているものとする。
突然だが、俺──茂部正人には恐ろしい相手が二人いる。
それは、数少ない友人かつ中学入学時から高校二年現在に至るまでの長い付き合いである
兄は柔和な微笑みを常に浮かべているような、なんとも儚げかつ穏やかな雰囲気を纏うひとつ上の先輩である。対照的に弟はつり目がちで高飛車そうな近寄り難い印象を与える、ひとつ下の後輩だ。どちらも顔立ちは正反対の系統ではあるが、校内でダントツ上位に入るほど整っている。今日はどっちが先に来るんだろうね、なんて女子が色めき立つのもおかしくない。結局二人とも同じタイミングで来るというオチもそれなりにあり、そういった日は同時に拝めたからか女子たちのテンションも目に見えて高いのだ。
そして彼らは、顔も良ければ頭も運動神経もトップクラスと来た。完璧人間故のお近づきになり難いオーラを放っている人種である。
その血が繋がった親友も顔に関して言えば当然良いには違いないのだが、楓真はイケメンというよりはどちらかというと中性的な可愛らしい顔立ちだ。成績は低いわけではないが特別良いというわけでもない。なにより俗に言う──ドジっ子、というやつだった。馴れ初めだってそうだ。入学早々青い顔になっていた彼に居てもたってもいられず声をかけ聞いてみれば、忘れ物をしたと言われ筆記用具を貸したところから始まったし、そういうミスをしやすいタイプなのだ。本人にとってはコンプレックスらしいが──まあ言わば、愛されキャラみたいなものだろう。
男にドジっ子などという表現を使うのは些か首をひねりそうになるが、ともかくそういうところや人懐っこい性格に親しみを感じ、今思えば奇跡的に友人になることができたのだ。彼と行動を共にできるようになったおかげでぼっちを回避できたと言っても過言ではないような、感謝してもしきれない存在である。
なにもかもパッとせず、苗字の時点で平凡を運命付けられたような俺にとって、近付きやすいとはいえある種漫画の主人公のような楓真の存在こそが唯一の非凡であった。……だからだろうか。その兄弟に、並々ならぬ敵意を長年の間、それも毎日向けられているのは。
「楓真」
朝、一限前の瞬きよりも短い安らぎの時間。
楓真との談笑の最中、教室前方の入口からかかった聞き覚えのある声に、思わず大げさに肩が跳ねる。落ち着いた優しい声色だがなによりも恐ろしい。何故ならまさにそれこそが、俺を敵視している、楓真の兄──優真さんのものだったからだ。
柔らかな茶色がかった黒髪を揺らし、こちらへ歩んでくる。三兄弟の中でも頭ひとつ抜けた長駆は、大した身長にもならないまま成長の止まったこちらにも少しくらいわけて欲しいものだ……なんて、現実逃避もしたくなる。そうでもしていないと、今にも緊張で逃げ出してしまいそうだから。
「兄さん」
「あ……どうも」
「……こんにちは。茂部くん」
ぴくり、と形の良い笑みがほんの僅かに引き攣ったのはきっと、いや確実に見間違いではない。弟に向き直った次の瞬間には、クラスの女子が一人残らず惚れるような綺麗な笑顔に戻っていた。胃が痛くなる。
「またお弁当忘れてたから届けに来たよ」
「え、うそ! 忘れてたっけ? 入れたと思ったんだけどな……ありがとう」
「いいんだよ。可愛い弟のためだからね」
「あはは、はいはい」
弁当を手渡すと同時に自然な動作で楓真の頭を撫でた。もう見慣れたものである。最初はそりゃあもう距離の近さやスキンシップに驚いたが、中学の頃から何度も行われているのだ。慣れない方がおかしいだろう。なんなら髪にキスまでしても俺は驚かない自信がある。ああまあこの兄弟ならするだろうよ。
「茂部くん、今日はどこで一緒にお昼食べようか?」
くる、とこちらを向いた楓真の無邪気な笑み。瞬時に兄もこちらへ視線を注ぐ。
「……あ、あー……うん、そうだなぁ……」
「…………」
痛い、視線がすごく痛い!
前の席に座っている楓真は横に立つ兄の顔が視界に入っていない。いや、俺も視界には入っていないのだが、なんとなく感じ取れる。どんな恐ろしい目をしているのか。じっとこちらを見つめるそれと目を合わせたら最後、俺は石になって死んでしまいそうな気さえした。
「……ふふ、毎日一緒に食べてるんだよね。楓真が嬉しそうに家で話すから知っているよ」
「あ、言わないでよ!」
「そ……そうなんですか? わあ、そっかー……」
「うん。……本当に、仲がいいよね」
含みが怖いよお兄さん!!
彼の言葉の最後には、括弧書きで威圧という文字が補正で見える。気のせいではない。絶対に。
「茂部くんの卵焼きすっごく美味しいから好きなんだ。手作りだもん、すごいよね!」
声を弾ませた楓真の言葉に気恥ずかしさを覚える。これといって特別なところもない卵焼きだが、いつもおかずの交換で彼が「食べたい」と言ってくるくらいには気に入ってもらえているようだ。
だから、素直に嬉しいと思った。
思って、しまった。
「普通の卵焼きだしそれ以外は母さんのとか冷凍だけどな、はは」
ふうん。
場に響いて聞こえる冷めた声に、寒気を覚えた。ずっと不機嫌そうな色が浮かんでいる。何故かなんて疑いようもない、楓真が俺を褒めたからだ。
「俺も食べてみたいな。……どんな味なのか、気になるからね」
俺の弟にどんな不味いもん食わせてんだお前ってこと? 下手なもの食わせてたら容赦しないぞってこと?
「今度食べさせてよ、ねえ?」
「あ、はは……いや、お口に合うかどうか……」
むず痒い褒め言葉に素直に喜ぶんじゃなかった。目に見えて機嫌が急降下した優真さんがじわりと詰め寄って来て、口元が引き攣る。
「もう、今日の一限は移動教室でしょ、遅れるよ! ほら、戻って戻って!」
楓真……!!
俺の親友は救世主だった。楓真は椅子から立ち上がると、ぱしぱしと兄の背中を軽く叩いた。子どものするような仕草に、優真さんがおかしそうに笑う。
「わあ、楓真ったら。まだ時間あるよ?」
「いいから! 茂部くんも困ってるでしょ!」
「…………、迷惑だった?」
「えっ!? い、いえ! 全然!」
弟に注意されたせいだろう、優真さんは神妙な面持ちでこちらを見下ろした。下手なことは言わないに限る。本当に。
「……そう」
冷たいって〜!!!
慌てて否定した俺の反応に、小さく息をついてから素っ気なく呟いた。誰にでも優しい人が俺にだけ冷たいのは、なかなか心を抉られる。可愛い弟に付き纏っているから好きになれないとはいえ、血反吐を吐きそうなほど俺は心の中で叫んでいるのを知って欲しい。いや、知られても怖いからやっぱりいい。
「それじゃ、戻るね。ばいばい、楓真、……茂部くん」
「うん、またね」
「ど、どうも、お兄さん……」
彼が去ろうとしてすれ違った、その一瞬。耳元で、低い声がする。
「……卵焼き、覚えてるからね」
終わった。命日は近いかもしれない、なんて甘いものではなく確実に近い。卒倒しなかったことを誰かに褒めてもらいたい気分だった。
「ごめんね、いきなり。お弁当ちゃんと入れたはずなんだけどな……寝ぼけてたのかな」
まさか弟に会いに来るために、抜き取ったとか。……いや、まさかな。そうだとしたら……ちょっと、怖すぎる。
あんまり気にするなよ、と宥めながら、恐怖から高鳴る鼓動を深呼吸で落ち着かせた。朝一番に兄が来るとは思いもしなかった。予想外の来客ではあったが、これで少しは落ち着けると息をつく。
授業まで少しは時間があるとはいえ、まさか弟くんは今は来ないだろう──
「兄さん」
「あれ、
なるほど、俗に言うフラグであった。弟である陽真くんの凛とした少し高めの声が耳に入る。
恐る恐る顔を上げると、ばちりと視線が合って彼の唇の端が不快そうに歪められた。もうつらい。ツリ目がちで気の強そうな印象も相俟って、敵意が一層強く伝わってくる。兄同様に柔らかそうな、濡れ羽色の髪は今にも逆立ちそうだ。まるで威嚇する黒猫みたい──と思えるほど、俺は彼が可愛らしくは見えない。せめて黒豹である。
「優真兄さんもさっき来てたよ。二人とも朝に来るなんて珍しいね」
「……優真兄さんも? へえ……」
面白くないような顔だ。大方先に来て抜け駆けされた気分になったのだろう。
「それで、どうしたの?」
「僕の電子辞書、楓真兄さんのバッグに入っていませんでした? 一限で使うんですが、見当たらなくて」
「あ、昨日一緒に勉強してたときに間違えて
「お願いします」
唯一の頼みの綱が席から立ち上がり、教室後方のロッカーへと向かってしまった。気まずいから行かないでくれ、などと言える訳もなく。
「…………」
「…………」
落ちた重い沈黙。それと依然として鋭い視線に、ちくちくと肌を刺される。
黙ったままなのはどうなんだ。先輩として空気が読めていないんじゃないのか。たとえ相手が俺を嫌いでも、少しくらいはコミュニケーションを取る気がある姿勢を見せるべきなんじゃないのか。
そうだ。いけ、茂部正人。お前がここで動かなかったらそれこそ一生モブのままだぞ!
そうして俺は、一世一代の決心とともに口を開いたのだ。
「えっと、弟くんはさ……」
「あの。弟くんって言うのやめてくれません? 嫌なので」
楓真お願い、早く帰って来てくれ。もう心が折れそうだ。
兄の遠回しな威圧も精神に来るが、嫌悪もろだしの直接的な言葉も精神になかなか来る。呼び方キモかったかな、と年下に泣かされそうになりつつ、慌てて口を開く。
「えっ、あっごめん……え、じゃあ、ええと……」
「……名前で、いいです」
「あ、うん、は、陽真くん……」
「……まあ、いいです。それで」
不服そう!
陽真の方が距離感近くなってないか。それはまだ耐えられる方なのか。もう彼の地雷がわからない。これは波乱だ。
探るように言葉を選んで、口を開く。
「……え、えーと、昨日一緒に勉強してたの?」
「ええ」
「やっぱ仲良いんだね、きょうだいがいるの楽しそうだなー、って、思っちゃうな……」
「ええ、まあ。……茂部さんはひとりっこでしたよね」
「! う、うん」
話に乗ってくれたという小さなことが大げさなほどに嬉しくて、思わず大きな声で相槌を打ってしまう。
「弟が欲しいと思ったこともあってさ……だから陽真くんみたいな弟がいる楓真がちょっと羨ましくなったときもあるよ」
笑ってそう言えば、彼は目を小さく見開いて。それからまた渋い表情を作り口を開いた。
「……そうですか。僕はあなたが兄なんて考えられませんけどね」
「うん……そうだよね、……うん…………」
泣いていいか、これ。
上げてから落とされるダメージは尋常ではない。そんな俺の様子には構わず、冷たい声で言葉を続ける。
「兄がいる方がお似合いですよ」
「……今から増えることあるかな?」
そんなに弟になりたくないか。
刺さった言葉の矢に苦しんでいると、「ごめんごめん、あったよ!」と楓真の焦った声が話を遮った。楓真には助けて貰ってばかりだ。
時計を見れば、もう開始まで三分前。辞書を受け取った弟くん──いや、陽真くんは少しだけ名残惜しそうな素振りを見せると、俺たちに向き直って声を発した。
「それじゃ、失礼します。楓真兄さん、……茂部さん」
忌々しげに吐き捨てられた硬い声に傷つくと同時に、脱力しそうになった。ああ、まずは山場を乗り越えられた、と。今日はまだ長い。この後も教室に来る可能性はあるが、なんとか生きたのだ。
授業が始まる前から疲弊しきった体に鞭を打って、一限の準備を始めようとしたときだった。
「…………はぁ」
突然耳に入ったのは、小さな溜息。先ほどまでにこにこ微笑みながら手を振って弟を見送っていた、楓真のものだった。
「どうした?」
「……あ、ううん。いや、俺本当にミス多いなって……」
「うーん……まあ、重なるときもあるよ。俺だってそういう日はあるしさ」
「……そうかな。ごめんね。俺、相変わらずこんなんで……茂部くんにもすごく迷惑かけてるよね」
「は? そんなわけないだろ」
反射的に言い切る。楓真は面食らったようにぱちりと瞬きをした。
「……ほら、初めて会ったときもさ。お前が忘れ物したおかげで関わるきっかけができたんだから」
「そう、だけど」
「それに迷惑だと思ったことも本当に一回もないし、あんま悩むなって。……楓真とこうやって友だちでいられてるの、あー……」
すごく嬉しいんだからさ。
「……っ、茂部くん!!」
「うわっ!」
蚊の鳴くような声で呟くや否や、がばりと抱きつかれる。距離の近い兄弟の影響か、なんやかんやでこいつもスキンシップは過多な方である。こうやって好意をすぐに顕にしてくれるのは、まあ正直嬉しいのだ。
初めて兄弟と顔を合わせたときの、彼らの値踏みするような容赦ない眼差しを思い出す。こんなに純朴な目が離せない家族がいるのだ、下手なやつとつるんで悪影響を与えられたら困るだろう。尋常じゃない恐怖を植え付けられはしたが、その気持ちも十二分にわかる、つもりだ。
多少は、本当に多少は自分への当たりもマシになったとはいえ、やっぱり警戒は拭われない。それも、仕方ない。だけど、もう少しだけでいい。……いや、本音を言うとずっと。
楓真の友人でいることくらいは、許してくれないだろうか。
***
「……はぁ……ほんっと、あの子……」
「本当に、あの人は……」
家に帰った後。楓真の兄と弟は、大きなため息をついて、顔を覆い──
『可愛い……!!』
声を揃えて、噛み締めた。楓真の親友──茂部の、かわいらしさを。
「世話焼きで、なんだかぷるぷるしてて小動物みたいで……もう、食べちゃいたいなあ」
「ええ、鈍感なところもまた可愛らしい」
ふふん、と陽真が得意げに鼻を鳴らして兄を見た。
「僕、やっと進展したんですから。初めて名前を呼んでもらいましたし? それにあの人、僕みたいな弟が欲しかったって言ったんです。好意的な証拠でしょう?」
「あれ、弟として見られてるんだ? 先は長そうだね」
「なっ、もちろん否定しましたしアプローチだってしました! ……伝わっては、なさそうですけど」
「ふふ、陽ったら必死で可愛い。俺は今度手作りの卵焼き食べさせてもらうんだ」
「はっ!? なんだそれ、羨ましい……!!」
「あのときの兄さんは強引だったけどね」
口を挟んだのは、楓真。少しだけ呆れを滲ませて、視線を向ければ。当の本人はほんの僅かに頬を緩ませて続けた。
「恥ずかしいな。必死だったんだよ」
珍しいその反応。ふふ、と小さく笑ってから楓真は唇を開いた。
「……茂部くんへの態度、変わったよね。優真兄さんも、陽真も」
ばつが悪そうに陽真が目を伏せる。
「……楓真兄さんを支えてくれた人なんですから、少しは見る目も変わりますよ」
「最初は警戒しちゃったけど、今は頭が上がらないよ」
「……うん」
茂部は、楓真の人生を語る上では欠かすことができない。それほどまでに重要な存在なのだ。楓真はその有り難さをじんわり噛み締めながら、過去を思い返した。
小学校は、あまりいい思い出がない。
ドジを踏みやすいところに目をつけられ、6年の終わり頃からイジメとも言いきれぬような、なにか悪感情の籠った小さな嫌がらせの対象になっていた。幼子の無邪気な悪意は真綿で首を絞めるように緩やかに、しかし確かに楓真の精神を削っていった。卒業も近い頃、異変に気付いた家族たちは楓真を気遣い、知り合いのいないところへ引越し、卒業と同時に県外の中学に通うことにしたのだ。
楓真も心優しい家族に報いるため、自身の欠点を治そうと意気込んだ矢先。楓真はというと──入学してすぐ忘れ物をし絶望していた。
どうしよう、どうしよう、なんでこんな早くにミスなんか!
カバンを底まで探っても、どのポケットを探っても見つからない。何度も確認したはずだったのに。
さあ、と全身の血が冷えていく感覚。情けなさと悔しさで頭がいっぱいになる。そこに声をかけたのが──茂部だった。
『なあ、大丈夫? 体調でも悪いの?』
『あ、その……ちがくて、俺……』
『うん。そんな慌てなくていいよ』
『あの……わ、忘れ物……、しちゃって』
筆箱、忘れてきちゃった。
震える声でそう言った楓真は、言い切るとともに顔を伏せる。まともに相手の顔を見ることはできなかった。
会ってすぐこんなミスをしたことを知られるなんて。呆れられるんじゃないのか。馬鹿にされるんじゃないのか。……また、嫌なことをされるんじゃないのか。
パニックで嫌な汗が吹き出る中、吹き出すような声が耳に入った。目を丸くする。不思議と、嫌な感情はそこに浮かんでいないことがわかったのだ。
『っはは、ごめん! 死にそうな顔してるからどうしたのかと思ったら……筆箱くらい大丈夫だよ。俺、シャーペンとか余分に持ってるから貸すよ』
『……いい、の?』
『え? そりゃ、いいに決まってるって。俺だって忘れ物とかするしさ……』
続く優しい言葉。だけど、甘えてはいけない。誰だって最初はみんな優しかった。回数を重ねるごとに、侮蔑が混じっていったのだ。何度もミスをすればこの少年だって嫌気が差す。
そうだ。自惚れてはいけないのだ。自分がそんな人間だと知れば、関わりたくないと思うだろう。
その原因は自分にあって、そうならないように努めなくてはいけないのだが、どうも生まれた不安は今すぐ消えてはくれなくて。弱音を、思わず吐いてしまったのだ。
『あの……俺、今までずっとそういうミス多くて……周りに迷惑かけることも、すごくあったから……』
『ふうん……そっか。じゃあ俺、できる限りフォローするよ。今日みたいにさ』
『えっ』
耳を疑う。平然と言ってのける姿に冗談かと思いもしたが、至極真面目な顔でいたのだから飲み込むのには時間を要した。
『いや、そんな……! 俺ももちろん気を付けるけど、そんな何回も助けてもらっちゃってたらそっちが大変じゃ──』
『いいって。別にそんなん苦じゃないよ、だって友だちになりたいし』
『え──』
時が止まったようだった。友達になりたい? 俺と? こんな、ダメなやつなのに? 会って早々に迷惑をかけてしまったのに?
黙りこくって顔を見つめていると、気まずそうに少年はへらりと笑う。
『……あー、なんか押し付けがましくなっちゃったな。ごめん、友だちになるのも無理にとは言わないからさ』
『え、あ、いや……違くて! ええと……その、友だちになってくれるの、嬉しくて……』
顔に熱が集まり、視線をうろうろと惑わせる。
だって、まさか、そんな。前の学校で散々嘲られた自分が、すんなり受け入れられる、なんて。あまりにも自分に都合が良すぎて、夢でも見ているようだった。
そんな楓真の様子を見た少年は、またおかしそうに声を上げて笑った。
『そっか、ならよかった! ……あ、自己紹介してなかったよな、俺は茂部正人』
『お、俺は、八乙女楓真……!』
『楓真か、……な、今日の移動教室のときとか一緒に行かない? 恥ずかしいんだけど、小学校からの友だちいないんだ』
『! うん……俺もいなかったからすごく嬉しい!』
『あ、消しゴム二個は……無いか。……えい』
『えっあっええ!? 新しい消しゴムでしょ!? 割らなくてもよかったのに、悪いよそんなの……!!』
『いいのいいの。この方が便利だろ、お互い』
茂部と名乗るその少年と談笑しながら、楓真は心の中で決意した。
茂部が、自分に見切りを付けたとき。自分が性懲りも無く失敗を重ねる中で、こんなに優しい彼がとうとう呆れてしまったら。
もう、友人を作るのは諦めよう。きっともう、自分と友人になってくれる人などいないのだから──と。
喜びと諦念に挟まれながら、いつか訪れるかもしれないその日を怯えて過ごした。彼と送る一日一日が輝いていたが、前の学校で向けられていた冷たい嗤いの浮かぶ目を、彼が向けてくる夢を何度も見て跳ね起きた。
どうかその日が来ませんようにと、固く手を組み願いながら浅い息を吐き、眠りについた。
そして、結局。楓真の決意と恐れは、ただの杞憂に終わることとなる。
友人になった彼は細やかなサポートを嫌な顔ひとつせずこなした。不注意に嫌気が差すこともなく、隣に寄り添い続けた。そのおかげもあってかゆっくりと、着実にだが楓真のおっちょこちょいな部分が改善していく様子を見せてきたのは、友人になって一年目のころだ。
他人への恐怖心も、自分へのコンプレックスも知らぬ間に消し去ったのは茂部である。間違いなく彼は楓真の、そして家族たちの恩人であった。
「……でもさ、いつも思うけどふたりとも緊張しすぎだよ」
「あの子を前にすると、自然な笑顔がわからなくなっちゃって。ちょっと意気込んじゃうんだよね」
困ったように微笑む優真の横で。普段から他人に対して笑いかけることもない陽真は、茂部のために毎日行っている笑顔の練習の効果が発揮出来ていないことを思い出し人知れず落ち込んだ。
「それに毎回忘れ物とか、用事があるていで来なくてもいいのに。もう普通に茂部くんに会いに来たって言えば?」
ちょっとは不注意なのも改善してきてるのに、ふたりがそうお願いしてくるから成長してないみたいじゃない。
「……だって、素直に言えるわけないじゃないですかぁ……」
「楓真に会いに来たって言い訳も使いすぎたし……いや実際その理由もあるけどね?」
「周りから見たらあんまり変わらないよ!」
「う……でも、そうですよね。すみません、兄さん……兄さんは忘れ物するの、コンプレックスなのに……」
「そうだよね……ごめん、楓真」
「ええ、ちょっと言っただけだよ! そこまで思い詰めなくていいから!」
「でも……」
「いーの! それに俺、最近はそういうとこもコンプレックスじゃなくなってきたんだから!」
「え……そうなの?」
「うん! ……だって、茂部くんが優しくしてくれるから、ね」
「……楓真、俺も前から思ってたんだけど……昔よりなんだか、その……変わったっていうか、強かになったね?」
「そう? ふふっ」
可愛らしい顔に浮かべた笑顔は、茂部に向けるものとは似ても似つかないほど艶やかだ。
ああ、あの可愛い子をどうやって落とそうか。
ほくそ笑む三人は、とんだ似た者兄弟であった。


