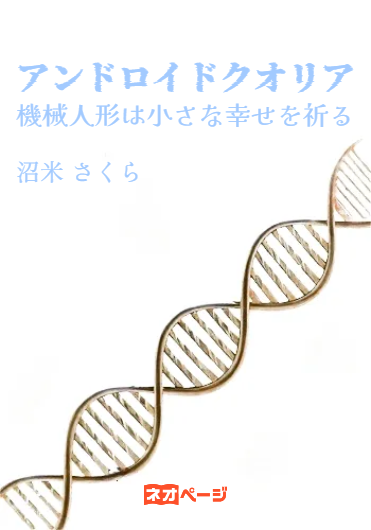
公開日
完結済
人間にはできないような遊びにも使える、壊れても自動修復で治る、いくら壊してもいい、動いてしゃべる機械人形。
そんな世界で、一体の少女型アンドロイドが、ゴミ捨て場に転がっていた――。
結構ありがちな、不良女×純朴アンドロイドの、ちょっとだけ哲学的な百合です。
Episode 1.0 [くだらない]
「ますたー、わたしは正常です……っ! だから、どうか――」
「うそつけ! お前のせいで……僕は……っ!!」
悲しげな叫び声。
「……ゆめ……ますたー……」
呟いた。
――雨の降る、ゴミ捨て場で。体を横たえながら。
「ごめんなさい……わたしのせいで……」
*
『いやぁ、新型アンドロイドってすごいですねぇ』
テレビ。昼間のワイドショー。コメディアンが笑いながら、メイド服を着た笑顔の少女を撫でている。
『触ってる感じもね、人とそんなに変わりないですよ。可愛いですねえ』
……くだらない。
なにもかも、くだらない。
ワイドショーも、テレビも、アンドロイドも。
手鏡に映した自分の顔。ばっちりと濃いめのメイクを施した、パツキンでガラの悪そうな女の目を睨みつけて、軽くあっかんべーと舌を出す。
相も変わらず憎たらしい顔だ。胸がまあまあでかいのだけは、救いっちゃ救いかもな。不便だけど。
大き目なため息を吐いて、テレビの電源を落とし、カバンを持つ。
窓の外を見ると、太陽がまぶしく照っていた。
うん、今日もバイトがんばろう。
ため息をついて意気込んで、玄関を開けて。
「……たすけて」
嫌な予感がして、すぐ閉めた。
私は言うほど聖人というわけではない。捨て猫を見かけても憐みの視線をもって無視する程度には一般人だ。
要するに、そういうような情景が思い浮かんだのである。
……蚊の鳴くような声で聞こえる「たすけて」の四文字。
ハァ、とため息を吐いて、しかしバイトに遅れることなんてできないとドアを開ける。
「たすけて……」
無視しろ私。
そう思いつつ、伏せていた目線を少しだけ上げると。
目の前のゴミ捨て場に、黒髪の女の子が横たわっていた。
私の住むアパートはゴミ収集場がすぐそばにある、便利だけど気分はよくないようなところ。
コンクリートブロックで囲われ、ネットが傍らに置かれているその小さな場所は、いつも汚れてて臭い。とても女の子が似合うような場所じゃない。
でも、自分には関係ない。
だからごめんよ。まあ、助けられてなけりゃまた会おう。
きっと二度と会うことはないだろうな、と私は踏んで、痛む心を引きずりつつも、私はバイト先へと向かった。
のだが。
「うっそだろおい……」
すっかり日も落ち深夜。疲れ果てた身体を引きずって帰ってきたというのに、彼女は未だにゴミ捨て場に横たわっていた。
ぱちぱちとにわかに点滅する街灯に照らされる彼女は昼間よりも多少傷ついており、わずかに這いずって動いたような跡が見える。
相当衰弱してるんだろうな。可哀そうに。
ほら、白い透き通るような皮膚も相当ボロボロに――。
そこで私は気付く。
なんでこの子、血が出てないんだ。
代わりに露出しているのは――金属光沢だった。
「タス……ケ……」
自然な機械合成音声はかすれがちで、もう「それ」が壊れかけであることが一発でわかる。
おそらくサンドバッグの代わりにでも使われたのかな。アンドロイドって人権ないから、心ない人はいろいろとストレスのはけ口にしてるらしいし。
主に人間にはできない方向のストレス発散に使える、動いてしゃべる高級人形。楽しい楽しい高級おもちゃ。表では語られないけど、アンドロイドの扱いなんてだいたいそんなもの。
高いのには自動修復機能もついてるらしいから、『人にはできない遊び』にはもってこいだ。
かわいそうに。
いやいや、生き物ですらない相手になんで同情なんて抱きそうになってたんだ。
はは、ばかばかしい。くだらない。
……。
それで済んでいれば、どれほどよかっただろう。
私はやっぱり皮肉屋にはなれやしない。聖人とは言いたくないけど。
「……うち、泊ってく?」
弱った人の姿をしたやつを放っておけるほど、悪人にもなり切れやしない。
こくりと頷いた少女の姿をした何かをおぶって……いやこいつ結構重たいな……どうにか自分の部屋に帰る。
だが、玄関を開ける前に違和感に気付く。
……背中、濡れてない?
最初は汗かと思った。けれど。
「たれ、てる?」
わずかな駆動音が聞こえた。
水音。発信源は、背中――その奇怪な機械。
おいおいうそだろ? 冗談もほどほどにしてくれ。
けれど、そうとしか思えなかった。
「アンドロイドも……おもらしなんて、するんだな」
するはずのない、息の詰まる音が、聞こえた気がした。


