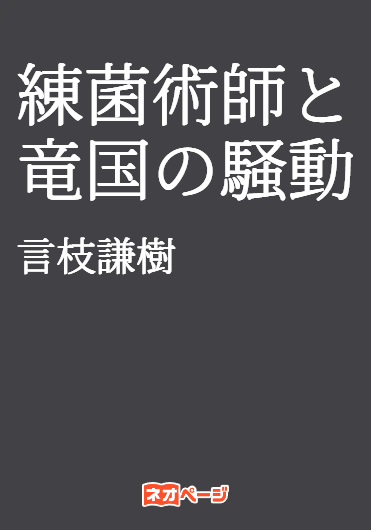
公開日
連載中
人間族の作った王国の北端に位置する新興市エクリウスは、北西方面で巨大な樹海と隣接している。
多種の動物、植物、菌類だけではなく、竜族、エルフ族を含む魔族が住むその森林地帯は、王国領土よりもはるかに広大な地だ。そこは薪や建材、腐葉土、季節の自然の実りなどを豊富に産み出す魅力的な場だが、やはり他種族のテリトリーという意識があり、人間族はあまり近寄らないようにしている。
あまり近寄らないというのは当然、全く近寄らないということではない。
樹海を棲家とする魔族たちも人間族と交流することを極力避けているので樹海の途切れる場所までやってくることはほとんどなく、そう奥地へ踏み込まなければ危険度は低い。
エクリウス城市内で一人練菌工房を構える僕は、そこでよく自然の恩恵にあずかっている。
茸狩りにゆくことにする。
樹海の中へは菌糸を織込んだ焦茶のマントを纏い、菌糸のハンティングベレイをかぶってゆかねばならない。
極力、菌を偽装しないことには、茸に出会うことも儘ならぬ。
今回の採集対象は浮揚茸。その胞子を加工し船体に塗ると浮力が格段に増加する。最近は巨大帆船の建造ラッシュとなっているので需要のほうも増すばかり。
目的地の樹海までは近所の農夫に手当てを払って荷馬車で運んでもらう算段。
市街のはずれ、高い市壁に程近く小さな民家の立ち並ぶ場所にある僕の工房を出て、早朝から賑わいを見せる商業区へ。石張り舗装を施された街路を早足でゆく。いくつかの物品を買い求めていると、以前植物系の素材を納品していた生花店の看板娘に声を掛けられる。
「あら練菌術師さん、今日のお召し物、素敵ですわね」
「ありがとうございます。まだ少し暑いですが必要に駆られまして」
彼女はいつも商業的なものとは思えないあたたかな笑顔をふりまいてくれる。僕のほうは一度たりとも愛想を見せたことはないのだけれど。僕はその存在自体に敬遠されるようなところがあるので人間族とはあまり親しくならないようにしているのだが、この娘の見せてくれる好意を心地よく感じてしまうことも、なくはない。
「暑さが気にならなくなるのも、すぐですわ」
「そうですね。よい茸が採れそうです」
年は十七、八だろうか、最近目立って大人びてきた娘は頬を薄っすらと赤く染めて言う。
「もう秋の気配がそこここに。私も茶系色の上着が恋しくなってきました」
「是非。似合いますよ」
「練菌術師さんこそ。焦茶のマントが白くて美しい顔を一層引き立てていますわ」
僕より少し年上の花の似合うこの娘は僕の容姿をよく褒めてくれるのだが、その度に居たたまれなくなってしまいそそくさとお別れの挨拶をしてその場を離れる。
僕は自分の容姿が好きではない。
城市の中心から一直線に伸びる中央道、馬車が頻繁に行きかう石畳の道を城門へ向かって歩いていると、呼び止められる。
「おい練菌!」
「おはようございます。錬金術師さん」
「ぐはは! またおめかししやがって、どこいくんでぃ!」
もしゃもしゃの金髪、不敵な笑みを浮かべるこの若者は、レンティヌスという名のとても腕のよいアルケミスト。
しかし、漆黒に染めあげた上衣とズボンは悪くないのだが、首に巻きつけているふっくらとした紅白の幅広ストライプマフラーがなんとも怪しげだ。九月に合った風体ではないしそれの長さも尋常ではない。後ろにだらりと下げている両端がほとんど地面スレスレにまで延びている。それはだらしのない触角にも見えるし、このような配色の蛾の幼虫がいたような気もする。
加えて常に肩に担ぐようにして持っている特大の巾着袋も甚だしく珍妙だ。中に何が入っているかわかったものではない。ごく稀にたいへん便利なものを出してくれるが。
錬金術師の後ろに半分隠れている小さな子供が二人。おそろいのブルーのコットに濃紺のシュルコをあわせている。
「くすくす」
「くすくす」
こちらを見て笑っている、双子のホムンクルス。実に美麗なる容姿の少年と少女。三フィート足らずの二人の背丈に合わせるために、僕はしゃがみこんで挨拶をする。
「メンダちゃん、アネトン君、おはよう」
二人は錬金術師の陰からとことこと出てきてペコリと頭をさげる。
「練菌のお兄ちゃん、おはようなのニャ」
「練菌のお兄ちゃん、おはようなのニャ」
短いおかっぱの銀髪に包まれた二人の可愛らしい頭を撫ぜる。よく出来た人造人間だ。
「きのこ飴、舐める?」
「舐めるニャ」
「舐めるニャ」
会うたびに僕の工房特製きのこフレイバー使用のフルーティーな飴玉をあげているので、わりと懐いている。きのこなのにフルーティーはないだろうと言われても困る。そのような香料がきのこから抽出出来てしまうのだから仕方がない。
「おいおい、こいつら餌づけしてもいいことねーぞ!」
錬金術師の言葉を軽く聞き流し、腰巻きのツールサックに入れてあったきのこ飴用の麻袋を開く。二人がちんまりとした手のひらを差し出すのでその上に一つづつ載せてやる。
「ありがとニャ」
「ありがとニャ」
ニマニマしながら桜色の小さな唇を少し開いて飴玉を口に入れる。
「甘いニャ」
「甘いニャ」
美しく整った顔に笑顔を浮かべる、幼き二人の人形。またあげようと思う。
そろそろ二十代半ばに差し掛かろうかという錬金術師、ホムンクルスを作り上げるくらいだから腕は最上級、しかし性格は傲岸不遜、そのくせ偉そうにしている領主や貴族が大嫌いで彼らの金銭援助をことごとく断り、こんな王国の北端の街に流れてきて平民街の片隅に工房を構え、なにやらゴソゴソと研究を重ねている。
市の人々はこの天賦の才を持つ傍若無人な若錬金術師を敬遠する者ばかりなのだが、新興市特有の自由な雰囲気もあってか、その特異な才能に興味を持つ奇人もまた少なからずおり、孤立することもなく日々過ごしている。
また、錬金術師のほうも自分が認めた人間にはフレンドリーに接するようなところもあるので、ここでの生活もそこそこ楽しんでいるようにも見える。
なにが彼の琴線に触れたのかは知らないが、僕も彼に気に入られている。
「茸狩りにゆくところです」
「おう! するってーと、こいつが菌糸のマントか!」
無作法なほどじろじろと見つめてくる。
「ふむ。いい光沢だな!」
不安になってもおかしくないくらいの時間見続けたあとに、彼はこう宣う。
「よし! 俺もつき合ってやるぜ!」
「いや、マントは私の分しかないし採集を一緒には出来ないですよ」
「ぐはは! 樹海のほとりの草原でごろごろしてるぜ!」
ピクニック気分だ。この人は言い出すと聞かないので早々に観念する。
「では、ご一緒しましょう」
「ごろごろするニャ」
「ごろごろするニャ」
双子も楽しそうにぴょこぴょこと跳ねている。
西へ向かう街道を荷馬車にて二時間程揺られる。農地や牧草地、点々と残る森が途切れて、延々と手つかずの草原が続く。
エクリウス市の一帯は元々森林だったのだが、樹海の周囲数マイルだけは何故か高木が育たず原野となっている。その不思議な領域は、開拓を拒否するかのような印象を隣接地に入植した人間族に与えた。
やんわりとした起伏を見せる草原。
深緑色の水平な広がりが見えてくる。空気が変わる。竜やエルフ、魔族の棲む、深く暗い森。
色々と厄介なことがあるので、定期的に樹海に入る人間は、この市には僕しかいない。
街道から外れてひたすら北進、樹海から百ヤード手前で停止。農夫にはここで待機してもらう。
「四時間程で戻ってきます」
「ああ。気をつけていっておいで」
錬金術師、双子と一緒に樹海の際までゆったりと歩いてゆき、適当な場所に莚を敷く。
「さあ、めし食おうぜ!」
「わーいニャ」
「わーいニャ」
本当にピクニックをしているようだ。まだ昼前だが自分も昼食。いつも一人で食事をしているので、心が少しあたたかくなる。
ホムンクルスの食事は彼らにとって一口大程度しかないオレンジ色のパンのようなもの一切れと、緑色のスウプほんの少し。あっという間に完食。二人はふわふわとした笑顔を浮かべながら言う。
「お花摘んできていいニャ?」
「お花摘んできていいニャ?」
「おう! あんまし遠くへいくんじゃねぇぞ! あと樹海には絶対入っちゃダメだかんな!」
「わかったニャ」
「わかったニャ」
くすくす笑いながら手を繋いでとことこと歩いてゆく。たまにしゃがんではちまっと花を摘み、けらけら笑いながらまたてくてくとあちらのほうへ。見ていると和む。
ゆっくりと食事をする。
錬金術師は、穏やかな面持ちで目を細めている。彼はたまにこんな表情をする。普段からその顔を皆に見せていれば敬遠されずに済むものを。
「そろそろ二年ですか」
かなりの間を置いて、返事がくる。
「ああ」
「凄いなぁ」
「あったりめーよ。俺様が作ったんだぜ」
錬金術師の顔に、いつもの傲岸不遜な表情はない。
ホムンクルスの寿命は、長くはない。
「六年でしたか?」
「そう言われちゃあいるがな、所詮は神代の頃からの言い伝えだ。三年もった奴は俺の知る限りはいねーな」
神代の技術は残念ながらかなりの部分が失われてしまっていて、断片的にしか伝わっていない。
「ま、人間がなんで死ぬかってことすら、よくわかってねーしなー」
「細胞レベルだと、不死みたいなものもあるのでしょう?」
「ああ、細胞分裂し続けるやつな」
近年、顕微鏡の発明でこの分野もずいぶんと研究が進んだ。
人間を構成する細胞は基本、分裂回数に上限がある。これが老化、死の原因の一つではないかと推察されているが、他にも原因と考えられているものもありそのメカニズムは未だ解明されてはいない。だが、分裂回数の縛りがなくなって、不死化といってもいいような状態になる人間の細胞も、ある。
「有名なんは、ある種の悪性腫瘍だな」
「はい」
「なにがあって上限がとっぱらわれっかが、わかんねぇ」
「菌類細胞だと、そういった上限は、基本ないともの思われます」
「植物細胞もそうだな。ただ劣化はあるだろ」
「挿し木だと根元に近い部分に新しく出てきたものを採って使うほうが、上の方のものより育ちがいいのだそうですね」
「上の方が細胞分裂を重ねてきた回数が多くて、劣化しているのではねぇかってとこだな」
この天才的な錬金術師の面白いところは、いつもは不敵、というか人を小馬鹿にしたような笑みを浮かべているくせに、こと研究の話になると急に生真面目な表情になるか、楽しいことに熱中している子供のような笑顔になる。
今の表情には、笑顔はない。
あの愛おしい双子の人形が消え去ってしまうのも、そう遠い先のことではない。
さて、森の中を探索だ。
「じゃ、ちょっといってきます」
「おう。昼寝して待ってるぜ」
「イノシシとか出てきたら撃退して下さいよ」
「ああ。熊でもやっつけるぜ!」
熊やオオカミ、魔族の類はこんな樹海の途切れる所まではほとんど出てこないけれど、以前さしあげた幻覚茸粉入りの熊除け玉くらいは持っているのだろう。いやいや、この人なら想像もつかないような謎の武器などもほとんど体と一体化しているようにも見えるメガ巾着袋に忍ばせていそうだが。
樹海のほうに歩いてゆくと双子がてけてけとやってくる。
「森に入るニャ?」
「森に入るニャ?」
僕はしゃがんで答える。
「うん。ちょっといってくるよ」
人気のまったくない草原の中で二人の頭を撫でてやると、神妙な顔をして小声で言う。
「練菌のお兄ちゃん、ボクたちに似てるニャ」
「似てるニャ」
「んー、髪の毛とか?」
同じ銀髪だし、ショートであるところも似ているといえば似ているかな。
「顔も似てるニャ」
「似てるニャ」
お互いに割と癖のない顔立ち、と言えばそうかもしれない。二人は銀色の大きな瞳を真っすぐに向け、いっそう声をひそめて言う。
「練菌のお兄ちゃん、ボクたちの仲間ニャ?」
「ボクたちの仲間ニャ?」
二人の絹のようにやわらかな髪をゆっくりと撫ぜる。
「……僕はね、ハーフエルフなんだよ」
「ニャ?」
「ニャ?」
二人同時に小さな頭を傾げる。
「練菌術師は皆、エルフかハーフエルフなんだ」
「エルフは森の人ニャ」
「森の人ニャ」
「うん。森や山に住んでいる。植物や動物、菌類と共に生きている」
「街にもときどき来るニャ」
「来るニャ」
「たまにね」
僕も付き合いがある。
「ハーフエルフはお兄ちゃんしか見たことないニャ」
「見たことないニャ」
「いないね」
さて、仕事を早めに片づけて戻ってこよう。ざっと立ちあがる。
「早く帰ってきてニャ」
「早く帰ってきてニャ」
双子はすがるように僕の手を握ってくる。
「うん。森の中へは入ってはだめだよ」
「うんニャ」
「うんニャ」
僕は二つのベビーサイズの手をやわらかく握ってお別れをし、暗く広がる樹海に入ってゆく。


