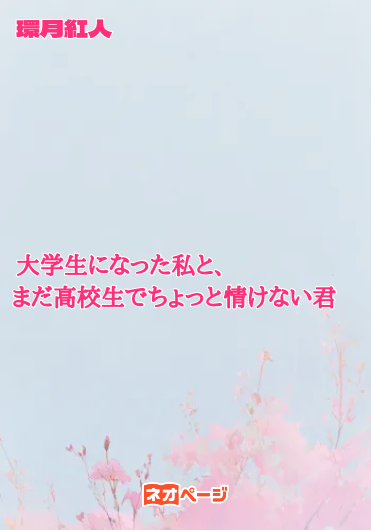
公開日
完結済
本編
三ヶ月前に僕は好きな人へ告白し、お付き合いすることになった。
先輩が、好きです。寂しくなります。あんなに楽しかったのに、一年しか一緒にいられないなんて、僕は嫌です。先輩を見送るべき卒業式なのに、この日がくることを僕は受け入れられなくて……。だから気付きました。僕は、先輩のことが好きだったんです。ずっと、初めて会った、そのときから。
………いま考えても、恥ずかしい。あのときの僕はどうかしてたけど、あのときの僕がいなければこうはならなかっただろう。
ぽこん、という音にスマホの液晶が明るくなる。ロック画面には部室でクリスマスを祝った僕と先輩が顔を寄せた写真の"先輩のほう"を切り取った待ち受けがあり、通知欄には彼女からのメッセージが『遅れそう?』ときた。
『いえ』『着きました』と返す。
彼女のご実家のインターホンを押した。
§
……
私はリラックスしてるけど、彼はそうでもないみたいだ。
「もう、ガチガチすぎ。私、君のお部屋に行ったことだってあるんだし、お互い様じゃん。くつろいでよ」
正座でかしこまる彼の心をほぐすように声をかける。彼は困惑混じりの笑みを返した。
「……その、大学、楽しいですか?」
なんだソレ。
笑ったら悪いから笑わないけど、普通に面白い。
「うーんと、楽しいよ。高校より自由って感じで」
「そうですか……。み、瑞希さんがそっちに行ってから、普段の瑞希さんが想像できなくて、僕はちょっと不安なんです」
「不安?」
「だって瑞希さん、絶対モテるじゃないですか……」
何を言い出すのかと思った。
笑い出したい衝動に駆られながら、いじらしい態度を見せる彼をからかいに走る。
「えぇ〜、嫉妬ってこと? まあ、確かに大学生ってちょっと大人に近づいてて、髪型なんかも染めたりして大学デビュー!してる人も多くて、服装のセンスもよく見えて、ちょっと子供っぽいところのある君とは少し違うかもね」
う、と呻く彼を見て、いたずらに笑う。
彼はむっとした顔を見せる。
「嫉妬してません。僕は彼氏ですし」
きょとんとした。
彼はときどき、私のふいを突く。
「……言うねえ。でもそんなんでいいのかぁ? ほら、もっと男らしくしないとさ……」
言ってるうちに、彼はずいっとこちらへ迫ってきた。そして、古典的な壁ドンで迫ってくる。こんな展開になるとは思わなかったけど、なるほど、これが彼の思う男らしさか、と可愛がりたくなる気持ちも芽生える。
……いや、嘘。
少しだけ"男"を感じさせるような面持ち。
ちょっと緊張する。
何を言い出すのかと、構える。
しかし、彼はふっと脱力した。
「やっぱり、僕は自信ないです……」
「抱っ、だっ……っっ!?」
「離れたくないです」
泣きつかれて、戸惑う。抱き締められるなんて、これが初めてだ。首筋に顔を埋められて、ふんわりと香る彼の髪の匂いに、彼の手が私の背へと回る。
私に甘えてくれているのが分かる。
「高校、寂しいです」
顔が熱くなる。この盛大な照れを彼にバレてしまいたくはなくて、私は必死になって表情を作る。
咳払いのあとの一音目は、上擦ってしまって、恥ずかしくて仕方なかった。
「ま、まあ、そうだね。私は男らしい君のことを好きになったんじゃないし、君は君のままだからいいんだよ。うん」
引きはがす。あの心臓のバクバクが、彼が離れても胸に残るので、私のものだったかと気付いた。
……ムカついたので、彼のおでこを小突く。
「そりゃ、私だって寂しいよ」
彼はほっとしたように笑った。


