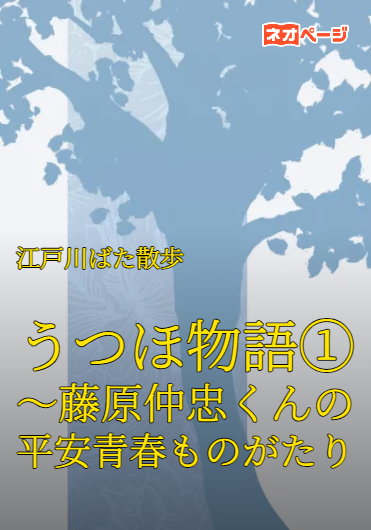
公開日
完結済
清少納言たちも萌えた! と言われている男子中心のものがたりです。
男性キャラの人物造形はそのまま、女性があまりにも扱われていないので、補完しつつ話を進めていきます。
第1話 その1 「琴の琴で有名な吹上の源氏の君のところへ遊びに行こうぜ」
発端は一つの訪問だった。
「こんにちはー!
声を張り上げ、
右大将、
花盛り、紅葉盛りには家族を連れて滞在するのが常。
その頃兼雅は、最愛の妻「三条の北の方」とその息子の仲忠と共に花の季節を過ごしていた。
「どうしたの? こんな所まで」
自宅ということで、楽な格好でくつろいで居た仲忠は、慌てて客を迎える。
「友達に向かって、どうしたもこうしたも無いだろ?」
ええ? と仲頼は笑う。
「おや、琵琶が。弾いてたのですか?」
かつては彼の琵琶の師でもあった行正は目敏く見つける。
「鶯の声が美しかったので…」
言葉を濁す。
仲忠はそれ以上は言わない。仲頼はそんな仲忠に、いつ見てもぼぉっとした奴だ、と思う。
「だったら笛にすれば良かったのに。それなら俺の領分だ」
「おやおやそう言って。あなたの笛で鶯が逃げてしまったらどうするのですか」
「まあまあまあまあ」
仲忠は笑う。二人はその笑顔に力が抜ける。
「そういう話をしに来たのではないのでしょ? わざわざ桂まで」
「ああそうそう」
うん、と仲頼は大きくうなづく。
「実はな、俺達明後日あたりからちょっと面白いところへ行こうと思っているんだ」
「面白い所? あなた、もうあらかた回ったって言ってませんでした?」
「いやいや、都じゃあないんだ」
「都じゃない」
首を傾げる。
「吹上の浜を知っているだろ?」
「紀伊国だね。遠くはないけど、近くもないなぁ。でも仲頼さんと行正さんが一緒なんでしょ? そうするとずいぶんな人になるじゃない。そんなに面白いところなの?」
「そう、そこだ!」
ぽん、と仲頼は膝を叩いた。
「仲忠、お前、そこに住んでいるという源氏の君のことを聞いたことないか?」
「え、もしかして」
仲忠はぱっと顔を上げる。
「そのもしかしてですよ」
ふふ、と行正は笑う。
「いや、この間、うちの部下の松方がその吹上の宮にこの間行ってきたんだと。あいつ、陣でもう、自慢するする」
「そうしたら、この好奇心旺盛なひとは、まず真っ直ぐ私の所へやってきたのでしたね。じっとしていられない、行こう行こうってしつこくって」
「……うるさいなあ。行正だってすぐに乗り気になったくせに。行きたいけどすぐに休暇が取れるか判らないから、いつ行くかを教えろって俺を急かして」
「僕も、父上からそのことは話を聞いていたんだ」
するりと仲忠は口を挟む。
「右大将殿が?」
「うん。あのひとは本当にそういうことについては、耳とか手とか早いんだ」
おいそれ、自分の父君のことだろう?
仲頼は言いたい気持ちはあったが、言葉にはしなかった。
「右大将殿はお前にどう話して下さったんだ?」
「うーん。色々話してくれたんだけど…… 琴が素晴らしいってことしか覚えてなくて」
「お前らしいよ!」
「あなたらしいです!」
二人の声が重なった。
「……だって、琴だし」
「……まあ、そのあたりが実にあなたと言えばあなたなんですけどね… 何をおいても琴琴琴! それも
「それでいて、いつの間にか、箏の琴も和琴も笛も琵琶も、師匠である俺達を追い抜いてしまうんだからなあ」
「だってお二人とも、女の方程、笛も琵琶もお好きではないでしょ?」
ああ! と仲頼は額を押さえる。
「比べられるものではないでしょう?」
「んー…」
行正の反論に口ごもり、仲忠は視線を逸らす。
「だいたいあなただって、あの『例の方』には何かと文を送っているという話ですよ」
「やめとけよ、行正。その話になると俺達は、自分の無様さを曝さなくてはならなくなるぞ」
そうですね、と行正は素直に引っ込む。
「話が逸れたぞ。ともかく俺達は行く。お前はどうだ? 一緒に行かないか? と言うか、行こう」
そう言って仲頼は仲忠の肩をぽんと叩く。
「うーん… 僕も行きたいなぁ、とは思うんだけど」
「…けど? 煮え切らないなあ」
「いや、父上がいいって言ったら行くよ。何かと僕が一人で遊びに行くのにうるさくって」
「一人じゃなけりゃいいじゃないか」
なぁ、と仲頼は行正に同意を求めた。そうだねぇ、と仲忠はのんびりと答えた。
*
「と言う訳で、父上、出かけてもよいでしょうか」
「と言う訳じゃ判らないが、一人じゃあないのだな?」
「この通り仲頼さんと行正さんがお誘いに」
控えている彼らを手を上げ、仲忠は示す。見えている、と父親は思う。
「念のため聞くが、都の外れの怪しい所ではないのだろうね?」
「父上ではありませんのでそういうことはありません」
さらりと仲忠は言う。
背後の二人は思わずのけぞった。何はともあれ、自分達が子供の頃から既に右大将を勤めているひとに。
だがその当人はそんな息子の言いぐさには慣れているのか。
「まあこの二人が一緒なら安心だ。しかし一体、何処まで行くのだい?」
視線を仲頼達に向ける。仲頼は答える。
「紀伊国の吹上の浜のあたりです」
「もしかして、源氏の君の所かい?」
「はい。今朝、松方が先日訪問した折のことを私に色々自慢致しまして。こうなったら行かずにはいられない、と」
ほぉ、と兼雅はうなづく。
「いいねえ。私ももう少し君等の様に身軽だったら行きたいところだ。ぜひ行ってきなさい。仲忠も琴が琴が、とばかり私に聞くが、私はあまり琴のことには詳しくはない。そういうことは、噂よりは実際に行ってみるべきだ」
「父上」
ぱっ、と仲忠の表情が明るくなる。
「私はその間、そなたの母を独り占めするとしよう」
途端に表情が引きつった。
「その方は確か、
「父上は、その方のことをご存じですか?」
そうだな、と兼雅は顎に手をやる。
「ずいぶん昔のことだ。まだそなたの母とも出会う前。童殿上していた頃、時々見かけたことがある。子供心にも美しいひとだった」
「当時から父上は、そういう所には目敏かったですね」
「言うな。それでも、そなたの母が最初の恋人なのだぞ」
「それはよく判っております」
「しかし、そなたの母とはまた違った美しさを持ったひとだった。彼女の父親の
「―――確か、紀伊国では介に次ぐ地位ですが、ずいぶんな物持ちと聞いております」
行正が答える。
「そう。『
「へえ…」
仲頼は思わず口をぽかんと開ける。
「種松という男はかなり有能らしいな。国で三番目の地位にあるなら、人々から搾り取ることもできるだろうが、不平不満を出すこともなく、ずいぶんな成果を上げているらしい。そのせいか、代々の紀伊守も彼には何かと気をつかう。大納言の姫だった北の方を紹介したのも、当時の紀伊守だ」
「それはもう…… ずいぶんと身分違いではないですか」
行正は驚く。うむ、と兼雅は頬杖をつき、大きくうなづく。
「運の悪い方だったのだな。父君と、当時の夫君をほぼ同時に流行病で亡くされた」
「それは確かに、困りますね」
しみじみと仲忠は言い、ちら、と父親を見る。兼雅はその視線に気付いたが、あえて見ない振りをする。
「そこでかつて、故大納言に世話になっていた、当時の紀伊守が姫の身の振り様を心配した。夫君を亡くしたと言ってもまだ若かったし、心映えの良いひとだったから、いっそ自分が、とも思ったらしい」
「よく思いとどまりましたね」
仲頼は肩をすくめる。
「さあそこだ」
兼雅はぽん、と脇息を扇で軽く叩く。
「執心していることは、それでも行動で伝えてはいた様だ。何かと物を届けたり、女ばかりの家の守りを固めたり。だがそれを北の方が知ってしまった」
仲頼と行正は顔を見合わせる。
「まあ可愛そうな姫様、とは言っても奥方、それ以上のことは決して許しませんよとばかりに、守の下の政人の妻達にさりげなくその話を回したのだな。美しく心映えも良い方が困っていらっしゃる。誰か裕福な再婚の当ては無いものか、と」
「それで種松が?」
「いやまず、当時の第二の者…… 介にどうか、という話がきたんだ」
「けど?」
仲忠はふっと笑う。
「駄目だったのですね?」
「まあな。気後れがして文の一つも出すことができない。何せ大納言の姫だ。入内させて、時めくこともできる身分だ。そんな姫にそうそう介程度の男が近寄ることもできまい。普通はな。だがこの神南備種松という男はそうではなかった」
三人の若者は大きくうなづいた。
「彼には
まあそれはそうでしょうね、と行正は内心うなづく。
「家の者が折れれば、もう後は簡単だ。手引きをしてもらい、通いだし、紀伊の守に話を持ちかけ、正式な妻として引き取ってしまった」
「素晴らしい!」
思わず仲頼は膝を叩く。
仲忠はそんな友人をちらり、と横目で見た。
*
そんな経緯から紀伊の国、吹上へと出向いた彼等だったが。
目的の地に辿り着く直前、一行に異変が起きたのだ。


