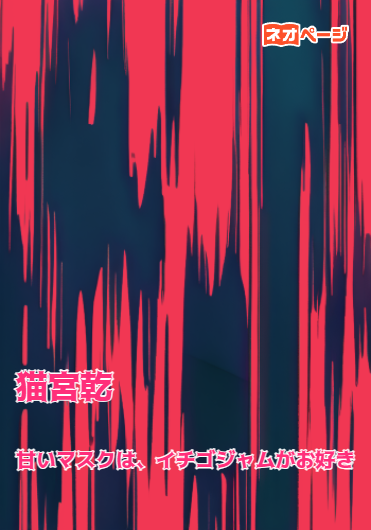
公開日
完結済
第1話 開けっぱなしの遮光カーテン
遮光カーテンの合間から、朝の日射しが入ってくる。
片側を開けたまま眠ってしまった、昨夜の自分を呪う。
今日は折角の非番だというのに、結局はいつもとほぼ変わらない時間に目を覚ました。
艶やかな金色の髪と、青色の形のいい目をしている梓藤は、警備部特殊捜査局第一係の主任をしている。現在二十七歳。大学卒業後に警察学校で学び、すぐに特殊捜査局へと配属された。移動は一度もした事がない。だが周囲が次々と殉死していくため、自動的に昇進していく。
ベッドから降りて、上に着ていた白いTシャツを脱ぎ捨てた梓藤は、百七十二センチのそれなりに筋肉のある体で、一度背を反らして天井を見上げてから、キッチンへと向かった。冷蔵庫を開けてミネラルウォーターのペットボトルを取り出し、キャップを捻る。すると冷ややかな水が、喉を癒やしてくれた。
それから鏡の前へと向かい、手に水を掬って顔を洗い眠気を覚ます。
彼はふと鏡の中の自分を一瞥した。
梓藤は整った顔立ちをしている。少し彫りが深めだ。だが別段ハーフやクォーターというわけでもないし、かといって髪を染めていたり、カラーコンタクトを身につけているわけでもない。昔から梓藤の家には、時折この色彩の者が、科学的な法則を無視するかのように生まれてくる。だから梓藤の周囲の人間は、彼の出生時、特に誰も驚くことはなかったらしい。梓藤は近くのカゴに手を伸ばし、真新しいYシャツの袋を開封して着替えた。
支給されているスマートフォンが着信音を響かせたのは、丁度その時だった。
電話の主が同僚の
「もしもし」
『おはよう、冬親。起きてた?』
「おう。なんだよ、こんなに朝早く。事件か?」
『うん、そうだね。今、君の家の玄関の前まで来てるけど、入っていい?』
「ああ」
頷いた梓藤は、実は非常に寝穢い。寝過ごす事が度々あり、斑目に念のため合鍵を預けている。梓藤はリビングへ向かい、ティーサーバーの下にカップを置き、珈琲を用意する。玄関から斑目が入ってくる気配を感じる。珈琲を二つ淹れ終わり、リビングのソファへと向かった時、斑目もその場に顔を出した。
「ありがとう、冬親」
梓藤を下の名前で呼ぶ人間は、今ではほとんどいない。カップを斑目の前に置き、対面するソファに腰を下ろしつつ、梓藤は親友を見据えた。
いつも穏やかに微笑している斑目は、梓藤の片腕で副主任をしている。少し色素の薄い茶色の髪をしていて、それが柔らかそうに見える。瞳の色も同色だ。
「それで?」
「うん。珍しく捕縛に成功したマスクが、警察車両から脱走したんだって。最悪な事に胴体に被弾しているから、恐らく肉体的が完全に死亡していて、顔からマスクが分離できる状態になっているみたいだよ」
「そうか。これだから生け捕りにしようなんていうのは、無理があると俺は思うんだ」
「まぁまぁ。実際に何度かは、成功例もあるしね。それで、ここから近い西区画の住宅街に逃げ込んだみたいだから、本部に待機していた僕と、非番だけど一番近所にいた冬親とで、マスクを探しをして欲しいって。勿論、もう次は排除対象だから、生け捕る必要はないよ」
斑目の声に頷きながら、ゆっくりと梓藤は珈琲を飲み込む。
「折角の休みだって言うのに、俺も運が悪いな。で? 廣瀬、何か手がかりは?」
「路地の防犯カメラの映像だと、その頃通りかかっていたのは、小学生の女児以外はいなかったみたいだよ。最近にしては比較的珍しい、古き良き赤いランドセルを背負っていたんだってね」
下の名前で相手を呼ぶのは、梓藤も同じだ。それだけ斑目の事を梓藤は信頼しているし、職場の同僚の範囲を超えて、よき友人だと考えている。なにより斑目の微笑を見ていると、どことなく落ち着いた気持ちにさせられるので、梓藤は居心地がよいと感じていた。
「とりあえず、その小学生の身元を確認して、家にでも行ってみるか?」
「もう、住所も氏名も特定済みだよ」
「さすがだな」
「車で来てるから、冬親の準備ができ次第行こうか」
「おう。上着を取ってくる」
こうして二人は、マスクを探し排除するために、梓藤のマンションを後にした。


