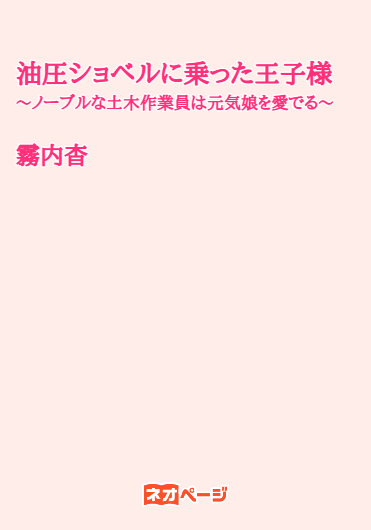
公開日
完結
うちの御曹司は御曹司なのをいいことにセクハラパワハラ放題で。
後輩の涙に耐えられず抗議したら、クビになりました……。
お腹がすいたなー、なんて川辺でぼーっとしていたら飛び込むのかと勘違いされ。
心配してくれたガテン系イケメンのおかげで土木会社に就職できました。
作業員のおっちゃんたちも社長もとてもいい人だ。
特に私に声をかけてくれたお兄さん、暢祐さんは私を可愛がってくれる。
私が恋にウブなのをいいことに時々からかってくるけど、……本気になっちゃうよ?
いい人に囲まれた最高の職場だけれど、ここにもガンはいたのです……。
兎本璃世 うもとりせ 25
ちっちゃくて可愛い元気っ娘
童顔で子供扱いされるのがコンプレックス
正義感が強くてつい口が出がち
×
渡守暢祐 わたしもりのぶひろ 28
土木会社の作業員
爽やかイケメン君だが、したたか
しかしなにやら秘密が……?
私の王子様は油圧ショベルで迎えに来ました!?
「オ、オマエはクビだー!」
顔を真っ赤にし、唾を飛ばして御曹司が怒鳴る。
「こっちこそ、あなたみたいな無能が次期社長の会社なんて願い下げですよ!」
……と、売り言葉に買い言葉で会社をクビになったのが一時間ほど前。
早くも私は、後悔していた。
「……はぁーっ」
川辺のベンチに座り、憂鬱なため息をつく。
なんであんなこと、言っちゃったかなー。
すぐ口が出るのは私の悪い癖だ。
「……はぁーっ」
また、私の口からため息が漏れる。
御曹司に意見したのは後悔していない。
そうしないと後輩が泣くくらいならまだいいが、御曹司から身体に加害を受けるところだった。
それでももうちょっと穏便に話せば、クビは免れていたかもしれない。
「まあ、言っちゃったものは仕方ないんだけど」
私の口から乾いた笑いが落ちていく。
いまさら取り消しもできないし、反ってあんな会社を辞めて清々しているくらいだ。
私のいた会社では御曹司のパワハラ、セクハラが横行していた。
気に入らない人間には到底できない仕事を与え、どうしてできないのかと怒鳴り散らす。
女性社員、特に気に入っている子はオレの女扱い。
既婚者なのに、だ。
なにか意見しようものなら、親父に言って辞めさせてやると脅された。
もう三十も過ぎているのに父親頼りの御曹司もどうかと思うし、社長もひとり息子だからか彼に甘いのだ。
社員の給料は据え置きどころか減給でも、息子には数千万のスポーツカーを買ってやる。
そんな会社なので行く末は見えていた。
「これからどーしよー」
辞めたのに悔いはないが、これから先が困った。
そういう会社だったので給料は生活費でカツカツ、貯蓄などほとんどない。
円満に辞めていれば雀の涙ほどだろうが退職金も出ただろうが、クビなのでもちろんあるわけがない。
さらに喧嘩を売って飛び出てきたのでまともに退職手続きをしてもらえるかも怪しく、失業保険がもらえない可能性もある。
私の気持ちなど知らず、目の前では気持ちよさそうに水鳥が泳いでいる。
ああ、もういっそ、あの鳥になりたい。
などと思っていたら、お腹が派手になった。
お昼も食べていないし、そうなる。
「なんか食べるか……」
腰を浮かせかけて、またその場にへなへなと座り込んだ。
給料日前で財布の中にはほとんどお金が入っていなかった。
バーコード払いで支払っても、引き落とし日にお金がある可能性は低い。
そもそも明日の給料日に、お金が振り込まれるのかすら怪しい状況だ。
「……はぁーっ」
またため息をつき、川面を眺める。
日の光が当たってキラキラして綺麗だが、それよりもお腹が減った。
就職活動をするとして、当面のお金をどうするかが問題だ。
「なあ」
「ひゃっ!」
唐突に頭上から声が降ってきて、飛び上がりそうになった。
こわごわ見上げると、私よりも少し年上そうな眼鏡の男性が立っていた。
「川の水は冷たいだろうし、溺れるのは苦しいと思うぞ」
いいともなんとも言っていないのに、彼が隣に腰掛けてくる。
作業着姿なので近くの工場かなんかの従業員なんだろうか。
それにしてはイケメン……というのは失礼だけれど。
眼鏡の奥の目は細く涼やかで、右目下のほくろがさらに爽やかに見せる。
鼻筋は通っており、薄い唇はキスを誘うかのように形がいい。
少し長めの黒髪はぼさっとしているが、整えればきっと、かなりのいい男に違いない。
「はぁ……?」
なにを言っているのかわからなくて、しばらく考える。
もしかしてこれは、自殺でも考えていると思われているんだろうか。
「なんか悩みがあるなら聞いてやるぞ。
人に話すだけでも気持ちが軽くなる」
ん、と持っていたエコバッグからペットボトルのお茶を取り出し、彼は差し出してきた。
「ありがとう、ございます……」
それを複雑な気持ちで見つめながらも、ありがたく受け取る。
彼が隣でコーラのペットボトルを開け、プシュッと音がした。
そのままごくごくと勢いよく飲み、ぷはーっと最後に彼が炭酸を吐き出す。
なんだかそれが凄く気持ちよさそうで、気が抜けた。
「その。
ご心配はありがたいんですが、死ぬ気なんてまったくないんで」
手持ち無沙汰にもらったペットボトルを手の中で弄ぶ。
「そうなのか?」
さぞ意外そうに彼は黒縁眼鏡の奥で何度か瞬きした。
「滅茶苦茶深刻そうな顔でため息ついてるし、ずっとここにいるからてっきりそうなのかと」
「ずっと……?」
とは、そんなに前からこの人は私を観察していたんだろうか。
「現場から帰るときもここにいたし、コンビニ行くときも。
帰りにまだいたら声かけようと思ってた」
確かにそんな長い時間、こんなところにひとりで佇んでいたら心配になるかもしれない。
私だって声をかけるかも。
「まー、死ぬ気じゃないのはよかったわ。
そんなに若くてこっから先の楽しいことを知らずに死ぬのはもったいないからな」
彼は安心したのか笑っているが、若干引っかかった。
「あのー、若いって私をいくつだと思ってます?」
「ん?
高校生じゃないのか?」
ペットボトルを口に運びかけて止め、彼が不思議そうに私を見る。
「あのですねー、こう見えて一応、社会人なんですが」
口端がピキピキと引き攣るが、仕方ない。
童顔な私は二十五にもなって高校生に間違われるのがコンプレックスなのだ。
少しでも大人っぽく見せようとゆるふわポニテにし、ブルーストライプのシャツに黒パンツなんて格好をしているが、まったくの無駄らしい。
「じゃあ、あれか、高卒新入社員か。
そうだよな、制服じゃないし」
うんうんと彼は頷いていて、私の中でなにかがプチッと切れた。
「もう二十五で、会社でもしっかり後輩指導してたんですが!」
「おう」
食ってかかる私を、彼が両手でどうどうと宥めてくる。
「それは申し訳なかった。
すまない」
真摯に彼は頭を下げてくれた。
それで気が済んだ。
「いえ。
私もよく間違われるので。
その、怒鳴ったりしてすみませんでした」
ぺこんと私も頭を下げ返す。
「いや、いい。
見た目で年齢を判断した俺も悪いし」
しかし彼はなおも謝ってくれた。
もの凄くいい人に見えるのはあの最低御曹司の反動だろうか。
「でも、会社員ならなんで、あんな時間からこんなところにいたんだ?」
「うっ」
彼の疑問はもっともだ。
正確な時間はわからないが、たぶん三時頃からここに座っている。
そして今はようやく終業時間になったくらいだ。
「……か、会社をクビになってですね……」
こんなことを告白するのは恥ずかしく、身を小さく丸め膝の上で拳を堅く握り、だらだらと変な汗を掻きながら視線をあちこちに彷徨わせる。
「クビってなにをしたんだ?」
「そ、それは……」
あれは大人げなかったなと反省したところなので、なおさら言いづらい。
「クビとかよっぽどのことがなければならないだろ」
それは彼の言うとおりなだけに、さらに言いにくくなる。
しかし眼鏡の向こうからじっと見ている彼は言わなければ許してくれそうになかった。
「その。
……社長の息子と喧嘩、して」
きっと呆れているだろうとそろりと彼をうかがう。
けれど彼の表情は変わらなかった。
「喧嘩って、なんで?」
彼の目にはバカにするようなところはまったくない。
こんなに真剣に聞いてくれるのならば、私もそれに応えるべきだ。
「後輩が彼に食事を無理強いされて困っていたので抗議しました。
彼女だけじゃありません、ほかにも何人か、彼にセクハラなんて言葉では片付けられない行為をされた人がいます。
それでもう、我慢できなくなりました」
すんでのところで彼氏さんが気づき、一命を取り留めた先輩。
電話の向こうでずっと泣いていた後輩。
もう、あんなのを見るのはごめんだ。
ぎゅっと強く拳を握り込んだせいで、爪が手のひらに食い込んだ。
「……頑張ったんだな」
その言葉が私の胸に染みていく。
不意になにかが、私の頬を転がり落ちていった。
「えっ、あっ」
慌てて目尻を拭うが、それは次から次へと落ちていく。
「あっ、その」
「うん」
彼の手が伸びてきて、私の拳を握った。
温かいそれに、気持ちが一気に決壊する。
「うっ、うわーっ」
みっともなく子供のようにわんわん泣いた。
そんな私の手を、彼は黙ってじっと握ってくれている。
しばらく泣いて気持ちがすっきりし、ようやく涙は止まった。
「落ち着いたか」
慰めるように私の手を軽くぽんぽんと叩き、彼が離れる。
「はい。
すみませんでした」
「いや、いい」
まだ鼻をぐずぐずいわせている私に彼は首にかけていたタオルを渡しかけて、やめた。
なんかそれがおかしくて、少し笑っていた。
「今ならあれは間違ってたってわかるんですけどね」
泣きすぎて喉が渇き、ペットボトルを開ける。
すっかりぬるくなったお茶は優しく私の喉を潤していった。
「間違ってた?」
彼の声は怪訝そうだ。
たぶん、誤解をしている。
「はい。
カッとならず、もっと冷静に抗議するべきでした。
それでダメなら、しかるべきところに訴えればよかった。
じゃないと……」
視線を地面へと落とした。
御曹司の横暴は続き、被害者は出続ける。
「そうだな。
でも君は、許せなかったんだろ?」
「そう、ですね」
わかっていても、あの時間に戻り後輩から今にも泣き出しそうな、必死に縋る目で見られたらやはり、カッとなって食ってかかっている自信がある。
「君は頑張った、偉いよ」
「偉くなんかないです」
彼は褒めてくれるが、私はただ考えなしに御曹司と喧嘩をしたに過ぎない。
もしかしたら私のせいで、さらなる被害者が出たのかも。
そう思い至ると身体が冷えた。
「少なくともその後輩はきっと、君に感謝しているよ」
「……そう、言ってもらえると嬉しいです」
彼の手がまた、ぽんぽんと私の手を叩く。
それで幾分、私が救われた。
「あーもー、お腹空いたな!」
勢いよくベンチから立ち上がる。
彼が話を聞いてくれたおかげで、前向きに動こうという気力が湧いてきた。
お金はないがバーコード払いの前借りで、とりあえずお腹いっぱいなんか食べよう。
仕事が見つからなければ実家に帰ってもいい。
……後輩は今後の幸せを祈るしかできないけれど。
「なんだ、腹減ってるのか」
少し遅れて彼も立ち上がる。
並ぶとかなり背が高い。
背の低い私など、見上げないといけないくらいだ。
「メシ、食いに連れていってやるよ」
高い背を屈めて私の顔をのぞき込み、彼はにかっと笑った。
「え、いいですよ!」
見ず知らずの私に、事情まで聞いてくれてそこまでしてもらうのは申し分けなさすぎる。
「いいからほら、行こうぜ。
俺も腹、減ってるんだ」
促すように彼が、背中を思いっきり叩いてきた。
「あいたっ!」
睨んだけれど彼は涼しい顔をしていてまったく効いていない。
「なにが食いたい?
焼き肉もいいよなー」
「え、私、お金ないですよ!」
歩き出した彼と一緒に私も歩く。
「奢ってやるから心配するな」
「ほんとですか?
やったー」
あのベンチに座ったときはもう一生あそこから動けそうにないほど心は重かったが、彼のおかげですっかり軽くなっていた。


